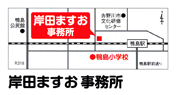令和元年12月定例会 一般質問 薫風会 岸田益雄
おはようございます
原井市長におかれましては、今回の市長選挙で2代目吉野川市長
のご当選おめでとうございます。
また、岡田副市長におかれましても、先日の議会承認を受けての、
副市長ご就任おめでとうございます。
市長・副市長共に、職員の皆さんと一緒になって、吉野川市民の
幸わせと市の発展に努力していただきたいと思います。
市民の代表である われわれ議員も、議会や委員会、また普段の
議員活動を通じて、市民の皆様の意見・要望や提案を市当局に伝える
とともに、一緒に考えて、吉野川市の更なる発展を考えていきたいと
思っておりますので、よろしくお願いいたします。
それでは、議長の許可を頂きましたので、通告書に従って質問を
行いたいと思います。
1.子育て環境の充実について
(1)放課後児童クラブの現状は
(2)放課後児童クラブの保護者の負担は
(3)移動時の安全対策は
○質問
ライフスタイルの多様化や女性の社会進出が進み、子育て世代の
共働きが増えております。
また、色々な事情によって乳幼児や児童を抱えた母子家庭、父子
家庭などのひとり親家庭も増加傾向にあります。子育てと働くこと
を両立させたい家庭にとって、安心して子供を預けられる場所の
存在は不可欠であります。
本市では、幼保再編が進み、公立施設として、認定こども園が山川
の高越こども園、川島の川島こども園、今年度開園した鴨島東こども園
とあり、また呉郷保育所、鴨島幼稚園、知恵島幼稚園とあります。私立
の施設として、鴨島かもめこども園、山瀬かもめこども園、鴨島ひかり乳
幼児保育園、それと現在は改築中ですが来年度は鴨島幼稚園・知恵島幼稚
園・鴨島中央保育園が一緒になって(仮称)認定こども園鴨島中央が誕生
し、市内全域で0歳から5歳までの子供たちの受け皿が出来、幼保再編化
計画も大きな区切りを迎えようとしています。
認定こども園や保育所、幼稚園では延長保育や預かり保育の制度が
あり、仕事や家庭の事情などにあわせて、保育時間に多少なりとも融
通が利くと聞いております。
しかし、子供たちが小学校に入学すると事情が一変し、1年生で入学
して4月中は学校に慣れる期間として、午前中の授業のみとなり正午
過ぎに下校となります。
それ以降も、1年生2年生はおおむね午後3時過ぎに下校、3年から
6年生はおおむね午後4時過ぎに下校となり、帰宅した時に保護者が
家にいる家庭は良いですが、前述したように家庭の事情で家に帰っても
夜まで誰もいない家庭が増えています。
その子どもたちの居場所として、鴨島児童館、鴨島南児童館、八坂児
童館などの児童館がありますが、保護者の皆さんの高まるニーズに応え
る受け皿として、放課後児童クラブがあります。
近年の女性就業率の上昇により、さらなる共稼ぎ家庭等の児童数の
増加が見込まれることで、放課後児童クラブの整備は必要であります。
すべての児童が放課後を安全・安心に過ごし多様な体験・活動を行う
ことができるように、放課後児童クラブの整備を推進するために、平成
30年9月に「新・放課後子ども総合プラン」が公表されました。
これは、平成27年度(2015)に発表された「放課後子ども総合
プラン」が4年間の施行期間が過ぎ、1年間前倒しされて見直されたもの
で、放課後児童クラブの量的拡充を図り、2021年度末までに約25万
人分を整備し待機児童の解消を目指し、女性就業率の上昇を踏まえ20
23年度末までにさらに約5万人分を整備し、5年間で約30万人分の
受け皿を整備することを目標としています。
また、全ての小学校区で両事業を一体的に又は連携して実施し、うち
小学校内で一体型として一万箇所以上で実施することを目指す。
さらに、両事業を新たに整備する場合には、学校施設を徹底的に活用
することとし、新たに開設する放課後児童クラブの約80%を小学校内
で実施することを目指すとあり、子どもの主体性を尊重し、子どもの健全
な育成を図る放課後児童クラブの役割を徹底し、子どもの自主性、社会性
等のより一層の向上を図るとあります。
そこで、お伺いいたしますが。
本市の放課後児童クラブの現状を教えて頂きたい、
さらに、以前の同僚議員の質問で市内の各放課後児童クラブでの保護
者負担が不均衡ではないのかとの質問もありましたが、現在の保護者
負担の現状を合わせて質問いたします。
また、「新・放課後子ども総合プラン」では、放課後児童クラブ
は小学校内に設置するのが望ましいとしていますが、現実は全ての
放課後児童クラブが小学校と隣接しているわけではありません。
小学校を出てから放課後児童クラブに通うまでの安全対策は、学
校、放課後児童クラブ、保護者や地域の方々との連携が欠かせないと
思いますので、お互いが密に連絡を取り合って安全を確保してほし
いと思いますが、放課後児童クラブと小学校はどのような連絡体
制や安全対策を行っているのかお伺いします。
〇答弁 宮本健康福祉部長
「子育て環境の充実について」のご質問にご答弁申し上げます。
まず、放課後児童クラブの現状についてでございますが、
吉野川市内には、鴨島地区に9ヶ所、川島地区に2ヶ所、山川地区
に4ヶ所、合計15ヶ所の放課後児童クラブがあり、平成31年4月
1日現在で606名の小学生が利用しております。
各児童クラブは、保護者負担金と国・県・市からの補助金で運営が
行われています。
各放課後児童クラブの施設の現状でございますが、学校法人と吉
野川市内の旧学習塾跡を利用しているところを除けば、市内公民館内、
こども園移転後の幼稚園の利用、小学校敷地内等、公的施設内や公的
施設跡を利用しています。
次に、現在の放課後児童クラブの保護者負担の現状でございますが、
保護者負担は、保護者や各運営委員組織がそれぞれ決定しており、
指導員の賃金、人数、開設時間、また、春・夏・冬休み等の長期休暇の
開設時間、発達障害児の受け入れなどによって、地域の実情や児童クラ
ブ設立経過の事情によって異なっています。
金額は、学校法人を除けば、月額、おやつ代を含み4,000円から
10,000円までのあいだで徴収されており、各児童クラブの予算の
範囲内で独自性をいかした運営体制を構築し、それぞれ独自の特色を
いかしたものになっております。
また、保護者負担金につきましては、保護者からの申し出があり、
一定の要件を満たせば、毎月の利用料が無料、または、毎月の利用料
より3,000円以内の軽減を受けることができます。
次に、放課後児童クラブと小学校はどのような連絡体制や安全対
策を行っているかについてでございますが
放課後児童クラブより、小学校に要請し、行事計画等の情報を提供
していただくとともに、急な下校時間の変更の際には、その都度、電話
連絡をしていただくなど、連携を図っております。
放課後児童クラブにつきましては学校での教育活動が終了した後、
各施設に子どもたちが移動しています。この施設間の移動が発生する
ことにつきましては、保護者も子どもも認識しております。
この際の児童の安全対策といたしましては、運営主体であります保
護者会において、危険箇所の点検や子供たちの見守りなど、学校や地域
の皆様、関係機関と連携を図りながら、安全の確保に努めていただいて
いるところでございます。
今後も、放課後児童クラブの実態に合わせた安全対策・安全確保が
できるよう、保護者会と連携を図ってまいりたいと考えております。
○再問
ありがとうございました。
現在、市内の鴨島地区には上浦児童クラブ、森山児童クラブ、牛島
児童クラブ、めぐみファミリーダンボクラス、鴨島児童クラブ、リアン
鴨島児童クラブ、ひまわり児童クラブ、知恵島児童クラブ、西麻植児童
クラブ、川島地区には川島児童クラブ、学島児童クラブ、山川・美郷地
区には、山瀬学童保育所のびのびクラブ、山瀬学童保育所ほのぼのクラブ、
高越学童おひさまクラブ、高越学童あおぞらクラブと、15の放課後児童
クラブがありますが、それぞれ利用している施設が、小学校内であったり
旧の幼稚園を利用したり、公民館や市の施設を利用したり、民間の施設を
賃貸で利用したりして様々な形態で運営されています。
それぞれ各地域の小学校の近辺に設置されていますが、地域によれば
児童数が多くて放課後児童クラブに、入れない児童いわゆる待機児童
もいるのではないでしょうか?
国の「新・放課後子ども総合プラン」では、2017年5月時点で待機
児童数が約17000人ですが、自治体を支援し3年間で待機児童を
解消し2021年度末には0にするのを目標としています。
また、女性(25歳から44歳)の就業率は2016年度で72.7%
であるが2023年度末には80%に上昇するとして、放課後児童クラ
ブの受け皿を30万人分整備するとしています。
そこで現在、市内の放課後児童クラブでの待機児童はいるのか、また
今後、増加が見込まれる地域での放課後児童クラブの施設整備や運営
に関しての課題や「新・放課後子ども総合プラン」に対する今後の取組
みを再問いたします。
〇答弁 宮本健康福祉部長
再問にご答弁申し上げます。
現在、待機児童につきましては、発生していないという状況でござ
います。
議員からお話がありましたように「新・放課後子ども総合プラン」に
おいて、「放課後児童クラブ・放課後子ども教室の両事業を新たに整備
等する場合には、学校施設を徹底的に活用することとし、新たに開設する
放課後児童クラブの約80%を小学校内で実施することを目指す。」と
あります。
これらの事業を新たに始める場合は、学校施設の余裕教室を最大限
活用することが求められますが、学校施設の管理区分を明確にする
必要があります。このプランを推進するには、場所や人材の確保など
根本的な課題もありますが、地域の、あるいは保護者のニーズも踏まえ
ながら、児童の放課後の居場所づくりについて、関係部局と協議・連携
しながら検討してまいります。
以上でございます。
〇要望
ありがとうございました。
現在のところ、放課後児童クラブの待機児童はゼロということで
安心いたしましたが、今後、女性の就業率のアップと共に、放課後
児童クラブの利用者が増加することも考えられますので、このことも
踏まえて、関係部局との連携を密にしておいてください。
これからの将来をになう、こどもたちが安全・安心して成長する
ためには、小学校だけではなく、児童館や放課後児童クラブの役割
も大きなものがあります。
市長の所信にもありました、「子育て・教育の満足度向上」には、
児童の放課後の時間を安全・安心に過ごせる放課後児童クラブは
必要不可欠なものであると思います。
放課後児童クラブは、それぞれ市内の地域ごとに、環境や条件も
違うと思いますので、市としても各児童クラブの現状に合せた対応
をして頂き、子どもたちが朝家を出てから、元気に家に帰るまで安全
・安心に過ごせますように目を行き届かせてくださいますことをお願
いして、この質問を終わることにいたします。
2.東部都市計画について
(1)都市計画の見直しは
(2)今後の対応は
昭和47年決定の徳島東部都市計画において、県や市が(当時は
鴨島町)今後の徳島県東部の都市の発展を見越して、徳島東部都市
計画図を作成し、市街地に東西又は南北に走る県道や市道の新路線
を発表しました。
市は、喜来上下島線、鴨島上下島線、本郷春日免線、新開地中央通
線、知恵島中島線、喜来知恵島線、喜来東西支線の7つの新しい市道
を発表しました。
喜来上下島線は知恵島のバイパスからセレブ東の三叉路までの間で
平成9年3月開通、鴨島上下島線は鴨島小学校西の踏切から鴨島郵
便局西の国道192号の交差点の間で平成13年11月開通、本郷春日
免線はセレブ東の三叉路から国道192号をこえて鴨の湯東の県道交
差点までの間で平成24年3月開通していますが、
新開地中央通線は鴨島駅北側から吉野川市斎場南のバイパス信号
までの南北の道路で平成15年3月鴨島駅北側の一部を残し開通、
知恵島中島線は吉野川高校東の南北の道路で知恵島のバイパスから
国道192号までの間ですが平成7年3月に吉野川高校東のみ整備
されております。
しかし、喜来知恵島線(吉野川高校前から喜来第5団地の上を通
り国道318号までの東西の道路)、喜来東西支線(喜来の村本タバコ
屋前の三叉路からうめがわ商店前に抜ける東西の道路)は、まだ何も
手付かずの状態です。この計画路線の線引きの見直しを市はどのよう
に考えているかお伺いいたします。
昭和の時代に、国の発展のために国土開発計画や都市計画があちら
こちらで立案され、実施されました。
しかし、少子高齢化や人口減少が急激に進む、昭和から平成の時代
を経て、令和の時代となり、開発計画や都市計画の見直しが各地で行
われております。
本市においても、今後どのような計画でまちづくりを行っていくの
かを質問いたします。
〇答弁 小澤建設部長
東部都市計画についてに、ご答弁申し上げます。
旧鴨島町は、昭和46年に鴨島町全域が徳島東部都市計画地域
に指定され、その中から当時鴨島町役場や鴨島駅を中心とした区
域を市街化区域として指定し、主に都市計画道路を整備すること
で都市の骨格となる道路の整備を行いました。
これらの都市計画道路を整備する際には、鴨島中央通線、喜来
上下島線等の市街地の中心に位置し、重要度の高い路線から着手
し、その後、その周辺部にある路線の整備を進めて、現在6線が
完成しております。
この6線の都市計画道路を軸として現在の市街地は形成されて
おり、主要な都市計画道路の整備は既に終えていると考えています。
未整備である3路線は、市街地の外周に位置しており、今後、本市
でも急激な人口減少が進み市街地の縮小などにより、重要性が少なく
なると考えられるため、事業を廃止したいと考えています。
また、今後のまちづくりについては、急速な人口減少と少子・
高齢化に対応した、安心して暮らせる持続的なまちづくりの推進
を行って行かなければなりません。
出来るだけ早く、立地適正化計画の作成に着手したいと考えて
おります。
この計画は、高齢者や子育て世代の方々にとって、安心できる
健康で快適な生活環境を実現し、持続可能な都市経営が可能とな
るよう立地の適正化を行うための計画です。具体的には、都市機
能誘導区域、居住誘導区域を設定し、その地域の目的に合った施
設の誘導を行うものです。この立地適正化計画が反映された都市
計画マスタープランの中で、新たなまちづくりの方向を考えてい
くことになります。
〇再問
ありがとうございました。
未整備の3路線は事業を廃止したいと考えており、今後は立地
適正化計画の作成に着手するということですが、この立地適正
化計画は平成26年に始まりました。
国土交通省の施策であるコンパクトシティ形成支援事業で、対
象は「コンパクトなまちづくりを推進するため、立地適正化計
画等の計画立案や、医療、福祉施設等の集約地域への移転促進、
移転跡地の都市的土地利用からの転換等に対する支援を行う。」
とあり、平成30年6月には、「まち・ひと・しごと創生基本方針
2018」では、コンパクトシティ・プラス・ネットワークの
本格的推進が挙げられ、立地適正化計画等に取り組む地方公共
団体に対して、関係省庁が連携したコンサルティングや支援施
策の充実を行うとあります。
コンパクト・プラス・ネットワークのための計画制度では、都
市全体の構造を見渡しながら、居住機能や医療・福祉・商業等
の都市機能の誘導と、それに連携した持続可能な地域公共交通
ネットワークの形成を推進。
必要な機能の誘導・集約に向けた市町村の取組を推進するため、
計画の作成・実施を予算措置で支援とあります。
現在、鴨島駅前周辺地区都市再生整備計画で、アリーナ・交流
センターの整備が行われております。
また、都市再生整備事業として鴨島駅東線拡幅と駐車場整備を
計画し国から事業承認されている四国銀行鴨島支店跡地を事業
用地として市が購入し、令和2年度に駅前広場とその周辺を再
開発する予定とのことですが、鴨島駅前周辺の住民の方々の生
活道路の部分もありますし、JR鴨島駅も1日に約1800人
の乗降客が利用していますので、工事を行う際には、住民の方
々への事前の十分な周知と、工事期間中の安全対策に気を付けて
頂きたいと思います。
ちなみに、2018年度の徳島県内のJR駅1日あたりの乗降客数は
、徳島駅が16224人でトップ、2位が阿南駅で3134人、3位が勝瑞
駅で2410人、以下、石井駅、南小松島駅と続き、鴨島駅は6位で
1850人となっています。
また、銀座・文楽地区の道路・排水路整備についても、住民の
皆さんへの周知や安全対策をお願いいたします。
また、当初の予定では、関連事業として銀座通りのアーケード
撤去、駅前通りのアーケード改修とありましたが、これらの事
業を、立地適正化計画に反映させることはできないでしょうか。
今後の都市計画にどのように取り組んで行く予定なのかを再問
いたします。
また、都市計画道路のうち未整備である3路線は廃止する考え
とのことですが、今後のスケジュールについてもお伺いいたします。
〇答弁 小澤建設部長
今後の取り組みとしましては、当初計画に基づき、令和2年
3月末の吉野川市民プラザの完成後、令和2年度において鴨島
駅前広場周辺整備、令和3年度に鴨島駅東部主に銀座・文楽地
区の道路・排水施設の整備を行います。
銀座通り・駅前通りのアーケード改修につきましては、地元
商店街の皆様と協議し、今後の商店街活性化の取り組みや展望
などを踏まえた中で検討して参りたいと考えています。
先ほどご説明しました、立地適正化計画においては、現在進め
ている事業を反映できるよう、進めて参りたいと考えています。
次に、都市計画道路の廃止に向けて、今後のスケジュールに
つきましては、既に廃止に向けた協議を県と行いましたが、事
業廃止の環境が整っていないとの理由で現在も協議継続中です。
昨今、国土交通省及び県からは、コンパクトシティ・プラス・
ネットワークといった集約型都市の整備が呼びかけられ、市街
地の縮小が求められていることから、本市でも立地適正化計画
の策定が急がれる状況にあります。このことも踏まえ、事業廃
止の環境を整えるために計画を策定し、その際に未整備である
3路線の廃止の協議を進めて参りたいと考えています。
その後、マスタープラン等、上位計画の変更に向けて、都市
計画道路の廃止を記載した上で、県との協議とともに、住民説明
会等の手続きを進めて参りたいと考えています。
〇要望
ありがとうございました。
昭和の経済成長期の遺産が、今もなお、残っていて、旧の鴨島
地区では市街化区域や調整区域や道路等の線引きによって不自由
な思いをしている市民の方も大勢いらっしゃると聞いております。
時代に即した都市計画を立てて、迅速に実施することが大切な
事だと思いますので、国や県との交渉や協議もしっかりと早め
に実行して頂きたいと思います。
来春には、吉野川市のランドマークとなるアリーナが完成し、
鴨島駅前広場周辺整備も始まります。
1日約1800人が利用する、吉野川市の玄関口となる鴨島
駅を下りた時に、駅前には時計台と五九郎さんの石碑しか目に
入りません、駅前広場の整備を行うのなら、アリーナへ通じる
場所に何かシンボル的なインパクトのあるモニュメントなどを
設置出来ないものでしょうか。
市外からJRを利用して来る人々に、魅力ある街を印象づけ
るのに駅前広場からアリーナにかけてのアクセス空間を工夫
して、吉野川市の魅力を発信できる場所となることを要望して、
私の質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
おはようございます
原井市長におかれましては、今回の市長選挙で2代目吉野川市長
のご当選おめでとうございます。
また、岡田副市長におかれましても、先日の議会承認を受けての、
副市長ご就任おめでとうございます。
市長・副市長共に、職員の皆さんと一緒になって、吉野川市民の
幸わせと市の発展に努力していただきたいと思います。
市民の代表である われわれ議員も、議会や委員会、また普段の
議員活動を通じて、市民の皆様の意見・要望や提案を市当局に伝える
とともに、一緒に考えて、吉野川市の更なる発展を考えていきたいと
思っておりますので、よろしくお願いいたします。
それでは、議長の許可を頂きましたので、通告書に従って質問を
行いたいと思います。
1.子育て環境の充実について
(1)放課後児童クラブの現状は
(2)放課後児童クラブの保護者の負担は
(3)移動時の安全対策は
○質問
ライフスタイルの多様化や女性の社会進出が進み、子育て世代の
共働きが増えております。
また、色々な事情によって乳幼児や児童を抱えた母子家庭、父子
家庭などのひとり親家庭も増加傾向にあります。子育てと働くこと
を両立させたい家庭にとって、安心して子供を預けられる場所の
存在は不可欠であります。
本市では、幼保再編が進み、公立施設として、認定こども園が山川
の高越こども園、川島の川島こども園、今年度開園した鴨島東こども園
とあり、また呉郷保育所、鴨島幼稚園、知恵島幼稚園とあります。私立
の施設として、鴨島かもめこども園、山瀬かもめこども園、鴨島ひかり乳
幼児保育園、それと現在は改築中ですが来年度は鴨島幼稚園・知恵島幼稚
園・鴨島中央保育園が一緒になって(仮称)認定こども園鴨島中央が誕生
し、市内全域で0歳から5歳までの子供たちの受け皿が出来、幼保再編化
計画も大きな区切りを迎えようとしています。
認定こども園や保育所、幼稚園では延長保育や預かり保育の制度が
あり、仕事や家庭の事情などにあわせて、保育時間に多少なりとも融
通が利くと聞いております。
しかし、子供たちが小学校に入学すると事情が一変し、1年生で入学
して4月中は学校に慣れる期間として、午前中の授業のみとなり正午
過ぎに下校となります。
それ以降も、1年生2年生はおおむね午後3時過ぎに下校、3年から
6年生はおおむね午後4時過ぎに下校となり、帰宅した時に保護者が
家にいる家庭は良いですが、前述したように家庭の事情で家に帰っても
夜まで誰もいない家庭が増えています。
その子どもたちの居場所として、鴨島児童館、鴨島南児童館、八坂児
童館などの児童館がありますが、保護者の皆さんの高まるニーズに応え
る受け皿として、放課後児童クラブがあります。
近年の女性就業率の上昇により、さらなる共稼ぎ家庭等の児童数の
増加が見込まれることで、放課後児童クラブの整備は必要であります。
すべての児童が放課後を安全・安心に過ごし多様な体験・活動を行う
ことができるように、放課後児童クラブの整備を推進するために、平成
30年9月に「新・放課後子ども総合プラン」が公表されました。
これは、平成27年度(2015)に発表された「放課後子ども総合
プラン」が4年間の施行期間が過ぎ、1年間前倒しされて見直されたもの
で、放課後児童クラブの量的拡充を図り、2021年度末までに約25万
人分を整備し待機児童の解消を目指し、女性就業率の上昇を踏まえ20
23年度末までにさらに約5万人分を整備し、5年間で約30万人分の
受け皿を整備することを目標としています。
また、全ての小学校区で両事業を一体的に又は連携して実施し、うち
小学校内で一体型として一万箇所以上で実施することを目指す。
さらに、両事業を新たに整備する場合には、学校施設を徹底的に活用
することとし、新たに開設する放課後児童クラブの約80%を小学校内
で実施することを目指すとあり、子どもの主体性を尊重し、子どもの健全
な育成を図る放課後児童クラブの役割を徹底し、子どもの自主性、社会性
等のより一層の向上を図るとあります。
そこで、お伺いいたしますが。
本市の放課後児童クラブの現状を教えて頂きたい、
さらに、以前の同僚議員の質問で市内の各放課後児童クラブでの保護
者負担が不均衡ではないのかとの質問もありましたが、現在の保護者
負担の現状を合わせて質問いたします。
また、「新・放課後子ども総合プラン」では、放課後児童クラブ
は小学校内に設置するのが望ましいとしていますが、現実は全ての
放課後児童クラブが小学校と隣接しているわけではありません。
小学校を出てから放課後児童クラブに通うまでの安全対策は、学
校、放課後児童クラブ、保護者や地域の方々との連携が欠かせないと
思いますので、お互いが密に連絡を取り合って安全を確保してほし
いと思いますが、放課後児童クラブと小学校はどのような連絡体
制や安全対策を行っているのかお伺いします。
〇答弁 宮本健康福祉部長
「子育て環境の充実について」のご質問にご答弁申し上げます。
まず、放課後児童クラブの現状についてでございますが、
吉野川市内には、鴨島地区に9ヶ所、川島地区に2ヶ所、山川地区
に4ヶ所、合計15ヶ所の放課後児童クラブがあり、平成31年4月
1日現在で606名の小学生が利用しております。
各児童クラブは、保護者負担金と国・県・市からの補助金で運営が
行われています。
各放課後児童クラブの施設の現状でございますが、学校法人と吉
野川市内の旧学習塾跡を利用しているところを除けば、市内公民館内、
こども園移転後の幼稚園の利用、小学校敷地内等、公的施設内や公的
施設跡を利用しています。
次に、現在の放課後児童クラブの保護者負担の現状でございますが、
保護者負担は、保護者や各運営委員組織がそれぞれ決定しており、
指導員の賃金、人数、開設時間、また、春・夏・冬休み等の長期休暇の
開設時間、発達障害児の受け入れなどによって、地域の実情や児童クラ
ブ設立経過の事情によって異なっています。
金額は、学校法人を除けば、月額、おやつ代を含み4,000円から
10,000円までのあいだで徴収されており、各児童クラブの予算の
範囲内で独自性をいかした運営体制を構築し、それぞれ独自の特色を
いかしたものになっております。
また、保護者負担金につきましては、保護者からの申し出があり、
一定の要件を満たせば、毎月の利用料が無料、または、毎月の利用料
より3,000円以内の軽減を受けることができます。
次に、放課後児童クラブと小学校はどのような連絡体制や安全対
策を行っているかについてでございますが
放課後児童クラブより、小学校に要請し、行事計画等の情報を提供
していただくとともに、急な下校時間の変更の際には、その都度、電話
連絡をしていただくなど、連携を図っております。
放課後児童クラブにつきましては学校での教育活動が終了した後、
各施設に子どもたちが移動しています。この施設間の移動が発生する
ことにつきましては、保護者も子どもも認識しております。
この際の児童の安全対策といたしましては、運営主体であります保
護者会において、危険箇所の点検や子供たちの見守りなど、学校や地域
の皆様、関係機関と連携を図りながら、安全の確保に努めていただいて
いるところでございます。
今後も、放課後児童クラブの実態に合わせた安全対策・安全確保が
できるよう、保護者会と連携を図ってまいりたいと考えております。
○再問
ありがとうございました。
現在、市内の鴨島地区には上浦児童クラブ、森山児童クラブ、牛島
児童クラブ、めぐみファミリーダンボクラス、鴨島児童クラブ、リアン
鴨島児童クラブ、ひまわり児童クラブ、知恵島児童クラブ、西麻植児童
クラブ、川島地区には川島児童クラブ、学島児童クラブ、山川・美郷地
区には、山瀬学童保育所のびのびクラブ、山瀬学童保育所ほのぼのクラブ、
高越学童おひさまクラブ、高越学童あおぞらクラブと、15の放課後児童
クラブがありますが、それぞれ利用している施設が、小学校内であったり
旧の幼稚園を利用したり、公民館や市の施設を利用したり、民間の施設を
賃貸で利用したりして様々な形態で運営されています。
それぞれ各地域の小学校の近辺に設置されていますが、地域によれば
児童数が多くて放課後児童クラブに、入れない児童いわゆる待機児童
もいるのではないでしょうか?
国の「新・放課後子ども総合プラン」では、2017年5月時点で待機
児童数が約17000人ですが、自治体を支援し3年間で待機児童を
解消し2021年度末には0にするのを目標としています。
また、女性(25歳から44歳)の就業率は2016年度で72.7%
であるが2023年度末には80%に上昇するとして、放課後児童クラ
ブの受け皿を30万人分整備するとしています。
そこで現在、市内の放課後児童クラブでの待機児童はいるのか、また
今後、増加が見込まれる地域での放課後児童クラブの施設整備や運営
に関しての課題や「新・放課後子ども総合プラン」に対する今後の取組
みを再問いたします。
〇答弁 宮本健康福祉部長
再問にご答弁申し上げます。
現在、待機児童につきましては、発生していないという状況でござ
います。
議員からお話がありましたように「新・放課後子ども総合プラン」に
おいて、「放課後児童クラブ・放課後子ども教室の両事業を新たに整備
等する場合には、学校施設を徹底的に活用することとし、新たに開設する
放課後児童クラブの約80%を小学校内で実施することを目指す。」と
あります。
これらの事業を新たに始める場合は、学校施設の余裕教室を最大限
活用することが求められますが、学校施設の管理区分を明確にする
必要があります。このプランを推進するには、場所や人材の確保など
根本的な課題もありますが、地域の、あるいは保護者のニーズも踏まえ
ながら、児童の放課後の居場所づくりについて、関係部局と協議・連携
しながら検討してまいります。
以上でございます。
〇要望
ありがとうございました。
現在のところ、放課後児童クラブの待機児童はゼロということで
安心いたしましたが、今後、女性の就業率のアップと共に、放課後
児童クラブの利用者が増加することも考えられますので、このことも
踏まえて、関係部局との連携を密にしておいてください。
これからの将来をになう、こどもたちが安全・安心して成長する
ためには、小学校だけではなく、児童館や放課後児童クラブの役割
も大きなものがあります。
市長の所信にもありました、「子育て・教育の満足度向上」には、
児童の放課後の時間を安全・安心に過ごせる放課後児童クラブは
必要不可欠なものであると思います。
放課後児童クラブは、それぞれ市内の地域ごとに、環境や条件も
違うと思いますので、市としても各児童クラブの現状に合せた対応
をして頂き、子どもたちが朝家を出てから、元気に家に帰るまで安全
・安心に過ごせますように目を行き届かせてくださいますことをお願
いして、この質問を終わることにいたします。
2.東部都市計画について
(1)都市計画の見直しは
(2)今後の対応は
昭和47年決定の徳島東部都市計画において、県や市が(当時は
鴨島町)今後の徳島県東部の都市の発展を見越して、徳島東部都市
計画図を作成し、市街地に東西又は南北に走る県道や市道の新路線
を発表しました。
市は、喜来上下島線、鴨島上下島線、本郷春日免線、新開地中央通
線、知恵島中島線、喜来知恵島線、喜来東西支線の7つの新しい市道
を発表しました。
喜来上下島線は知恵島のバイパスからセレブ東の三叉路までの間で
平成9年3月開通、鴨島上下島線は鴨島小学校西の踏切から鴨島郵
便局西の国道192号の交差点の間で平成13年11月開通、本郷春日
免線はセレブ東の三叉路から国道192号をこえて鴨の湯東の県道交
差点までの間で平成24年3月開通していますが、
新開地中央通線は鴨島駅北側から吉野川市斎場南のバイパス信号
までの南北の道路で平成15年3月鴨島駅北側の一部を残し開通、
知恵島中島線は吉野川高校東の南北の道路で知恵島のバイパスから
国道192号までの間ですが平成7年3月に吉野川高校東のみ整備
されております。
しかし、喜来知恵島線(吉野川高校前から喜来第5団地の上を通
り国道318号までの東西の道路)、喜来東西支線(喜来の村本タバコ
屋前の三叉路からうめがわ商店前に抜ける東西の道路)は、まだ何も
手付かずの状態です。この計画路線の線引きの見直しを市はどのよう
に考えているかお伺いいたします。
昭和の時代に、国の発展のために国土開発計画や都市計画があちら
こちらで立案され、実施されました。
しかし、少子高齢化や人口減少が急激に進む、昭和から平成の時代
を経て、令和の時代となり、開発計画や都市計画の見直しが各地で行
われております。
本市においても、今後どのような計画でまちづくりを行っていくの
かを質問いたします。
〇答弁 小澤建設部長
東部都市計画についてに、ご答弁申し上げます。
旧鴨島町は、昭和46年に鴨島町全域が徳島東部都市計画地域
に指定され、その中から当時鴨島町役場や鴨島駅を中心とした区
域を市街化区域として指定し、主に都市計画道路を整備すること
で都市の骨格となる道路の整備を行いました。
これらの都市計画道路を整備する際には、鴨島中央通線、喜来
上下島線等の市街地の中心に位置し、重要度の高い路線から着手
し、その後、その周辺部にある路線の整備を進めて、現在6線が
完成しております。
この6線の都市計画道路を軸として現在の市街地は形成されて
おり、主要な都市計画道路の整備は既に終えていると考えています。
未整備である3路線は、市街地の外周に位置しており、今後、本市
でも急激な人口減少が進み市街地の縮小などにより、重要性が少なく
なると考えられるため、事業を廃止したいと考えています。
また、今後のまちづくりについては、急速な人口減少と少子・
高齢化に対応した、安心して暮らせる持続的なまちづくりの推進
を行って行かなければなりません。
出来るだけ早く、立地適正化計画の作成に着手したいと考えて
おります。
この計画は、高齢者や子育て世代の方々にとって、安心できる
健康で快適な生活環境を実現し、持続可能な都市経営が可能とな
るよう立地の適正化を行うための計画です。具体的には、都市機
能誘導区域、居住誘導区域を設定し、その地域の目的に合った施
設の誘導を行うものです。この立地適正化計画が反映された都市
計画マスタープランの中で、新たなまちづくりの方向を考えてい
くことになります。
〇再問
ありがとうございました。
未整備の3路線は事業を廃止したいと考えており、今後は立地
適正化計画の作成に着手するということですが、この立地適正
化計画は平成26年に始まりました。
国土交通省の施策であるコンパクトシティ形成支援事業で、対
象は「コンパクトなまちづくりを推進するため、立地適正化計
画等の計画立案や、医療、福祉施設等の集約地域への移転促進、
移転跡地の都市的土地利用からの転換等に対する支援を行う。」
とあり、平成30年6月には、「まち・ひと・しごと創生基本方針
2018」では、コンパクトシティ・プラス・ネットワークの
本格的推進が挙げられ、立地適正化計画等に取り組む地方公共
団体に対して、関係省庁が連携したコンサルティングや支援施
策の充実を行うとあります。
コンパクト・プラス・ネットワークのための計画制度では、都
市全体の構造を見渡しながら、居住機能や医療・福祉・商業等
の都市機能の誘導と、それに連携した持続可能な地域公共交通
ネットワークの形成を推進。
必要な機能の誘導・集約に向けた市町村の取組を推進するため、
計画の作成・実施を予算措置で支援とあります。
現在、鴨島駅前周辺地区都市再生整備計画で、アリーナ・交流
センターの整備が行われております。
また、都市再生整備事業として鴨島駅東線拡幅と駐車場整備を
計画し国から事業承認されている四国銀行鴨島支店跡地を事業
用地として市が購入し、令和2年度に駅前広場とその周辺を再
開発する予定とのことですが、鴨島駅前周辺の住民の方々の生
活道路の部分もありますし、JR鴨島駅も1日に約1800人
の乗降客が利用していますので、工事を行う際には、住民の方
々への事前の十分な周知と、工事期間中の安全対策に気を付けて
頂きたいと思います。
ちなみに、2018年度の徳島県内のJR駅1日あたりの乗降客数は
、徳島駅が16224人でトップ、2位が阿南駅で3134人、3位が勝瑞
駅で2410人、以下、石井駅、南小松島駅と続き、鴨島駅は6位で
1850人となっています。
また、銀座・文楽地区の道路・排水路整備についても、住民の
皆さんへの周知や安全対策をお願いいたします。
また、当初の予定では、関連事業として銀座通りのアーケード
撤去、駅前通りのアーケード改修とありましたが、これらの事
業を、立地適正化計画に反映させることはできないでしょうか。
今後の都市計画にどのように取り組んで行く予定なのかを再問
いたします。
また、都市計画道路のうち未整備である3路線は廃止する考え
とのことですが、今後のスケジュールについてもお伺いいたします。
〇答弁 小澤建設部長
今後の取り組みとしましては、当初計画に基づき、令和2年
3月末の吉野川市民プラザの完成後、令和2年度において鴨島
駅前広場周辺整備、令和3年度に鴨島駅東部主に銀座・文楽地
区の道路・排水施設の整備を行います。
銀座通り・駅前通りのアーケード改修につきましては、地元
商店街の皆様と協議し、今後の商店街活性化の取り組みや展望
などを踏まえた中で検討して参りたいと考えています。
先ほどご説明しました、立地適正化計画においては、現在進め
ている事業を反映できるよう、進めて参りたいと考えています。
次に、都市計画道路の廃止に向けて、今後のスケジュールに
つきましては、既に廃止に向けた協議を県と行いましたが、事
業廃止の環境が整っていないとの理由で現在も協議継続中です。
昨今、国土交通省及び県からは、コンパクトシティ・プラス・
ネットワークといった集約型都市の整備が呼びかけられ、市街
地の縮小が求められていることから、本市でも立地適正化計画
の策定が急がれる状況にあります。このことも踏まえ、事業廃
止の環境を整えるために計画を策定し、その際に未整備である
3路線の廃止の協議を進めて参りたいと考えています。
その後、マスタープラン等、上位計画の変更に向けて、都市
計画道路の廃止を記載した上で、県との協議とともに、住民説明
会等の手続きを進めて参りたいと考えています。
〇要望
ありがとうございました。
昭和の経済成長期の遺産が、今もなお、残っていて、旧の鴨島
地区では市街化区域や調整区域や道路等の線引きによって不自由
な思いをしている市民の方も大勢いらっしゃると聞いております。
時代に即した都市計画を立てて、迅速に実施することが大切な
事だと思いますので、国や県との交渉や協議もしっかりと早め
に実行して頂きたいと思います。
来春には、吉野川市のランドマークとなるアリーナが完成し、
鴨島駅前広場周辺整備も始まります。
1日約1800人が利用する、吉野川市の玄関口となる鴨島
駅を下りた時に、駅前には時計台と五九郎さんの石碑しか目に
入りません、駅前広場の整備を行うのなら、アリーナへ通じる
場所に何かシンボル的なインパクトのあるモニュメントなどを
設置出来ないものでしょうか。
市外からJRを利用して来る人々に、魅力ある街を印象づけ
るのに駅前広場からアリーナにかけてのアクセス空間を工夫
して、吉野川市の魅力を発信できる場所となることを要望して、
私の質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
令和元年9月定例会 薫風会代表質問
岸田益雄
1.合併15年目を迎えて
(1)これまでの取り組みの成果は
(2)今後の課題は
2.消費税の引き上げについて
(1)幼児教育・保育の無償化の詳細は
(2)プレミアム付商品券の詳細は
3.英語教育の充実について
(1)英語教育の現状と今後の対応は
(2)英語検定受検への取り組みは
(3)JETプログラムの積極的な取組は
薫風会代表質問
おはようございます
議長の許可をいただきましたので、通告書に従い
薫風会の代表質問を行いたいと思います。
まず、最初に
1 合併15年目を迎えて
(1)これまでの取り組みの成果は
(2)今後の課題は でございます
吉野川市が誕生してはや15年目を迎えようとしております。
平成16年10月に麻植郡の4町村が合併して誕生した吉野川市
ですが、川真田市長は市が誕生してから、4回の市長選挙を経て
15年間、市の舵取りを行っておられます。
最初の所信では「吉野川市地域創造プラン」を示し、「人輝き
地域輝く 夢紡ぐ 吉野川市」の実現のために、「合併の効果
を活かす行財政改革の断行」で「行財政改革本部」を設置、「吉
野川パートナーシッププラン」の実行で「吉野川市市制懇談会」
の実施、「よしのがわ子育て支援プラン」の実施、健康な暮らし
と安全の確保をめざす「よしのがわ安らぎ創造プラン」の実施を
目標に掲げていました。
2期目では、「安心安全な生活環境づくり」「子育て支援と教
育環境の整備」「個性豊かな地域の活性化」を柱として
3期目では「誰もがもっと住みやすいまちに」を目指して「より
万全の防災対策」「教育の振興」「子育て支援の充実」「地場産
業の振興」「笑顔のある暮らし」「インフラの整備」「みんなで
キレイに」「行財政改革の推進」を公約の柱とし
4期目では、「子育てに優しいまちづくり」「教育に強いまち
づくり」「若い世代に魅力のあるまちづくり」「地域の個性を生
かしたまちづくり」「安全・安心なまちづくり」「効率的に行政
運営をするまちづくり」を公約の柱とし、一貫して「誰もが安心
して暮らしていただけるまちづくり」を目指して、「子育て支援」
「教育環境の整備」「防災対策」「産業振興」などの政策を掲げて
市政の舵取りをされてきました。
その時代・その時代に適応した施策を取り入れながらも、合併
特例債を十分に活用しながら、15年間を歩み続けてきたと思い
ますが、これまでの取組を振り返ってどのような成果を成し遂げ
られたのかをお伺いします。
今年度から、露口政策監が徳島県から出向されていますので、
吉野川市が合併してからの施策や事業の成果についての、ご意見
をお伺いしたいと思います。
また、15年間を振り返り、今後の吉野川市の長期的な発展の
ための課題を川真田市長にお伺いしたいと思います。
答弁【露口政策監】
「合併15年目を迎えて、これまでの取り組みの成果について」の
ご質問に、ご答弁申し上げます。
政策監として着任以来、早5ケ月が過ぎましたが、吉野川市が発
足以来、合併による優遇措置を最大限に活用し、計画的に施策を
進めてきた結果、合併したからこそ出来得た成果を、市内の各地
域において、見て取ることが出来ます。
まず、平成16年10月1日の吉野川市発足以来、行財政改革による
職員の大幅な削減(153名)や、保育所及び温泉施設の民間移管、
公民館・児童館・公園などへの指定管理者制度の導入などにより、
経費削減に努めて来たところでございます。
一方で、合併による優遇措置である普通交付税の算定替えや、合
併特例債を有効に活用し、将来への基盤とするため、各種施設の
整備を積極的に進めてまいりました。
この15年間の成果として、主なものを具体的にもうしあげますと、
1.まず、美郷地区における情報通信格差を是正するための地域
イントラネット基盤整備事業
2.庁舎統合のための「市役所東館」整備事業や、山川庁舎を利
活用した「山川地域総合センター」整備事業
3.小・中学校における学習環境の整備としては、
・「川島中学校校舎」及び「屋内運動場」改築事業、
・「山川中学校校舎」改築事業
・「高越小学校」整備事業
・「学校給食センター」整備事業
・全小中学校における普通科全教室へのエアコンの設置
4.働きながら子どもを産み育てやすい環境づくりとして
本市における幼保再編構想により、
・旧川島庁舎を利活用した「川島こども園」整備事業
・「高越こども園」及び「鴨島東こども園」整備事業
また、民間が主体となった
・「山瀬かもめこども園」及び「鴨島中央部こども園」
整備事業
5.安全・安心で暮らしやすいまちづくりとして
・「消防団詰所・格納庫」整備事業
・徳島中央広域連合「消防本部」・「東署」・「西署」
改築事業
・「水道施設・管路」耐震化事業
6.市民の皆さんへ安心で安全な医療サービスを提供
するための、旧麻植協同病院の移転改築に伴う周
辺整備事業及び、吉野川医療センターでの産婦人
科における分娩の再開
7.ごみの減量化や資源化を促進するための
運転管理センターやリサイクルセンター整備事業
8.地域における生涯学習の拠点整備として
上浦公民館・山瀬公民館整備事業
9.県央部におけるスポーツ施設として、現在大変好評を
得ております、上桜スポーツグラウンド整備事業
10.最後に、現在進行中ですが、中心市街地である鴨島
駅周辺地区の活性化を図り、活力と賑わいのある「街
なか」としての再生を目指す、市民プラザ建設を中心
とした都市再生事業等があげられます。
今後は、これらの施設を有効に活用し、吉野川市の活性化
に繋げて参りたいと考えております。
以上でございます。
答弁【川真田市長】
「市政施行15年目を迎えて 今後の課題は」の
ご質問にご答弁申し上げます。
先ほど、政策監の方から答弁申し上げましたとおり、
吉野川市発足以来15年の間、行財政改革による経費
削減に努める一方で、合併の優遇措置を最大限活用し、
各種施設の整備を進めてまいりました。
とりわけ、平成29年度からの3年間を、合併によるまち
づくりの総仕上げの期間として集中的に事業を実施して
きたところであります。
これまでの15年間で、施設整備につきましては、一定の
成果は挙げられたと考えておりますが、市内にはまだま
だ老朽化した施設がたくさんございますので、これらの
維持に係る経費も増大することが見込まれます。今後は、
そのあり方につきまして、慎重に検討する必要があると
考えております。
また、今後は、扶助費など削ることなどが出来ない経費
の増加も見込まれることや、次年度以降につきましては、
合併特例債などの合併による優遇措置は無くなるなど、
いっそう厳しい状況になることが見込まれます。本市が
将来にわたって、健全財政が持続できるよう、これまで
に引き続き、職員一丸となって、行財政改革の推進に取
り組むとともに、一部事務組合による共同処理の見直し
などにより、出来る限り歳出の抑制と財源の確保に努め、
市民サービスの向上に努めて参りたいと考えております。
以上でございます。
ありがとうございました。
市が誕生して15年、来年度以降には、合併特例債などの
合併による優遇措置は無くなり、厳しい財政状況になるこ
とが予想されます。
市長の答弁にもございましたが、年度別の吉野川市の決算
シートをみても、年々増加する扶助費などの民生費が他の
予算を圧迫しております。
今後も厳しい市政運営となる事が予想されますが、知恵を
絞り、今後もより良い街づくりのために、より良い施策を
行ってくださるように要望いたしまして、次の質問に移り
たいと思います。
続きまして、2つめの質問として
2.消費税の引上げについて 質問いたします。
(1)幼児教育・保育の無償化の詳細は
(2)プレミアム付商品券の詳細は であります。
来月10月から消費税が8%から10%に引上げられます。
少子高齢者や人口減少が進む日本で、社会保障をすべての
世代のものに転換し、これらを次世代に引き継ぐため、
また高齢者の安心や若者の希望を確かにし、社会保障を
充実させるための消費税の引上げとうたわれています。
引上げ分は、子ども、子育て、医療や介護、年金、高等
教育など、子育て世代や現役世代を含む全世代を対象とす
る社会保障の充実と安定のために使われ、待機児童の解消
や幼児教育・保育の無償化、高等教育の無償化、介護職員
の処置改善などに使われることになっています。
また景気対策として、プレミアム付商品券やキャッシュ
レス決済に対するポイント還元などの対策も行われます。
そこで、今回の消費税引上げが、子育て世代にどのよう
な影響を与えるのかを質問いたします。
まず、1点目として、幼児教育・保育の無償化について、
3歳から5歳までの幼稚園・保育所・認定こども園の費用を
無償化、また就学前の障害児の発達支援についても無償化
と言われているが、どのような内容なのかをお伺いします。
2点目として、所得の低い方や0?2歳の子育て世帯向け
にプレミアム付商品券を配布するとのことですが、その内
容についてお伺いいたします。ご答弁よろしくお願いいた
します。
答弁【宮本健康福祉部長】
「消費税率の引き上げについて」のご質問にご答弁申し
あげます。
まずはじめに、「幼児教育・保育の無償化について」で
ございますが、
本年10月の消費税増税に合わせ、幼稚園・保育所・
認定こども園を利用する3歳?5歳児の子ども、また、
保育所・認定こども園・小規模保育事業等の地域型保育
を利用する0歳?2歳児の住民税非課税世帯の子どもの
保育料につきましては、実費徴収分を除き無償とするこ
ととなっております。
また、私立幼稚園に通う子どもにつきましても、実費
徴収分を除き月額2万5千700円を上限に保育料が無
償化されることになります。その他、保育の必要性が認
められる場合には、幼稚園・認定こども園の1号認定子
どもの預かり保育料も無償化されるほか、幼稚園・認可
保育施設等を利用していない子どもにつきましては、
認可外保育施設・病児病後児保育・一時保育・ファミリ
ーサポートセンターの利用料について、3歳?5歳児で
は月額3万7千円を上限に、住民税非課税世帯の0歳?
2歳児では月額4万2千円を上限に無償化されることに
なります。
また、就学前の障害児の発達支援につきましては、
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与
などの支援を行う「児童発達支援事業」保育所などを訪
問し、障害児に対して障害児以外との集団生活への適応
のための専門的支援「保育所等訪問支援事業」など様々
なサービスの利用者負担も無償となります。
こうした就学前障害児の発達支援事業利用者について
は、保育所・こども園等と併用する場合についても無償
となります。
つづきまして、「プレミアム付商品券について」でござ
いますが、
プレミアム付商品券事業につきましては、本年10月か
らの消費税、地方消費税率の引き上げが低所得者、子育
て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域に
おける消費を喚起、下支えすることを目的として実施さ
れるものでございます。
この趣旨に沿って事業を実施する市町村等の実施主体
に、対象となる経費の全額に対して国から財政支援がな
されるというものであり、本市におきましても、国の実
施要領に基づき、定められた手続きにのっとって吉野川
商工会議所や吉野川市商工会等と連携・協力して実施し
ております。
内容については商品券をご購入いただけるのは、住民
税が非課税の方及び3歳未満のお子様のある世帯主、合
わせて1万2,000人の方々に額面2万5,000円
分の商品券を2万円で販売し、ご購入いただけるもので
ございます。
商品券をご利用いただける店舗については、広く市内
から公募し、商品券の使い道は、換金性の高いものは除
外するなど、一定の制限を設けております。
今回の事業は、平成27年度に実施をしたプレミアム
商品券とは異なり、ご購入いただける方を住民税が非課
税の方及び3歳未満のお子様のある世帯主に限っている
ことから、5,000円(販売額4,000円)から購
入できることとしております。
以上でございます。
ありがとうございました。
「幼児教育・保育の無償化」と「プレミアム付商品券」
についての概要を説明していただきました。
この保育料の無償化の質問は、以前から同僚議員も行
っておりますが、保護者の皆さんにとって保育料の無償
化はありがたいことだと思います。
現在、吉野川市内には、吉野川市立認定こども園、私立
認定こども園、乳児保育園、呉郷保育所と様々な施設が
ありますが、今回の保育料無償化による、それぞれの施
設での違いはあるのでしょうか、あるとするならどのよ
うな違いがあるのかお伺いいたします。
また、幼児教育・保育の無償化やプレミアム付商品券に
ついては、どのような手続きや申請が必要なのでしょう
かお伺いします。
また、プレミアム付商品券の取扱店は、8月20日現在で
吉野川商工会議所登録98件、吉野川市商工会登録66件の
合計164件であります。
前回のプレミアム商品券の時は、商工会議所176件、
商工会52件の合計228件と聞いています。
商品券の対象者は前回より少ないと思いますが、取扱店
が少なければ、使い勝手も悪いのではないでしょうか?
商品券の使用期限は令和元年10月1日から令和2年3月31日
までとなっていますが、今後の取扱店の募集についてお
伺いします。
答弁【宮本健康福祉部長】
再問にご答弁申しあげます。
今回の国の制度改正では、全ての3歳?5歳児・住民
税非課税世帯の0歳?2歳児の保育料が無償となります。
と同時に、これまで保育料に含まれていた2号認定児の
副食費につきましては1号認定児と同様に実費徴収する
ことになりました。
本市ではこれまで、国の保育料無償化に先駆けて、
3?5歳児における保育料は、本市独自のカウント方法
により、18歳以下からカウントし第2子以降無償とし
てきたところで、国の制度に合わせ、一律に副食費を負
担していただくことになると、実質的な値上がりとなる
児童がいるため、子育て支援の充実という観点から、月
額4,500円ほどの副食費を助成し、保護者の負担軽
減を図るよう、今議会に予算計上していることころで
あります。
そうした点を踏まえまして、ご質問の「今回の保育料
無償化による、それぞれの施設で違いはあるのか」につ
いてでございますが、
国から示されている副食費の基準額につきましては、
月額4,500円が目安とされており、公立園について
は、国に準じた金額設定としております。
しかしながら、保護者の同意が得られれば4,500
円を超えてもかまわないとも示されており、一部私立
園では身体作りのため、保育所給食の手引きにうたわ
れていない朝の牛乳を提供することとしていることか
ら、若干の増額になるとも聞いております。
また、主食費については、公立園では、これまでど
おり500円を負担していただきますが、一部私立園
では、ごはんを持参するため主食費代を徴収していな
い園もございます。
次に、「幼児教育・保育の無償化にはどのような手
続きや申請が必要なのか」についてでございますが、
現在、保育所・こども園・幼稚園を利用されている
1号認定・2号認定そして非課税世帯の3号認定につ
きましては、特に手続きの必要はありません。
しかしながら、新制度未移行幼稚園につきましては
新1号、鴨島幼稚園で預かり保育を利用されている児
童については、新2号の認定が必要なため申請をして
いただく必要があります。該当児は把握しており、す
でに勧奨通知を発送しております。
また、該当は少ないと考えられますが、幼稚園・認
可保育施設を利用しておらず保育が必要と認められる
方につきましては、新2号・新3号の認定が必要なた
め、認可外保育施設・病児病後児保育など該当施設を
利用する前に、就労証明等添付した認定申請が必要と
なりますので、広報よしのがわやホームページなどで
周知を徹底していきたいと考えております。
次に、プレミアム付商品券については、どのような
手続きや申請が必要なのかについてでございますが、
吉野川市プレミアム付商品券を購入するには、吉野
川市プレミアム付商品券購入引換券が必要となります
ので、事前申請をしていただくことになります。
プレミアム付商品券の購入対象と思われる平成31
年度の住民税が課税されておらず、課税者の扶養親族
でない低所得者の方については、令和元年8月7日に
引換券交付申請書を発送しております。
商品券の購入を希望される場合は、郵送された申請
書の内容等をご確認のうえ、必要事項に記入し、11
月30日(当日消印有効)までに提出していただくこ
ととなります。 提出していただいた後、審査を行い
、該当者には9月より順次、商品券の購入引換券を送
付させていただきます。
平成28年4月2日から令和元年9月30日までに
生まれたお子様がいる世帯主の方は、引換券交付申請
は、必要ありません。 対象となる人には、9月より
お子様の誕生日に応じ、順次購入引換券を送付させて
いただきます。 購入引換券が届きましたら、「購入
引換券」を持参し、社会福祉課及び各支所において、
令和元年10月1日から令和2年2月29日までに商
品券を購入していただくこととなります。
なお、プレミアム付商品券の使用期間は、商品券取
扱登録店舗にて令和元年10月1日から令和2年3月
31日となっております。
次に、今後の取扱店の募集についてでございますが、
広報よしのがわ及びホームページ、吉野川商工会議
所や吉野川市商工会が開催する会議等、いろんな場面
で周知をさせていただき、今後においても、取扱店の
募集を行ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
ありがとうございました。
詳細な説明を頂き、よく理解できました。
8%から10%に引き上げられた消費税分は、子ども
、子育て、医療や介護、年金、高等教育など子育て世
代や現役世代を含む全世代を対象とする社会保障の充
実と安定や、待機児童の解消、幼児教育・保育の無償
化、高等教育の無償化、介護職員の処置改善などに使
われることになっています。
景気対策として実施されるプレミアム付商品券を有
効に利用して、地域消費の喚起と景気の下支えとなる
事を期待して、この質問を終わりたいと思います。
それでは、最後の質問に移りたいと思います。
3. 英語教育の充実について
(1) 英語教育の現状と今後の対応は
(2) 英語検定受検への取り組みは
(3) JETプログラムの積極的な取り組みは
であります
本市の英語教育の充実について質問いたします。
グローバル化の進展の中、英語教育についての新学習
指導要綱が示され、小学校での外国語教育が重視され
ています。
令和2年度からは、小学校5年6年生に導入されていた
外国語活動が小学校3年4年生に、そして小学校5年6年
生には、英語が教科として導入されます。これまでも小
学校では、外国語活動として、「聞く」・「話す」を中
心とした外国語教育に取り組んで、コミュニケーション
力の向上に力を入れてきましたが、今回の改定で、中学
校で実施している英語教育と同様に、「聞く」・「話す」
に加えて、「読む」・「書く」の活動も加わります。
これまでは指定されていなかった単語数も、小学校3年
から6年で600?700語、中学校では現行の1200語程度か
ら、今後は1600?1800語程度へと増加しています。
このような時代の動きに対して、小学校や中学校での授
業の形態が大きく変わろうとしています。
そこで、1点目として大きく変わろうとしている外国語
教育に対して、本市の英語教育の現状と今後の対応をお
伺いいたします。
2点目として、英語教育の充実を目指し、生徒達の学習
意欲向上にもつながる英語検定等の受検への市の取り組
みはどうなのかをお伺いいたします。
3点目として、JETプログラム、これは「語学指導等
を行う外国青年招致事業」The Japan Exchange and
Teaching Programme(ザ・ジャパン・エックスチェン
ジ・アンド・ティーチング・プログラム)の略称で、
地方自治体が総務省、外務省、文部科学省及び一般財団
法人自治体国際化協会の協力の下に実施しているもので
、主に海外の青年を招致し、地方自治体、教育委員会及
び全国の小・中学校や高等学校で、国際交流の業務と外
国語教育に携わることにより、地域レベルでの草の根の
国際化を推進することを目的としています。
本市において、このJETプログラムへの取り組みは
どうなのか、以上3点を質問いたします。
答弁【住友副教育長】
「英語教育について」のご質問に、ご答弁申し上げます。
1点目の「現在の英語教育の現状と今後の対応は」とのご
質問について申し上げます。
小学校においては、2年間の移行期間を経て、来年度より
新学習指導要領が本格実施となり、3・4年生は、週1時
間・年間35時間の「外国語活動」を、5・6年生は、週
2時間・年間70時間の教科である「外国語科」の学習を
実施します。
本市の小学校では、授業時数確保のため、週授業時数を
1時間増やすなどの対応をし、今年度よりすでに、本格実
施時と同様の授業時数にて外国語学習を行っております。
デジタル教科書やALT及び英語専科教員等を有効活用し
、外国語による聞くこと、読むことならびに話すこと、
書くことの言語活動を通して、コミュニケーションの素地
と基礎となる資質・能力を育成することを目指しております。
令和3年度から本格実施の中学校については、小学校の学び
を踏まえ、コミュニケーションを図る資質・能力を育成する
ことを目指すべく、現在移行期間中であります。
本市では、グローバル社会を生きる子供たちに求められる
力を育成するため、小中学校における外国語活動・英語教
育の充実をめざした取組をこれまでも推進してまいりました。
本市小中学校生を対象とした子ども英語教室やイングリッ
シュキャンプの開催、ALTの増員、小学校教員を対象と
しました英語ミニ研修会の取組でございます。
これら本市児童生徒の英語力の向上に貢献しております取組
のさらなる充実を図るとともに、新学習指導要領の本格実施
にともなう、ハード・ソフト両面のさらなる充実を図るべく、
教育委員会といたしまして、しっかりと学校現場と連携して
まいります。
2点目の「英語検定受検への取組は」とのご質問について申
し上げます。
本市の外国語教育・英語教育の充実をめざした取り組みの
ひとつに「英語検定検定料補助制度」があり、これは本市
の「まち・ひと・しごと創生」総合戦略の基本目標であり
ます「特色ある学校教育の推進」をめざした事業であります。
平成28年度より、実用英語技能検定を効果的に活用し「聞く」
「話す」「読む」「書く」の英語4技能をバランスよく身に
つけることができるよう、また受検をとおして生徒の英語
学習への関心、意欲を高めることができるよう、検定料の
一部を補助しております。
補助対象級は1級から5級のうち、準2級から4級となっており
、準2級検定料4900円のうち3600円を、3級検定料3900円の
うち2900円を、4級検定料の2600円のうち1900円をそれぞれ
補助しております。補助は、1年度につき1回限りとなって
おります。
英検3級程度以上を達成した中学校3年生の割合を50%以上
にすることを具体的な目標とし、本事業がスタートいたしま
した平成28年度当初は、44.4%であった割合が、平成
29年度は57.7%、平成30年度は64.2%と、目標数値
を上回る結果を残しており、本市の英語力の向上を示す具体
例のひとつであると考えます。
3点目の「JETプログラムの積極的な取組は」とのご質問に
ついて申し上げます。
本市では、現在6名の外国語指導助手ALTを採用しており、
うち5名がJETプログラムによるALTであり、平成28年
7月現在には3名であったJETプログラムによるALTで
ありますが、同年8月には4名、平成30年8月には5名へ増員と
なり、現在にいたっております。
ALTを増員し適切に各校に配置することで、児童生徒は、
英語をより身近に感じ、英語に対する興味関心を増すことに
つながっており、授業において「聞く・話す」機会をさらに
充実することができております。
また、本市の英語教育推進の取組であります、小中イングリ
ッシュキャンプにもスタッフとして参加し、児童生徒および
教員と積極的にコミュニケーションをとり、運営に大きく寄
与ができておりました。
ALTがよりスムーズに学校現場とコミュニケーションをと
り、児童生徒の外国語教育、英語教育に資することができる
よう、配置数・配置方法等を含めた、制度の充実・改善に向
けて、教育委員会として適切に対応してまいります。
以上でございます。
ありがとうございました。
現在の英語教育の現状と今後の対応について、英語検定受検
への取り組みについて、JETプログラムの積極的な取り組
みについてのご答弁を頂きました。それでは再問をさせてい
ただきます。
薫風会の研修として、平成30年1月23日に国会の衆議院
会館において、次年度から始まる小学校の外国語教育につい
て、文部科学省初等中等教育局幼児教育課振興係長よりレク
チャーを受けました。
内容としては、ご答弁にもあった部分もございますが
2020年から小学校3、4年生から「外国語活動」が新
たに始まる。5、6年生では外国語が「教科」になる。
2018年、2019年度は、移行措置期間である。
中学校では、2021年度から、授業は外国語で行うことが
基本となり、対話的な活動や、実際に活用する言語活動を重
視する。
高校では、2022年度から、「聞く」「読む」「話す」
「書く」を総合的に学び発信力を高める。
「大学入試」では2020年度から、外部検定試験を活用し
「読む」「聞く」「話す」「書く」の4技能が評価される。
英語教員などの体制整備の面では平成30年度1000人、
平成31年度1000人、平成32年度には2000人を専
門指導のための加配措置を行う。
小学校における外国語教育の指導体制は、専科教員が学級担
任の負担を軽減する。ALTも学級担任を英語面でサポート
して、生きた英語の提供を行う。
英語教育推進リーダーが各地域の小学校中核教員の指導力研
修を行う。
研修を受けた中核教員が、ALTプラス外部人材など校内研
修などを行い英語指導力に優れた小学校教員を育成・輩出する。
JETプログラムに係る地方財政措置については、現行措
置に加え、市町村におけるJETプログラムコーディネーター
の活用に要する経費について、特別交付税措置がある。
小学校移行期間中(平成30・31年度)の5・6年生は新
たに年間15単位時間を加え、50単位時間を確保し、外国
語活動の内容に加えて外国語科の内容を扱う。外国語科の内
容については、中学校との接続の観点から、最低限必要な内
容と、それを活用して行う言語活動を中心に取り扱う。
平成31年から、教員養成大学で、小学校の先生を選べば英
語の指導方法を学ぶようになるなどの説明を受けました。
ただし毎年、財務省と折衝して予算が通ればとのことでした。
また、担当者に現在、小学校では、月・火・水・金が6コマ
で木曜が5コマの授業であるが、この上に1コマ増えれば、
現場での仕事量が増えるばかりであるが文部科学省はどう思
っているのかと問うと、働き方改革で教員の定数を増やすよ
うに財務省に交渉した、専門の英語教員を増やす方向で進め
ていく。との答弁でしたが現状はどうなのでしょうか、
お伺いします。
JETプログラムにつきましては、現在の人員では不足が
ちだと思われますので、より良い人材をより多く確保出来る
ように県へ粘り強く要望して下さい。
英語検定につきましては、中学校1年生レベルで5級、2
年生レベルで4級、3年生レベルで3級、その上が準2級、
2級となっているそうですが、現在英語検定補助事業は、4
級の検定料2600円に対し1900円を補助し自己負担額
が700円、3級の検定料3900円に対し補助が2900
円で自己負担が1000円、準2級の検定料4900円に対
し補助額が3600円で自己負担額1300円となっています。
検定料の補助は1年度につき一度限りで、1年に2回受験する
場合は自己負担となるとのことです。
また、この補助制度で中学校卒業時には50%の生徒が「英
検3級以上」の資格取得を目指すとのことです。
各級の受検志願者と合格者は年々増加傾向にあるというこ
とで、生徒達の頑張りを補助金等で応援出来ていると思いま
すが今後小学校での英語の授業が始まれば、児童・生徒達の
英語に対しての学習意欲が高まり、自分の実力を計るために
英語検定の受検者は増加すると思います。
また、中学生でも準2級のレベルではものたらずに,2級
や準1級へのチャレンジをしたい生徒もいると聞いておりま
すが2級の検定料5500円には現在市の補助はありません。
また、英語検定の入口の5級の受検料2000円にも補助
がありません。子どもたちの未来のために、学習意欲を高め、
英語力を育成するために、この英語検定料補助事業はあると
思いますので、5級から2級までの英語検定受検者にも補助
制度を拡大出来ないかをお伺いいたします。
さらに、現在の検定料の補助は、1年度につき1回限りと
なっており、1年度に4級、3級と級を変えて2回受験して
も補助は1回となっていますが、チャレンジ精神を養うため
にも1年間で3回ある英語検定試験で、上級の検定を受検す
る者に対しての補助は出来ないかお伺いします。
鉄は熱いうちに打てとのことわざもあり、英語の学習意欲に
燃えている時ほど、大人が後押しするのが良いのではないで
しょうか。
本市の生徒達の、英語学習の意欲をより高めるためにも、よ
り良い制度となるよう補助事業を拡大できないかをお伺いし
ます。
答弁【住友副教育長】
岸田議員の再問について、ご答弁いたします。
1点目の「小学校外国語教育指導体制の充実にむけた、英語
専科教員の配置状況は」とのご質問について申しあげます。
ご質問の中で説明いただいたように、文部科学省におきまし
ては、新学習指導要領全面実施にむけた指導体制の強化・充
実を図るべく、様々な取り組みを打ち出しております。
なかでも、新学習指導要領の円滑な実施と学校における働
き方改革といたしまして、「小学校英語教育の早期化・教科
化に伴う、一定の英語力を有し、質の高い英語教育を行う専
科指導教員の充実」を薦めております。
本市では、現在1名の英語専科教員が配置されております。
2校を兼務している状況ではありますが、指導体制の充実・
強化に向け、さらなる増員が望まれるところであります。
2点目の「英語検定料補助事業の補助対象級ならびに補助回
数の拡大にむけての対応は」とのご質問につきまして、お答
えいたします。
来年度の小学校学習指導要領全面実施に向けた、本市なら
びに市内各小学校のこれまでの取り組みにより、児童の英語
に対する興味関心・学習意欲は高まってきております。
教育委員会におきましては、本事業の具体的な目標であり
ます「英語検定3級以上を達成した中学3年生の割合を50%
以上にすること」を基本としながらも、小学校ならびに中学
校新学習指導要領全面実施による外国語教育・英語教育のさ
らなる充実を考慮した英語検定料補助対象級の拡大を前向き
に検討してまいります。
なお、検定料補助の回数拡大につきましては、小学校での
英語教育推進にともなう英語力向上を考慮しますと、今後の
受検者数の動向が不透明であるため現在は考えておりません。
以上でございます。
ありがとうございました、
前向きに検討して頂くということで、来年度からは英語検
定を受検する生徒達の励みになると思います。
検定料補助の回数につきましては、受検者数の動向がはっ
きりと分かる段階で、再考して頂ければと思います。
義務教育の場では、学校での学習に取り組むことが大切で
あると考えますが、年齢が進むにつれ、また社会人となっ
たら、みずから資格試験を受検し、キャリアアップするこ
とも大切で、早い段階からそのような習慣を身に着けるこ
とも大切な事だと思います。
2020年度から大学入試改革で、現センター試験は廃止され
、新たに共通テストが先行実施されます。小学校では次期
学習指導要領が全面実施され、2021年度からは中学校でも
次期学習指導要領が全面実施されます。
学習指導要領の改訂の考え方では、これからの教育課程
の理念として、「よりよい学校教育を通じて、よりよい社
会を創るという目標を学校と社会が共有し、それぞれの学
校において、必要な教育内容をどのように学び、どのよう
な資質・能力を身に付けられるようにするかを明確にしな
がら、社会との連携・協働によりその実現を図っていく。
」とありますが、本市において、どのような姿勢で取り組
んで行くかを教育長にお伺いします。
答弁【石川教育長】
「これからの教育課程の理念に対する本市の取組姿勢は」
とのご質問について申しあげます。
新学習指導要領における改善点の基盤となる考え方が「社
会に開かれた教育課程」であります。
今後は,「社会や世界の状況を幅広く視野に入れ,よりよ
い学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標をもち,
教育課程を介してその目標を社会と共有していくこと」なら
びに「グローバル化がますます進むであろう,これからの社
会を創りだしていく子ども達が,社会や世界に向き合い関わ
り,自らの人生を切り開いていくために求められる資質・能
力とは何かを,教育課程において明確化し、育んでいくこと
」等が求められます。
教育委員会といたしましては,家庭・地域と連携し,学校
の特色を生かした教育過程をより具現化できるよう人的・物
的資源の活用を積極的に支援してまいります。
また,グローバル社会を生き抜く力を育むべく,これまで
の英語教育に対する取組をさらに進めてまいります。
ありがとうございました。
時代の変化と共に、学習要領の内容も変化してきます。
グローバル化の中、英語教育の比重は高まるばかりです。
今後も、さまざまな取り組みを通じて子供たちの力を伸ばして
頂く事を要望して、薫風会の代表質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
岸田益雄
1.合併15年目を迎えて
(1)これまでの取り組みの成果は
(2)今後の課題は
2.消費税の引き上げについて
(1)幼児教育・保育の無償化の詳細は
(2)プレミアム付商品券の詳細は
3.英語教育の充実について
(1)英語教育の現状と今後の対応は
(2)英語検定受検への取り組みは
(3)JETプログラムの積極的な取組は
薫風会代表質問
おはようございます
議長の許可をいただきましたので、通告書に従い
薫風会の代表質問を行いたいと思います。
まず、最初に
1 合併15年目を迎えて
(1)これまでの取り組みの成果は
(2)今後の課題は でございます
吉野川市が誕生してはや15年目を迎えようとしております。
平成16年10月に麻植郡の4町村が合併して誕生した吉野川市
ですが、川真田市長は市が誕生してから、4回の市長選挙を経て
15年間、市の舵取りを行っておられます。
最初の所信では「吉野川市地域創造プラン」を示し、「人輝き
地域輝く 夢紡ぐ 吉野川市」の実現のために、「合併の効果
を活かす行財政改革の断行」で「行財政改革本部」を設置、「吉
野川パートナーシッププラン」の実行で「吉野川市市制懇談会」
の実施、「よしのがわ子育て支援プラン」の実施、健康な暮らし
と安全の確保をめざす「よしのがわ安らぎ創造プラン」の実施を
目標に掲げていました。
2期目では、「安心安全な生活環境づくり」「子育て支援と教
育環境の整備」「個性豊かな地域の活性化」を柱として
3期目では「誰もがもっと住みやすいまちに」を目指して「より
万全の防災対策」「教育の振興」「子育て支援の充実」「地場産
業の振興」「笑顔のある暮らし」「インフラの整備」「みんなで
キレイに」「行財政改革の推進」を公約の柱とし
4期目では、「子育てに優しいまちづくり」「教育に強いまち
づくり」「若い世代に魅力のあるまちづくり」「地域の個性を生
かしたまちづくり」「安全・安心なまちづくり」「効率的に行政
運営をするまちづくり」を公約の柱とし、一貫して「誰もが安心
して暮らしていただけるまちづくり」を目指して、「子育て支援」
「教育環境の整備」「防災対策」「産業振興」などの政策を掲げて
市政の舵取りをされてきました。
その時代・その時代に適応した施策を取り入れながらも、合併
特例債を十分に活用しながら、15年間を歩み続けてきたと思い
ますが、これまでの取組を振り返ってどのような成果を成し遂げ
られたのかをお伺いします。
今年度から、露口政策監が徳島県から出向されていますので、
吉野川市が合併してからの施策や事業の成果についての、ご意見
をお伺いしたいと思います。
また、15年間を振り返り、今後の吉野川市の長期的な発展の
ための課題を川真田市長にお伺いしたいと思います。
答弁【露口政策監】
「合併15年目を迎えて、これまでの取り組みの成果について」の
ご質問に、ご答弁申し上げます。
政策監として着任以来、早5ケ月が過ぎましたが、吉野川市が発
足以来、合併による優遇措置を最大限に活用し、計画的に施策を
進めてきた結果、合併したからこそ出来得た成果を、市内の各地
域において、見て取ることが出来ます。
まず、平成16年10月1日の吉野川市発足以来、行財政改革による
職員の大幅な削減(153名)や、保育所及び温泉施設の民間移管、
公民館・児童館・公園などへの指定管理者制度の導入などにより、
経費削減に努めて来たところでございます。
一方で、合併による優遇措置である普通交付税の算定替えや、合
併特例債を有効に活用し、将来への基盤とするため、各種施設の
整備を積極的に進めてまいりました。
この15年間の成果として、主なものを具体的にもうしあげますと、
1.まず、美郷地区における情報通信格差を是正するための地域
イントラネット基盤整備事業
2.庁舎統合のための「市役所東館」整備事業や、山川庁舎を利
活用した「山川地域総合センター」整備事業
3.小・中学校における学習環境の整備としては、
・「川島中学校校舎」及び「屋内運動場」改築事業、
・「山川中学校校舎」改築事業
・「高越小学校」整備事業
・「学校給食センター」整備事業
・全小中学校における普通科全教室へのエアコンの設置
4.働きながら子どもを産み育てやすい環境づくりとして
本市における幼保再編構想により、
・旧川島庁舎を利活用した「川島こども園」整備事業
・「高越こども園」及び「鴨島東こども園」整備事業
また、民間が主体となった
・「山瀬かもめこども園」及び「鴨島中央部こども園」
整備事業
5.安全・安心で暮らしやすいまちづくりとして
・「消防団詰所・格納庫」整備事業
・徳島中央広域連合「消防本部」・「東署」・「西署」
改築事業
・「水道施設・管路」耐震化事業
6.市民の皆さんへ安心で安全な医療サービスを提供
するための、旧麻植協同病院の移転改築に伴う周
辺整備事業及び、吉野川医療センターでの産婦人
科における分娩の再開
7.ごみの減量化や資源化を促進するための
運転管理センターやリサイクルセンター整備事業
8.地域における生涯学習の拠点整備として
上浦公民館・山瀬公民館整備事業
9.県央部におけるスポーツ施設として、現在大変好評を
得ております、上桜スポーツグラウンド整備事業
10.最後に、現在進行中ですが、中心市街地である鴨島
駅周辺地区の活性化を図り、活力と賑わいのある「街
なか」としての再生を目指す、市民プラザ建設を中心
とした都市再生事業等があげられます。
今後は、これらの施設を有効に活用し、吉野川市の活性化
に繋げて参りたいと考えております。
以上でございます。
答弁【川真田市長】
「市政施行15年目を迎えて 今後の課題は」の
ご質問にご答弁申し上げます。
先ほど、政策監の方から答弁申し上げましたとおり、
吉野川市発足以来15年の間、行財政改革による経費
削減に努める一方で、合併の優遇措置を最大限活用し、
各種施設の整備を進めてまいりました。
とりわけ、平成29年度からの3年間を、合併によるまち
づくりの総仕上げの期間として集中的に事業を実施して
きたところであります。
これまでの15年間で、施設整備につきましては、一定の
成果は挙げられたと考えておりますが、市内にはまだま
だ老朽化した施設がたくさんございますので、これらの
維持に係る経費も増大することが見込まれます。今後は、
そのあり方につきまして、慎重に検討する必要があると
考えております。
また、今後は、扶助費など削ることなどが出来ない経費
の増加も見込まれることや、次年度以降につきましては、
合併特例債などの合併による優遇措置は無くなるなど、
いっそう厳しい状況になることが見込まれます。本市が
将来にわたって、健全財政が持続できるよう、これまで
に引き続き、職員一丸となって、行財政改革の推進に取
り組むとともに、一部事務組合による共同処理の見直し
などにより、出来る限り歳出の抑制と財源の確保に努め、
市民サービスの向上に努めて参りたいと考えております。
以上でございます。
ありがとうございました。
市が誕生して15年、来年度以降には、合併特例債などの
合併による優遇措置は無くなり、厳しい財政状況になるこ
とが予想されます。
市長の答弁にもございましたが、年度別の吉野川市の決算
シートをみても、年々増加する扶助費などの民生費が他の
予算を圧迫しております。
今後も厳しい市政運営となる事が予想されますが、知恵を
絞り、今後もより良い街づくりのために、より良い施策を
行ってくださるように要望いたしまして、次の質問に移り
たいと思います。
続きまして、2つめの質問として
2.消費税の引上げについて 質問いたします。
(1)幼児教育・保育の無償化の詳細は
(2)プレミアム付商品券の詳細は であります。
来月10月から消費税が8%から10%に引上げられます。
少子高齢者や人口減少が進む日本で、社会保障をすべての
世代のものに転換し、これらを次世代に引き継ぐため、
また高齢者の安心や若者の希望を確かにし、社会保障を
充実させるための消費税の引上げとうたわれています。
引上げ分は、子ども、子育て、医療や介護、年金、高等
教育など、子育て世代や現役世代を含む全世代を対象とす
る社会保障の充実と安定のために使われ、待機児童の解消
や幼児教育・保育の無償化、高等教育の無償化、介護職員
の処置改善などに使われることになっています。
また景気対策として、プレミアム付商品券やキャッシュ
レス決済に対するポイント還元などの対策も行われます。
そこで、今回の消費税引上げが、子育て世代にどのよう
な影響を与えるのかを質問いたします。
まず、1点目として、幼児教育・保育の無償化について、
3歳から5歳までの幼稚園・保育所・認定こども園の費用を
無償化、また就学前の障害児の発達支援についても無償化
と言われているが、どのような内容なのかをお伺いします。
2点目として、所得の低い方や0?2歳の子育て世帯向け
にプレミアム付商品券を配布するとのことですが、その内
容についてお伺いいたします。ご答弁よろしくお願いいた
します。
答弁【宮本健康福祉部長】
「消費税率の引き上げについて」のご質問にご答弁申し
あげます。
まずはじめに、「幼児教育・保育の無償化について」で
ございますが、
本年10月の消費税増税に合わせ、幼稚園・保育所・
認定こども園を利用する3歳?5歳児の子ども、また、
保育所・認定こども園・小規模保育事業等の地域型保育
を利用する0歳?2歳児の住民税非課税世帯の子どもの
保育料につきましては、実費徴収分を除き無償とするこ
ととなっております。
また、私立幼稚園に通う子どもにつきましても、実費
徴収分を除き月額2万5千700円を上限に保育料が無
償化されることになります。その他、保育の必要性が認
められる場合には、幼稚園・認定こども園の1号認定子
どもの預かり保育料も無償化されるほか、幼稚園・認可
保育施設等を利用していない子どもにつきましては、
認可外保育施設・病児病後児保育・一時保育・ファミリ
ーサポートセンターの利用料について、3歳?5歳児で
は月額3万7千円を上限に、住民税非課税世帯の0歳?
2歳児では月額4万2千円を上限に無償化されることに
なります。
また、就学前の障害児の発達支援につきましては、
日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与
などの支援を行う「児童発達支援事業」保育所などを訪
問し、障害児に対して障害児以外との集団生活への適応
のための専門的支援「保育所等訪問支援事業」など様々
なサービスの利用者負担も無償となります。
こうした就学前障害児の発達支援事業利用者について
は、保育所・こども園等と併用する場合についても無償
となります。
つづきまして、「プレミアム付商品券について」でござ
いますが、
プレミアム付商品券事業につきましては、本年10月か
らの消費税、地方消費税率の引き上げが低所得者、子育
て世帯の消費に与える影響を緩和するとともに、地域に
おける消費を喚起、下支えすることを目的として実施さ
れるものでございます。
この趣旨に沿って事業を実施する市町村等の実施主体
に、対象となる経費の全額に対して国から財政支援がな
されるというものであり、本市におきましても、国の実
施要領に基づき、定められた手続きにのっとって吉野川
商工会議所や吉野川市商工会等と連携・協力して実施し
ております。
内容については商品券をご購入いただけるのは、住民
税が非課税の方及び3歳未満のお子様のある世帯主、合
わせて1万2,000人の方々に額面2万5,000円
分の商品券を2万円で販売し、ご購入いただけるもので
ございます。
商品券をご利用いただける店舗については、広く市内
から公募し、商品券の使い道は、換金性の高いものは除
外するなど、一定の制限を設けております。
今回の事業は、平成27年度に実施をしたプレミアム
商品券とは異なり、ご購入いただける方を住民税が非課
税の方及び3歳未満のお子様のある世帯主に限っている
ことから、5,000円(販売額4,000円)から購
入できることとしております。
以上でございます。
ありがとうございました。
「幼児教育・保育の無償化」と「プレミアム付商品券」
についての概要を説明していただきました。
この保育料の無償化の質問は、以前から同僚議員も行
っておりますが、保護者の皆さんにとって保育料の無償
化はありがたいことだと思います。
現在、吉野川市内には、吉野川市立認定こども園、私立
認定こども園、乳児保育園、呉郷保育所と様々な施設が
ありますが、今回の保育料無償化による、それぞれの施
設での違いはあるのでしょうか、あるとするならどのよ
うな違いがあるのかお伺いいたします。
また、幼児教育・保育の無償化やプレミアム付商品券に
ついては、どのような手続きや申請が必要なのでしょう
かお伺いします。
また、プレミアム付商品券の取扱店は、8月20日現在で
吉野川商工会議所登録98件、吉野川市商工会登録66件の
合計164件であります。
前回のプレミアム商品券の時は、商工会議所176件、
商工会52件の合計228件と聞いています。
商品券の対象者は前回より少ないと思いますが、取扱店
が少なければ、使い勝手も悪いのではないでしょうか?
商品券の使用期限は令和元年10月1日から令和2年3月31日
までとなっていますが、今後の取扱店の募集についてお
伺いします。
答弁【宮本健康福祉部長】
再問にご答弁申しあげます。
今回の国の制度改正では、全ての3歳?5歳児・住民
税非課税世帯の0歳?2歳児の保育料が無償となります。
と同時に、これまで保育料に含まれていた2号認定児の
副食費につきましては1号認定児と同様に実費徴収する
ことになりました。
本市ではこれまで、国の保育料無償化に先駆けて、
3?5歳児における保育料は、本市独自のカウント方法
により、18歳以下からカウントし第2子以降無償とし
てきたところで、国の制度に合わせ、一律に副食費を負
担していただくことになると、実質的な値上がりとなる
児童がいるため、子育て支援の充実という観点から、月
額4,500円ほどの副食費を助成し、保護者の負担軽
減を図るよう、今議会に予算計上していることころで
あります。
そうした点を踏まえまして、ご質問の「今回の保育料
無償化による、それぞれの施設で違いはあるのか」につ
いてでございますが、
国から示されている副食費の基準額につきましては、
月額4,500円が目安とされており、公立園について
は、国に準じた金額設定としております。
しかしながら、保護者の同意が得られれば4,500
円を超えてもかまわないとも示されており、一部私立
園では身体作りのため、保育所給食の手引きにうたわ
れていない朝の牛乳を提供することとしていることか
ら、若干の増額になるとも聞いております。
また、主食費については、公立園では、これまでど
おり500円を負担していただきますが、一部私立園
では、ごはんを持参するため主食費代を徴収していな
い園もございます。
次に、「幼児教育・保育の無償化にはどのような手
続きや申請が必要なのか」についてでございますが、
現在、保育所・こども園・幼稚園を利用されている
1号認定・2号認定そして非課税世帯の3号認定につ
きましては、特に手続きの必要はありません。
しかしながら、新制度未移行幼稚園につきましては
新1号、鴨島幼稚園で預かり保育を利用されている児
童については、新2号の認定が必要なため申請をして
いただく必要があります。該当児は把握しており、す
でに勧奨通知を発送しております。
また、該当は少ないと考えられますが、幼稚園・認
可保育施設を利用しておらず保育が必要と認められる
方につきましては、新2号・新3号の認定が必要なた
め、認可外保育施設・病児病後児保育など該当施設を
利用する前に、就労証明等添付した認定申請が必要と
なりますので、広報よしのがわやホームページなどで
周知を徹底していきたいと考えております。
次に、プレミアム付商品券については、どのような
手続きや申請が必要なのかについてでございますが、
吉野川市プレミアム付商品券を購入するには、吉野
川市プレミアム付商品券購入引換券が必要となります
ので、事前申請をしていただくことになります。
プレミアム付商品券の購入対象と思われる平成31
年度の住民税が課税されておらず、課税者の扶養親族
でない低所得者の方については、令和元年8月7日に
引換券交付申請書を発送しております。
商品券の購入を希望される場合は、郵送された申請
書の内容等をご確認のうえ、必要事項に記入し、11
月30日(当日消印有効)までに提出していただくこ
ととなります。 提出していただいた後、審査を行い
、該当者には9月より順次、商品券の購入引換券を送
付させていただきます。
平成28年4月2日から令和元年9月30日までに
生まれたお子様がいる世帯主の方は、引換券交付申請
は、必要ありません。 対象となる人には、9月より
お子様の誕生日に応じ、順次購入引換券を送付させて
いただきます。 購入引換券が届きましたら、「購入
引換券」を持参し、社会福祉課及び各支所において、
令和元年10月1日から令和2年2月29日までに商
品券を購入していただくこととなります。
なお、プレミアム付商品券の使用期間は、商品券取
扱登録店舗にて令和元年10月1日から令和2年3月
31日となっております。
次に、今後の取扱店の募集についてでございますが、
広報よしのがわ及びホームページ、吉野川商工会議
所や吉野川市商工会が開催する会議等、いろんな場面
で周知をさせていただき、今後においても、取扱店の
募集を行ってまいりたいと考えております。
以上でございます。
ありがとうございました。
詳細な説明を頂き、よく理解できました。
8%から10%に引き上げられた消費税分は、子ども
、子育て、医療や介護、年金、高等教育など子育て世
代や現役世代を含む全世代を対象とする社会保障の充
実と安定や、待機児童の解消、幼児教育・保育の無償
化、高等教育の無償化、介護職員の処置改善などに使
われることになっています。
景気対策として実施されるプレミアム付商品券を有
効に利用して、地域消費の喚起と景気の下支えとなる
事を期待して、この質問を終わりたいと思います。
それでは、最後の質問に移りたいと思います。
3. 英語教育の充実について
(1) 英語教育の現状と今後の対応は
(2) 英語検定受検への取り組みは
(3) JETプログラムの積極的な取り組みは
であります
本市の英語教育の充実について質問いたします。
グローバル化の進展の中、英語教育についての新学習
指導要綱が示され、小学校での外国語教育が重視され
ています。
令和2年度からは、小学校5年6年生に導入されていた
外国語活動が小学校3年4年生に、そして小学校5年6年
生には、英語が教科として導入されます。これまでも小
学校では、外国語活動として、「聞く」・「話す」を中
心とした外国語教育に取り組んで、コミュニケーション
力の向上に力を入れてきましたが、今回の改定で、中学
校で実施している英語教育と同様に、「聞く」・「話す」
に加えて、「読む」・「書く」の活動も加わります。
これまでは指定されていなかった単語数も、小学校3年
から6年で600?700語、中学校では現行の1200語程度か
ら、今後は1600?1800語程度へと増加しています。
このような時代の動きに対して、小学校や中学校での授
業の形態が大きく変わろうとしています。
そこで、1点目として大きく変わろうとしている外国語
教育に対して、本市の英語教育の現状と今後の対応をお
伺いいたします。
2点目として、英語教育の充実を目指し、生徒達の学習
意欲向上にもつながる英語検定等の受検への市の取り組
みはどうなのかをお伺いいたします。
3点目として、JETプログラム、これは「語学指導等
を行う外国青年招致事業」The Japan Exchange and
Teaching Programme(ザ・ジャパン・エックスチェン
ジ・アンド・ティーチング・プログラム)の略称で、
地方自治体が総務省、外務省、文部科学省及び一般財団
法人自治体国際化協会の協力の下に実施しているもので
、主に海外の青年を招致し、地方自治体、教育委員会及
び全国の小・中学校や高等学校で、国際交流の業務と外
国語教育に携わることにより、地域レベルでの草の根の
国際化を推進することを目的としています。
本市において、このJETプログラムへの取り組みは
どうなのか、以上3点を質問いたします。
答弁【住友副教育長】
「英語教育について」のご質問に、ご答弁申し上げます。
1点目の「現在の英語教育の現状と今後の対応は」とのご
質問について申し上げます。
小学校においては、2年間の移行期間を経て、来年度より
新学習指導要領が本格実施となり、3・4年生は、週1時
間・年間35時間の「外国語活動」を、5・6年生は、週
2時間・年間70時間の教科である「外国語科」の学習を
実施します。
本市の小学校では、授業時数確保のため、週授業時数を
1時間増やすなどの対応をし、今年度よりすでに、本格実
施時と同様の授業時数にて外国語学習を行っております。
デジタル教科書やALT及び英語専科教員等を有効活用し
、外国語による聞くこと、読むことならびに話すこと、
書くことの言語活動を通して、コミュニケーションの素地
と基礎となる資質・能力を育成することを目指しております。
令和3年度から本格実施の中学校については、小学校の学び
を踏まえ、コミュニケーションを図る資質・能力を育成する
ことを目指すべく、現在移行期間中であります。
本市では、グローバル社会を生きる子供たちに求められる
力を育成するため、小中学校における外国語活動・英語教
育の充実をめざした取組をこれまでも推進してまいりました。
本市小中学校生を対象とした子ども英語教室やイングリッ
シュキャンプの開催、ALTの増員、小学校教員を対象と
しました英語ミニ研修会の取組でございます。
これら本市児童生徒の英語力の向上に貢献しております取組
のさらなる充実を図るとともに、新学習指導要領の本格実施
にともなう、ハード・ソフト両面のさらなる充実を図るべく、
教育委員会といたしまして、しっかりと学校現場と連携して
まいります。
2点目の「英語検定受検への取組は」とのご質問について申
し上げます。
本市の外国語教育・英語教育の充実をめざした取り組みの
ひとつに「英語検定検定料補助制度」があり、これは本市
の「まち・ひと・しごと創生」総合戦略の基本目標であり
ます「特色ある学校教育の推進」をめざした事業であります。
平成28年度より、実用英語技能検定を効果的に活用し「聞く」
「話す」「読む」「書く」の英語4技能をバランスよく身に
つけることができるよう、また受検をとおして生徒の英語
学習への関心、意欲を高めることができるよう、検定料の
一部を補助しております。
補助対象級は1級から5級のうち、準2級から4級となっており
、準2級検定料4900円のうち3600円を、3級検定料3900円の
うち2900円を、4級検定料の2600円のうち1900円をそれぞれ
補助しております。補助は、1年度につき1回限りとなって
おります。
英検3級程度以上を達成した中学校3年生の割合を50%以上
にすることを具体的な目標とし、本事業がスタートいたしま
した平成28年度当初は、44.4%であった割合が、平成
29年度は57.7%、平成30年度は64.2%と、目標数値
を上回る結果を残しており、本市の英語力の向上を示す具体
例のひとつであると考えます。
3点目の「JETプログラムの積極的な取組は」とのご質問に
ついて申し上げます。
本市では、現在6名の外国語指導助手ALTを採用しており、
うち5名がJETプログラムによるALTであり、平成28年
7月現在には3名であったJETプログラムによるALTで
ありますが、同年8月には4名、平成30年8月には5名へ増員と
なり、現在にいたっております。
ALTを増員し適切に各校に配置することで、児童生徒は、
英語をより身近に感じ、英語に対する興味関心を増すことに
つながっており、授業において「聞く・話す」機会をさらに
充実することができております。
また、本市の英語教育推進の取組であります、小中イングリ
ッシュキャンプにもスタッフとして参加し、児童生徒および
教員と積極的にコミュニケーションをとり、運営に大きく寄
与ができておりました。
ALTがよりスムーズに学校現場とコミュニケーションをと
り、児童生徒の外国語教育、英語教育に資することができる
よう、配置数・配置方法等を含めた、制度の充実・改善に向
けて、教育委員会として適切に対応してまいります。
以上でございます。
ありがとうございました。
現在の英語教育の現状と今後の対応について、英語検定受検
への取り組みについて、JETプログラムの積極的な取り組
みについてのご答弁を頂きました。それでは再問をさせてい
ただきます。
薫風会の研修として、平成30年1月23日に国会の衆議院
会館において、次年度から始まる小学校の外国語教育につい
て、文部科学省初等中等教育局幼児教育課振興係長よりレク
チャーを受けました。
内容としては、ご答弁にもあった部分もございますが
2020年から小学校3、4年生から「外国語活動」が新
たに始まる。5、6年生では外国語が「教科」になる。
2018年、2019年度は、移行措置期間である。
中学校では、2021年度から、授業は外国語で行うことが
基本となり、対話的な活動や、実際に活用する言語活動を重
視する。
高校では、2022年度から、「聞く」「読む」「話す」
「書く」を総合的に学び発信力を高める。
「大学入試」では2020年度から、外部検定試験を活用し
「読む」「聞く」「話す」「書く」の4技能が評価される。
英語教員などの体制整備の面では平成30年度1000人、
平成31年度1000人、平成32年度には2000人を専
門指導のための加配措置を行う。
小学校における外国語教育の指導体制は、専科教員が学級担
任の負担を軽減する。ALTも学級担任を英語面でサポート
して、生きた英語の提供を行う。
英語教育推進リーダーが各地域の小学校中核教員の指導力研
修を行う。
研修を受けた中核教員が、ALTプラス外部人材など校内研
修などを行い英語指導力に優れた小学校教員を育成・輩出する。
JETプログラムに係る地方財政措置については、現行措
置に加え、市町村におけるJETプログラムコーディネーター
の活用に要する経費について、特別交付税措置がある。
小学校移行期間中(平成30・31年度)の5・6年生は新
たに年間15単位時間を加え、50単位時間を確保し、外国
語活動の内容に加えて外国語科の内容を扱う。外国語科の内
容については、中学校との接続の観点から、最低限必要な内
容と、それを活用して行う言語活動を中心に取り扱う。
平成31年から、教員養成大学で、小学校の先生を選べば英
語の指導方法を学ぶようになるなどの説明を受けました。
ただし毎年、財務省と折衝して予算が通ればとのことでした。
また、担当者に現在、小学校では、月・火・水・金が6コマ
で木曜が5コマの授業であるが、この上に1コマ増えれば、
現場での仕事量が増えるばかりであるが文部科学省はどう思
っているのかと問うと、働き方改革で教員の定数を増やすよ
うに財務省に交渉した、専門の英語教員を増やす方向で進め
ていく。との答弁でしたが現状はどうなのでしょうか、
お伺いします。
JETプログラムにつきましては、現在の人員では不足が
ちだと思われますので、より良い人材をより多く確保出来る
ように県へ粘り強く要望して下さい。
英語検定につきましては、中学校1年生レベルで5級、2
年生レベルで4級、3年生レベルで3級、その上が準2級、
2級となっているそうですが、現在英語検定補助事業は、4
級の検定料2600円に対し1900円を補助し自己負担額
が700円、3級の検定料3900円に対し補助が2900
円で自己負担が1000円、準2級の検定料4900円に対
し補助額が3600円で自己負担額1300円となっています。
検定料の補助は1年度につき一度限りで、1年に2回受験する
場合は自己負担となるとのことです。
また、この補助制度で中学校卒業時には50%の生徒が「英
検3級以上」の資格取得を目指すとのことです。
各級の受検志願者と合格者は年々増加傾向にあるというこ
とで、生徒達の頑張りを補助金等で応援出来ていると思いま
すが今後小学校での英語の授業が始まれば、児童・生徒達の
英語に対しての学習意欲が高まり、自分の実力を計るために
英語検定の受検者は増加すると思います。
また、中学生でも準2級のレベルではものたらずに,2級
や準1級へのチャレンジをしたい生徒もいると聞いておりま
すが2級の検定料5500円には現在市の補助はありません。
また、英語検定の入口の5級の受検料2000円にも補助
がありません。子どもたちの未来のために、学習意欲を高め、
英語力を育成するために、この英語検定料補助事業はあると
思いますので、5級から2級までの英語検定受検者にも補助
制度を拡大出来ないかをお伺いいたします。
さらに、現在の検定料の補助は、1年度につき1回限りと
なっており、1年度に4級、3級と級を変えて2回受験して
も補助は1回となっていますが、チャレンジ精神を養うため
にも1年間で3回ある英語検定試験で、上級の検定を受検す
る者に対しての補助は出来ないかお伺いします。
鉄は熱いうちに打てとのことわざもあり、英語の学習意欲に
燃えている時ほど、大人が後押しするのが良いのではないで
しょうか。
本市の生徒達の、英語学習の意欲をより高めるためにも、よ
り良い制度となるよう補助事業を拡大できないかをお伺いし
ます。
答弁【住友副教育長】
岸田議員の再問について、ご答弁いたします。
1点目の「小学校外国語教育指導体制の充実にむけた、英語
専科教員の配置状況は」とのご質問について申しあげます。
ご質問の中で説明いただいたように、文部科学省におきまし
ては、新学習指導要領全面実施にむけた指導体制の強化・充
実を図るべく、様々な取り組みを打ち出しております。
なかでも、新学習指導要領の円滑な実施と学校における働
き方改革といたしまして、「小学校英語教育の早期化・教科
化に伴う、一定の英語力を有し、質の高い英語教育を行う専
科指導教員の充実」を薦めております。
本市では、現在1名の英語専科教員が配置されております。
2校を兼務している状況ではありますが、指導体制の充実・
強化に向け、さらなる増員が望まれるところであります。
2点目の「英語検定料補助事業の補助対象級ならびに補助回
数の拡大にむけての対応は」とのご質問につきまして、お答
えいたします。
来年度の小学校学習指導要領全面実施に向けた、本市なら
びに市内各小学校のこれまでの取り組みにより、児童の英語
に対する興味関心・学習意欲は高まってきております。
教育委員会におきましては、本事業の具体的な目標であり
ます「英語検定3級以上を達成した中学3年生の割合を50%
以上にすること」を基本としながらも、小学校ならびに中学
校新学習指導要領全面実施による外国語教育・英語教育のさ
らなる充実を考慮した英語検定料補助対象級の拡大を前向き
に検討してまいります。
なお、検定料補助の回数拡大につきましては、小学校での
英語教育推進にともなう英語力向上を考慮しますと、今後の
受検者数の動向が不透明であるため現在は考えておりません。
以上でございます。
ありがとうございました、
前向きに検討して頂くということで、来年度からは英語検
定を受検する生徒達の励みになると思います。
検定料補助の回数につきましては、受検者数の動向がはっ
きりと分かる段階で、再考して頂ければと思います。
義務教育の場では、学校での学習に取り組むことが大切で
あると考えますが、年齢が進むにつれ、また社会人となっ
たら、みずから資格試験を受検し、キャリアアップするこ
とも大切で、早い段階からそのような習慣を身に着けるこ
とも大切な事だと思います。
2020年度から大学入試改革で、現センター試験は廃止され
、新たに共通テストが先行実施されます。小学校では次期
学習指導要領が全面実施され、2021年度からは中学校でも
次期学習指導要領が全面実施されます。
学習指導要領の改訂の考え方では、これからの教育課程
の理念として、「よりよい学校教育を通じて、よりよい社
会を創るという目標を学校と社会が共有し、それぞれの学
校において、必要な教育内容をどのように学び、どのよう
な資質・能力を身に付けられるようにするかを明確にしな
がら、社会との連携・協働によりその実現を図っていく。
」とありますが、本市において、どのような姿勢で取り組
んで行くかを教育長にお伺いします。
答弁【石川教育長】
「これからの教育課程の理念に対する本市の取組姿勢は」
とのご質問について申しあげます。
新学習指導要領における改善点の基盤となる考え方が「社
会に開かれた教育課程」であります。
今後は,「社会や世界の状況を幅広く視野に入れ,よりよ
い学校教育を通じてよりよい社会を創るという目標をもち,
教育課程を介してその目標を社会と共有していくこと」なら
びに「グローバル化がますます進むであろう,これからの社
会を創りだしていく子ども達が,社会や世界に向き合い関わ
り,自らの人生を切り開いていくために求められる資質・能
力とは何かを,教育課程において明確化し、育んでいくこと
」等が求められます。
教育委員会といたしましては,家庭・地域と連携し,学校
の特色を生かした教育過程をより具現化できるよう人的・物
的資源の活用を積極的に支援してまいります。
また,グローバル社会を生き抜く力を育むべく,これまで
の英語教育に対する取組をさらに進めてまいります。
ありがとうございました。
時代の変化と共に、学習要領の内容も変化してきます。
グローバル化の中、英語教育の比重は高まるばかりです。
今後も、さまざまな取り組みを通じて子供たちの力を伸ばして
頂く事を要望して、薫風会の代表質問を終わりたいと思います。
ありがとうございました。
7月10日(水)10時から もりおか歴史文化館
もりおか歴史文化館総括責任者 小野 芳史
盛岡市議会事務局議事総務課副主幹 朴田 勝
小野芳史総括責任者あいさつ
河野利英薫風会代表あいさつ
○もりおか歴史文化館について
もりおか歴史文化館は、県立図書館を増改築して平成2
3年に盛岡城跡公園内に開館した。盛岡城と城下町を一つ
のエリア(フィールドミュージアム)として、地域の活性
化に貢献することを目的にしている。
1階では、盛岡の祭りや旬の観光情報を紹介している。
祭り常設展示室では、「チャグチャグ馬コ」と「盛岡さん
さ踊り」を映像で紹介。馬コ(模型)の装束は見事である。
山車展示ホールでは、高さ9mもある明治時代の山車や
現在の山車を展示
2階は、盛岡の歴史常設展示室になっている
盛岡城築城以前の盛岡藩領の全体図や新山舟橋などを
展示
城下町盛岡の展示では、藩政時代の街並みや参勤交代の
様子を映像で再現盛岡城と南部家の関りやあらましを紹介
南部家ゆかりの品々を展示、武具・衣装・文書・書画な
どを展示
藩政の終わりから盛岡市誕生までのあゆみを展示して
いる。
質疑応答
Q.山車は何人で巡行するのか?
A.250人から300人が交代で一日中(10時から5
時まで)巡行するので人数は必要(盛岡市は、坂が多
いので大変)
Q.山車は年々作成するのか?
A.市内で36山車あるが、4年に1回出すので、毎年8
台出ている。
東京(浅草)の影響を受けているので、前面は歌舞伎、
裏面は昔話が多い
山車は上から、天・地・海を表現している。
飾りは主に紙で作っているので雨に弱いので、予備を
何セットも作る
Q.盛岡城の石垣はどのように積まれたのか?
A.地中に石は多く埋まっている、穴太衆が積んだのでは
ないかと言われている
Q.城跡に烏帽子岩があったが、どこから運んできたのか
A.地面を掘っていたら、地中から出てきた。
Q.石垣が一部壊れているが、どうするのか?
A.石垣を修復する職人がいないので、入札しても応募が
無いので弱っている
Q.年間の来場数はどのくらいいるのか?
A.大体年間で22万から25万人の来場者数がある
修学旅行とか自主研究の小学生が多くやって来る
山添純二議員お礼の言葉
所感:前日から盛岡市駅前のホテルに宿泊したが、翌朝に
はホテルまで朴田盛岡市議会事務局議事係長にバ
スで迎えに来て頂いた。
バスで市内を走りながら、盛岡市内の様子を説明し
ていただいた。
もりおか歴史文化館は盛岡城内にあり、総括責任者
の小野氏の盛岡市に関する詳しい説明をして頂い
た。
盛岡市は東北では歴史を誇る有数のまちであり、盛
岡城の城下町として栄えたまちでもある。
南部家の数々の至宝なども展示されていて、勉強に
なった。また、庶民の祭り「チャグチャグ馬コ」「も
りおかさんさ踊り」や高さ9mもある明治時代の山
車「和藤内」と現在の山車「連獅子」などが展示さ
れており、その絢爛豪華さに目を奪われました。
吉野川市も、古くは忌部の文化や歴史、麻植郡の
歴史など誇れるものが多くあるので、ぜひともこの
ような歴史文化館を設置して、後世の人達に
素晴らしい文化や歴史残していきたいものです。
もりおか歴史文化館総括責任者 小野 芳史
盛岡市議会事務局議事総務課副主幹 朴田 勝
小野芳史総括責任者あいさつ
河野利英薫風会代表あいさつ
○もりおか歴史文化館について
もりおか歴史文化館は、県立図書館を増改築して平成2
3年に盛岡城跡公園内に開館した。盛岡城と城下町を一つ
のエリア(フィールドミュージアム)として、地域の活性
化に貢献することを目的にしている。
1階では、盛岡の祭りや旬の観光情報を紹介している。
祭り常設展示室では、「チャグチャグ馬コ」と「盛岡さん
さ踊り」を映像で紹介。馬コ(模型)の装束は見事である。
山車展示ホールでは、高さ9mもある明治時代の山車や
現在の山車を展示
2階は、盛岡の歴史常設展示室になっている
盛岡城築城以前の盛岡藩領の全体図や新山舟橋などを
展示
城下町盛岡の展示では、藩政時代の街並みや参勤交代の
様子を映像で再現盛岡城と南部家の関りやあらましを紹介
南部家ゆかりの品々を展示、武具・衣装・文書・書画な
どを展示
藩政の終わりから盛岡市誕生までのあゆみを展示して
いる。
質疑応答
Q.山車は何人で巡行するのか?
A.250人から300人が交代で一日中(10時から5
時まで)巡行するので人数は必要(盛岡市は、坂が多
いので大変)
Q.山車は年々作成するのか?
A.市内で36山車あるが、4年に1回出すので、毎年8
台出ている。
東京(浅草)の影響を受けているので、前面は歌舞伎、
裏面は昔話が多い
山車は上から、天・地・海を表現している。
飾りは主に紙で作っているので雨に弱いので、予備を
何セットも作る
Q.盛岡城の石垣はどのように積まれたのか?
A.地中に石は多く埋まっている、穴太衆が積んだのでは
ないかと言われている
Q.城跡に烏帽子岩があったが、どこから運んできたのか
A.地面を掘っていたら、地中から出てきた。
Q.石垣が一部壊れているが、どうするのか?
A.石垣を修復する職人がいないので、入札しても応募が
無いので弱っている
Q.年間の来場数はどのくらいいるのか?
A.大体年間で22万から25万人の来場者数がある
修学旅行とか自主研究の小学生が多くやって来る
山添純二議員お礼の言葉
所感:前日から盛岡市駅前のホテルに宿泊したが、翌朝に
はホテルまで朴田盛岡市議会事務局議事係長にバ
スで迎えに来て頂いた。
バスで市内を走りながら、盛岡市内の様子を説明し
ていただいた。
もりおか歴史文化館は盛岡城内にあり、総括責任者
の小野氏の盛岡市に関する詳しい説明をして頂い
た。
盛岡市は東北では歴史を誇る有数のまちであり、盛
岡城の城下町として栄えたまちでもある。
南部家の数々の至宝なども展示されていて、勉強に
なった。また、庶民の祭り「チャグチャグ馬コ」「も
りおかさんさ踊り」や高さ9mもある明治時代の山
車「和藤内」と現在の山車「連獅子」などが展示さ
れており、その絢爛豪華さに目を奪われました。
吉野川市も、古くは忌部の文化や歴史、麻植郡の
歴史など誇れるものが多くあるので、ぜひともこの
ような歴史文化館を設置して、後世の人達に
素晴らしい文化や歴史残していきたいものです。
7月 9日(火)10時から
陸前高田市役所会議室
陸前高田市議会 議 長 伊藤 明彦
陸前高田市防災局防災課課長 中村 吉雄
〃 復興局局長 菅野 誠
〃 復興局復興推進課課長 佐々木 学
〃〃 市街地整備課課長補佐 高橋 宏紀
〃 議会事務局事務課長 熊谷 重昭
伊藤陸前高田市議長あいさつ
河野利英薫風会代表あいさつ
○東日本大震災による被災及び復興状況について
☆陸前高田市における東日本大震災による被害の概況
・地震の状況
発生時間―平成23年3月11日(金)午後2時46分
震源域――岩手県沖から茨木県沖
地震規模―マグニチュード9.0
本市震度―震度6弱(推定)
震源深さ―約24km
・津波の状況
津波浸水高―17.6m(高田町字法量)
浸水面積――13平方メートル(市の総面積の5.5%)
・人的被害状況
死 者 数―1,559人 関連死48名含む
行方不明者―202人
・家屋被害状況
全 壊―3,807世帯
半 壊― 240世帯
一部損壊―3,988世帯
合計8035世帯(津波被害4,065、地震被害3,970)
・その他の主な被害状況
水産物―鮮魚、うに、海藻類・被害額 4,500百万円
水産施設―共同施設、養殖施被害額 14,735百万円
農地―383ha(田336ha、畑47ha)・
被害額 7,700百万円
農業施設―771箇所(水路、ため池等)・
被害額 1,350百万円
☆応急仮設住宅等への入居状況
・市内における応急仮設住宅等への入居状況(令和元年
6月末現在)
世帯数 149世帯 最大時は2139世帯
人 数 366人 最大時は5635人
☆陸前高田市震災復興計画の概要
〈震災復興計画〉平成23年12月策定
将来に向けて希望と夢と安心のもてる本市の復興
ビジョンを示し、多くの方の協働、連携により、本市
の創生と活力向上に繋がる復興を実現しようとする
もの。
〈震災復興実施計画〉平成27年3月策定
震災復興計画に掲げる主要事業について、基本構想や
基本計画の実現に向け、現状に即した見直しや新たに必
要とされる事業を追加したもの。
基本構想の目標期間は、平成23年度から平成30年度
基本計画では、復興基盤整備期(第1期)が平成23年
から25年度)
復興展開期(第2期)が平成26年から30年度)
3つの基本理念、
世界に誇れる美しいまちの創造
ひとを育て、命と絆を守るまちの創造
活力あふれるまちの創造
6つのまちづくり基本方向
災害に強い安全なまち
快適で魅力のあるまち
市民の暮らしが安定したまち
活力あるまち
環境にやさしいまち
協働で築くまち
復興のめざすまちの姿は、
海と緑と太陽との共生、海浜新都市の創造
☆整備事業等
防潮堤や水門の整備
防潮堤は高さ12.5m
避難路の確保、
都市計画道路の整備
市街地のかさ上げ
約10mのかさ上げ
高台部への住宅移転
30団地の造成工事
災害復興公営住宅等整備
11団地895戸の整備
公共施設の整備状況
市役所新庁舎は令和2年度に完成予定(約50億円)
高田松原津波復興祈念公園
震災による犠牲者への追悼と鎮魂、日本の再生に向
けた復興への強い意思を国内外に向けて明確に示す
ことなどを目的とした、復興の象徴となる「復興祈念
公園」を国・県と連携して整備
エリア内には、野球場やサッカー場も整備
高田地区中心市街地の形成
震災前の中心市街地を山側に移動・集約し新たな中
心市街地を形成
奇跡の一本松の保存、復興まちづくり情報館による
情報発信
一本松・高さ25m、幹の直径約90cm、樹齢およ
そ170年
復興に向けた市の予算規模、職員体制
平成22年度11,341百万円→平成31年度73,221
百万円の予算規模
平成22年度は、正職員298名、嘱託61名、臨時
56名の計415名
平成31年度は、正職員238名、嘱託41名、臨時
27名
任期付職員32名、派遣応援職員77
名の計415名
☆他の地方自治体からの派遣応援職員の任期は
令和2年度まで
被災市街地復興土地区画整理事業
市街地は、気仙川を挟んで西に今泉地区(約112ha)、
東に高田地区(約186ha)に別れている。
浸水地域のかさ上げに約4kmのベルトコンベア
を導入し、山の土をかさ上げ部に運搬し、事業スピ
ードをアップした。
☆陸前高田市東日本大震災検証報告書より
平成25年に作成、市内全戸に配布
検証作業から得られた主な反省と教訓
1. 避難が何より重要
命を守るためには避難が何より重要。日頃から
危険な場所や避難先・避難経路などを確認する。
早めの避難を心掛ける。
2. 避難所に逃げたら終わりではない
繰り返し襲ってくる津波に気を配り、さらに高
いところへ避難する。
安全が確認できるまで避難を続ける。
3. 公的な役割を持つ人の安全の確保
災害対応や避難誘導にあたる人も、身の安全の
確保が最優先。
切迫した状況となる前に避難する。
4. 災害に強い安全なまちづくり
住まいの耐震化を促進
5. 社会的弱者も安全に生活できる社会の実現
要配慮者も安全に避難できるようにする。
☆避難とは命を守る行動!
〇指定緊急避難場所と指定避難場所の違い
・指定緊急避難場所=命を守るため・災害の危険から
まず逃げるための場所
・指定避難場所=自宅が被災して帰宅できない場合
一定期間避難生活を送るための場所
〇避難情報について
・レベル5=災害発生情報・命を守る行動―災害が発生
しています
・レベル4=避難勧告・ただちに全員避難―災害発生が
迫っています
避難指示(緊急)
・レベル3=避難準備・高齢者等避難開始・高齢者等は
避難開始!
災害発生のおそれが高まっています
☆外出することでかえって命に危険が及ぶような状況
では、近くの丈夫な 建物や自宅の上階などに避難
(垂直避難)して安全を確保する。
〇情報の入手
・防災行政無線
・緊急速報メール
・消防車などの広報
・市ホームページ
・ツイッターやフェイスブックなどのSNS
・テレビ・ラジオ
・防災行政無線の放送内容を電話やメールで情報提供し
ている
・緊急速報メール
質疑応答
Q.防災行政無線の内容を電話で聞けるとの事だが、回線
数は?
A.現在10回線で対応している
Q.応急仮設住宅にまだ入られている方がいるが、災害復
興公営住宅への案内
は出来ないのか?
A.応急仮設住宅は無償、災害復興公営住宅は収入によっ
て家賃が必要となる
また自宅を新築中の方が待機しているケースもある。
Q.仮設住宅は不要となった時は再利用するのか?
A.県が建てるので不要となったら廃棄するのではないか、
業者のリース分は再利用するのではないか
Q.震災の影響を受けた建物を残すべきだという意見は出
なかったのか?
A.市民からは被災した建物を残す・残さないの両論があ
った
個人企業の米沢商会は息子が屋上のアンテナにつか
まって助かったので、個人の意向で残している。
市としては、被災はしたが犠牲者が出なかった建物は
残していきたい。
県とも協議して、4つの建物を残す予定である。
Q.市の職員数415名を増やすことは考えなかったの
か?
A.一時は、派遣応援職員100名超いたので500名を
超えていた。令和3年以降は減員の予定である。
Q.派遣応援職員77名の給与は?
A.国の復興もあるが、基本的には派遣自治体が支払う。
Q.令和3年からの市の財源や運営は
A.事業の進め方もコスト縮減しながら進める。
包括業務委託(窓口業務等を外部に委託)などの手法
を採用する
Q.市役所の新庁舎の新築費用は
A.50億円強の予定である。令和2年度末に完成予定。
Q.防災行政無線の個別受令機は、全戸に設置するのか
A.防災行政無線の難聴区域の希望者に配布している
Q.全戸に配布はしないのか
A.市内で7500世帯あるので、財源的に厳しい
Q.人口の移動はあるのか
A.震災前は約24,000人、現在は約19,000人で
ある。
Q.高台移転した場合の地域のコミュニティはどうなの
か?
A.移転以前の地域ごとに移転しているので、地域コミュ
ニティは保たれている
川村洋樹副議長お礼のことば
所感:2011年3月11日(金)午後2時46分に岩手
県沖から茨城県沖を震源とするマグニチュード9.
0の規模の地震が起こり、陸前高田市では推定で震
度6弱を記録し、その後に発生した大津波で陸前高
田市だけではなく、東北地方の太平洋側地域は甚大
な被害を被った。
この東日本大震災発災から、1年半後の2012年
11月16日に会派薫風会の視察研修で陸前高田
市を訪れている。
東京から東北新幹線で北上市に向かい、北上市から
はバスで陸前高田市を訪れた。
研修に入る前に、被害を被った市内を視察したが
あまりにも甚大な被害で、担当職員の方の当日の説
明を聞いて想像以上の地獄絵図だったということ
が感じられた。同僚や友人、親せきや家族が大勢犠
牲になっている。市職員の方々も多くいる中を、仮
設プレハブの市役所での研修であったが、伊藤明彦
議長を始め市職員の方々の復興・復旧に向けた強
い決意を感じた視察研修であった。
あれから7年目の視察研修であった、今回は石巻
市からレンタカーで陸前高田市に向かったが、途中
の復興道路が現在も伸延工事中の箇所も多くレン
タカーのカーナビに反映されていない新しい道路
も多くあった。
市役所は、仮設プレハブで以前と同じ場所にあり、
職員や市民の皆さんが多く出入りしていました。
また、市議会議長は伊藤明彦氏が3期連続努めら
れて、久しぶりの再会となりました。
研修の中で、職員の方々の心配は、令和2年度で
復興予算も厳しくなるとの事で、現在の復興・復旧
の対応を進める努力をしているのが伺えた。
市役所も2年後には完成するとのことで、完成後
にまた視察に来て下さいと要望された。
機会があれば、元気になった陸前高田市を再訪し
たいものです。
陸前高田市役所会議室
陸前高田市議会 議 長 伊藤 明彦
陸前高田市防災局防災課課長 中村 吉雄
〃 復興局局長 菅野 誠
〃 復興局復興推進課課長 佐々木 学
〃〃 市街地整備課課長補佐 高橋 宏紀
〃 議会事務局事務課長 熊谷 重昭
伊藤陸前高田市議長あいさつ
河野利英薫風会代表あいさつ
○東日本大震災による被災及び復興状況について
☆陸前高田市における東日本大震災による被害の概況
・地震の状況
発生時間―平成23年3月11日(金)午後2時46分
震源域――岩手県沖から茨木県沖
地震規模―マグニチュード9.0
本市震度―震度6弱(推定)
震源深さ―約24km
・津波の状況
津波浸水高―17.6m(高田町字法量)
浸水面積――13平方メートル(市の総面積の5.5%)
・人的被害状況
死 者 数―1,559人 関連死48名含む
行方不明者―202人
・家屋被害状況
全 壊―3,807世帯
半 壊― 240世帯
一部損壊―3,988世帯
合計8035世帯(津波被害4,065、地震被害3,970)
・その他の主な被害状況
水産物―鮮魚、うに、海藻類・被害額 4,500百万円
水産施設―共同施設、養殖施被害額 14,735百万円
農地―383ha(田336ha、畑47ha)・
被害額 7,700百万円
農業施設―771箇所(水路、ため池等)・
被害額 1,350百万円
☆応急仮設住宅等への入居状況
・市内における応急仮設住宅等への入居状況(令和元年
6月末現在)
世帯数 149世帯 最大時は2139世帯
人 数 366人 最大時は5635人
☆陸前高田市震災復興計画の概要
〈震災復興計画〉平成23年12月策定
将来に向けて希望と夢と安心のもてる本市の復興
ビジョンを示し、多くの方の協働、連携により、本市
の創生と活力向上に繋がる復興を実現しようとする
もの。
〈震災復興実施計画〉平成27年3月策定
震災復興計画に掲げる主要事業について、基本構想や
基本計画の実現に向け、現状に即した見直しや新たに必
要とされる事業を追加したもの。
基本構想の目標期間は、平成23年度から平成30年度
基本計画では、復興基盤整備期(第1期)が平成23年
から25年度)
復興展開期(第2期)が平成26年から30年度)
3つの基本理念、
世界に誇れる美しいまちの創造
ひとを育て、命と絆を守るまちの創造
活力あふれるまちの創造
6つのまちづくり基本方向
災害に強い安全なまち
快適で魅力のあるまち
市民の暮らしが安定したまち
活力あるまち
環境にやさしいまち
協働で築くまち
復興のめざすまちの姿は、
海と緑と太陽との共生、海浜新都市の創造
☆整備事業等
防潮堤や水門の整備
防潮堤は高さ12.5m
避難路の確保、
都市計画道路の整備
市街地のかさ上げ
約10mのかさ上げ
高台部への住宅移転
30団地の造成工事
災害復興公営住宅等整備
11団地895戸の整備
公共施設の整備状況
市役所新庁舎は令和2年度に完成予定(約50億円)
高田松原津波復興祈念公園
震災による犠牲者への追悼と鎮魂、日本の再生に向
けた復興への強い意思を国内外に向けて明確に示す
ことなどを目的とした、復興の象徴となる「復興祈念
公園」を国・県と連携して整備
エリア内には、野球場やサッカー場も整備
高田地区中心市街地の形成
震災前の中心市街地を山側に移動・集約し新たな中
心市街地を形成
奇跡の一本松の保存、復興まちづくり情報館による
情報発信
一本松・高さ25m、幹の直径約90cm、樹齢およ
そ170年
復興に向けた市の予算規模、職員体制
平成22年度11,341百万円→平成31年度73,221
百万円の予算規模
平成22年度は、正職員298名、嘱託61名、臨時
56名の計415名
平成31年度は、正職員238名、嘱託41名、臨時
27名
任期付職員32名、派遣応援職員77
名の計415名
☆他の地方自治体からの派遣応援職員の任期は
令和2年度まで
被災市街地復興土地区画整理事業
市街地は、気仙川を挟んで西に今泉地区(約112ha)、
東に高田地区(約186ha)に別れている。
浸水地域のかさ上げに約4kmのベルトコンベア
を導入し、山の土をかさ上げ部に運搬し、事業スピ
ードをアップした。
☆陸前高田市東日本大震災検証報告書より
平成25年に作成、市内全戸に配布
検証作業から得られた主な反省と教訓
1. 避難が何より重要
命を守るためには避難が何より重要。日頃から
危険な場所や避難先・避難経路などを確認する。
早めの避難を心掛ける。
2. 避難所に逃げたら終わりではない
繰り返し襲ってくる津波に気を配り、さらに高
いところへ避難する。
安全が確認できるまで避難を続ける。
3. 公的な役割を持つ人の安全の確保
災害対応や避難誘導にあたる人も、身の安全の
確保が最優先。
切迫した状況となる前に避難する。
4. 災害に強い安全なまちづくり
住まいの耐震化を促進
5. 社会的弱者も安全に生活できる社会の実現
要配慮者も安全に避難できるようにする。
☆避難とは命を守る行動!
〇指定緊急避難場所と指定避難場所の違い
・指定緊急避難場所=命を守るため・災害の危険から
まず逃げるための場所
・指定避難場所=自宅が被災して帰宅できない場合
一定期間避難生活を送るための場所
〇避難情報について
・レベル5=災害発生情報・命を守る行動―災害が発生
しています
・レベル4=避難勧告・ただちに全員避難―災害発生が
迫っています
避難指示(緊急)
・レベル3=避難準備・高齢者等避難開始・高齢者等は
避難開始!
災害発生のおそれが高まっています
☆外出することでかえって命に危険が及ぶような状況
では、近くの丈夫な 建物や自宅の上階などに避難
(垂直避難)して安全を確保する。
〇情報の入手
・防災行政無線
・緊急速報メール
・消防車などの広報
・市ホームページ
・ツイッターやフェイスブックなどのSNS
・テレビ・ラジオ
・防災行政無線の放送内容を電話やメールで情報提供し
ている
・緊急速報メール
質疑応答
Q.防災行政無線の内容を電話で聞けるとの事だが、回線
数は?
A.現在10回線で対応している
Q.応急仮設住宅にまだ入られている方がいるが、災害復
興公営住宅への案内
は出来ないのか?
A.応急仮設住宅は無償、災害復興公営住宅は収入によっ
て家賃が必要となる
また自宅を新築中の方が待機しているケースもある。
Q.仮設住宅は不要となった時は再利用するのか?
A.県が建てるので不要となったら廃棄するのではないか、
業者のリース分は再利用するのではないか
Q.震災の影響を受けた建物を残すべきだという意見は出
なかったのか?
A.市民からは被災した建物を残す・残さないの両論があ
った
個人企業の米沢商会は息子が屋上のアンテナにつか
まって助かったので、個人の意向で残している。
市としては、被災はしたが犠牲者が出なかった建物は
残していきたい。
県とも協議して、4つの建物を残す予定である。
Q.市の職員数415名を増やすことは考えなかったの
か?
A.一時は、派遣応援職員100名超いたので500名を
超えていた。令和3年以降は減員の予定である。
Q.派遣応援職員77名の給与は?
A.国の復興もあるが、基本的には派遣自治体が支払う。
Q.令和3年からの市の財源や運営は
A.事業の進め方もコスト縮減しながら進める。
包括業務委託(窓口業務等を外部に委託)などの手法
を採用する
Q.市役所の新庁舎の新築費用は
A.50億円強の予定である。令和2年度末に完成予定。
Q.防災行政無線の個別受令機は、全戸に設置するのか
A.防災行政無線の難聴区域の希望者に配布している
Q.全戸に配布はしないのか
A.市内で7500世帯あるので、財源的に厳しい
Q.人口の移動はあるのか
A.震災前は約24,000人、現在は約19,000人で
ある。
Q.高台移転した場合の地域のコミュニティはどうなの
か?
A.移転以前の地域ごとに移転しているので、地域コミュ
ニティは保たれている
川村洋樹副議長お礼のことば
所感:2011年3月11日(金)午後2時46分に岩手
県沖から茨城県沖を震源とするマグニチュード9.
0の規模の地震が起こり、陸前高田市では推定で震
度6弱を記録し、その後に発生した大津波で陸前高
田市だけではなく、東北地方の太平洋側地域は甚大
な被害を被った。
この東日本大震災発災から、1年半後の2012年
11月16日に会派薫風会の視察研修で陸前高田
市を訪れている。
東京から東北新幹線で北上市に向かい、北上市から
はバスで陸前高田市を訪れた。
研修に入る前に、被害を被った市内を視察したが
あまりにも甚大な被害で、担当職員の方の当日の説
明を聞いて想像以上の地獄絵図だったということ
が感じられた。同僚や友人、親せきや家族が大勢犠
牲になっている。市職員の方々も多くいる中を、仮
設プレハブの市役所での研修であったが、伊藤明彦
議長を始め市職員の方々の復興・復旧に向けた強
い決意を感じた視察研修であった。
あれから7年目の視察研修であった、今回は石巻
市からレンタカーで陸前高田市に向かったが、途中
の復興道路が現在も伸延工事中の箇所も多くレン
タカーのカーナビに反映されていない新しい道路
も多くあった。
市役所は、仮設プレハブで以前と同じ場所にあり、
職員や市民の皆さんが多く出入りしていました。
また、市議会議長は伊藤明彦氏が3期連続努めら
れて、久しぶりの再会となりました。
研修の中で、職員の方々の心配は、令和2年度で
復興予算も厳しくなるとの事で、現在の復興・復旧
の対応を進める努力をしているのが伺えた。
市役所も2年後には完成するとのことで、完成後
にまた視察に来て下さいと要望された。
機会があれば、元気になった陸前高田市を再訪し
たいものです。
薫風会・公政麻植会・吉野川市民ファースト合同視察研修
令和元年 7月8日(月)?10日(水)
視察先
宮城県石巻市
岩手県陸前高田市
岩手県県盛岡市
7月 8日(月)14時30分から
石巻市防災センターシュミレーション室
石巻市議会 議 長 木村 忠良
石巻市総務部危機管理対策課事業推進官 木村 伸
石巻市議会事務局政策調査グループ主事 鍵 治彦
木村石巻市議長あいさつ
河野利英薫風会代表あいさつ
○震災復興の取り組みと防災減災対策について
石巻市は平成の大合併によって、1市6町が合併して生
まれた。昔から地震や津波の被害にあい、昭和8年の三陸
沖地震での津波が一番大きく、この時の被害状況を元に被
害想定を行い防災対策をとっていたが、平成23年の東日
本大震災はこの予想を超える大きな被害をもたらせた。
3月11日のマグニチュード9.0、最大震度6強の地
震が約160秒続き、地殻変動が最大1.2m下落、南東
に5.2m移動した。
石巻市の市街地でも、約70cmの地盤沈下があった。
地震が収まって、約30分後に津波が押し寄せた。
地震の被害は、死者3184名、行方不明者417名で
人口の2.3%避難者数は最大で5万人を超え、人口の
31.2%であった。
被災住家棟数は、全壊20038棟、半壊13046棟、
一部損壊23615棟など、76.6%の住家が被害を
受けた。
津波浸水総面積は73?、市内の浸水度は約13.2%、
平野部の浸水度は約30.0%、中心市街地の浸水度は
100%である。
石巻市のハザードマップの想定をはるかに超えた津波
被害であった。
石巻市職員の職員の被害者は48名(死者35名、行方
不明者13名)、家族の犠牲者は98名(死亡66名、
行方不明者32名)で職員の被災率は56.8%であっ
た。
津波避難ビルの指定・・・33社指定
・避難困難区域を解消するための民間整備
・整備事業費を補助(上限額1000万円)
・補助対象は、外付け階段、屋上フェンス、屋上デッキ、
自家発電・蓄電設備
案内表示板、誘導照明灯、備蓄倉庫等
津波避難タワーの整備・・・4基目完成
・避難困難区域を解消するための公共整備
・浸水想定水位以上の高さに避難上有効な場所を確保
・誘導照明灯、備蓄品、太陽光発電装置、蓄電設備を設
置、通信手段の確保
石巻南浜津波復興祈念公園整備事業
・県下唯一の国、県、市の連携による復興祈念公園
・犠牲者への追悼と鎮魂の場を構築し、震災の経験と
教訓を後世に伝承
・総面積 38.8ヘクタール
・平成29年3月起工式→平成32年度完成予定
復旧・復興事業費
石巻市における令和2年度までの復旧・復興事業費は、
国・県が施工する事業を含めると、1兆円を超えると
見込まれている。
●主な財源
〇災害復旧事業
異常な自然災害によって被害を受けた施設を原形に
復旧する事業
事業実施状況(事業費ベース) 約3,666億円
〇東日本大震災復興交付金(根拠法:東日本大震災復興
特別区域法)
東日本大震災により、相当数の住宅、公共施設その他
の施設の減失又は損壊等の著しい被害を受けた地域において、
災害復旧だけでは対応が困難な「失われた市街地の再生」
「生業の再建」等のほか、市町村の多様な復興ニーズに
復興交付金により対応。
事業計画提出状況 計20回提出
配分 約3,958億円(事業費総額は4,853億円)
〇その他
国から県に震災復興特別交付税として交付され、震災
復興基金交付金として、市に交付された震災復興基金に
ついては、被災者の生活支援や地域産業の支援、防災
対策など、主にソフト事業に活用する。
震災復興基金活用状況 約406億円
地域医療復興計画事業費 約205億円
復旧・復興事業費
復旧・復興にかかる事業費の総額は、約1兆2133
億円を予定している。
震災前の石巻市の一般会計歳出予算は617億円で
あったので、約20年分に相当する。(復旧事業費3666
億円、復興事業費8018億円)
☆財源はあるが、職員が足らないので全国の自治体から
応援を頼んでいる。
〇石巻市防災基本条例の制定
東日本大震災を教訓として、石巻市は災害から市民の
生命、身体及び財産を守るためには、災害に強いまちづ
くりを構築することが最重要課題であるとともに、
行政による災害対策には限界があり、「自助」、「共助」
、「公助」の理念に基づき、市民、事業者及び市が相互に
連携し、協力し合い、災害対策に取組むことが必要不可欠
であることを改めて認識しました。
石巻市では、自助・共助・公助の理念のもと、防災意
識を高め、災害に強いまちづくりを目指すことを目的に、
平成26年4月1日に「石巻市防災基本条例」を制定し
ました。
〇災害情報伝達手段の多層化
・衛星電話 孤立集落61箇所
・移動系防災無線
・防災行政無線→デジタル化、中継局の増設
・防災ラジオ・・・FM中継局の増設
・緊急速報メール・SNS
・防災センターの建設
〇災害復旧で苦労したのは
一番困難だったのは、がれきの処分であった。最終的に
は県が処理してくれた。仮設住宅を建てるのや、新たに
住宅地を開発するのに山を切り開いて造成工事をする
のに、個人所有の土地や、相続の出来ていない土地、遺
族の判らない土地などに苦労した。
燃料が無かったので、タンクローリーがやってきたが小
分けする手段がなかったのでタンクローリーを返した
こともある。
質疑応答
Q.開発する山林や土地の所有者がわからない土地はどう
したのか?
A.最終的には、そこの土地を避けて開発した。
Q.復興住宅を、4000戸建てたそうだが、すべて入居
したのか?
A.最初は3000戸の公営住宅の予定だったが、入居者
が増えてきた。
現在は20から30世帯残っている。仮設住宅は家賃無
料。
復興住宅は家賃が必要。仮設住宅は県の仕事。
Q.復興計画に要した期間、メンバーや市民からの意見の
吸い上げは?
A.平成23年4月に震災復興基本方針策定、5月から7
月までに有識者懇談会や市民意見の把握、意見交換会を経
て8月に基本計画骨子策定。11月パブリックコメント、
市民との意見交換会を経て12月22日に石巻市振興復
興基本計画策定した。大学の先生は複数呼んではだめ、
目的を絞って人選する方が良い。
Q.市民意見の選定は?
A.主だった代表者と、一般公募のメンバーを選定した
Q.防災避難所マニュアルは?
A.市の職員のためのマニュアルであって、実際には職員
が行けないので役に立たない。避難所ごとのマニュア
ルが必要ではないか。
市の職員は、各避難所を回って御用聞きのような役目
を果たす。
多くの職員は死亡者や行方不明者への戸籍の対応、道
路や水道などのインフラの復旧、家屋の被害調査など
を行うので、避難所等では共助の精神でボランティア
運営してもらう。出来るものは、民間に委託する。
物資輸送は市職員→自衛隊→佐川急便と時間経過と
共に替わっていった。
応援協定を色々な地方自治体と災害時応援協定を結
んでいる。
Q.町内会への加入率は良いのか?
A.町内会と自主防災会は別組織である。
自主防災会には目的別に色々な補助金を出している。
町内会加入促進には、マンションやアパートの家主さ
んにお願いしている。
自主防災会の結成率は85%である。後は集落別の団
体で活動している。
岸田益雄薫風会副代表お礼の挨拶
所感:石巻市の震災復興の取り組みと防災減災対策につい
ての研修を受けたが、中心市街地がほぼ全域70cm
の地盤沈下があり、浸水したとのことで今回の研修は
市役所の隣に新設された防災センターで実施された。
研修の行われた防災センター3階のシミュレーシ
ョン室では、常時市内の道路(浸水被害のあったアン
ダーパス部分)を数カ所防災カメラで監視していて、
その画像は壁面の大型モニターで見られるようにし
ている。
災害時に的確かつ迅速に被災状況を把握し、救命、
避難や災害応援復旧の指示等を行い、その対応を速
やかにできるよう、地域の防災拠点や避難所、関係
機関との連携が図れる施設となっている。
防災センターは、3階に災害対策本部室、オペレー
ション室、災害対策本部連絡班執務室、コールセン
ター室、通信指令室が連動できるようになっている
そうだ。
2階には災害復旧支援活動部隊詰所、防災関係者等
が協議できる会議や備蓄倉庫や仮眠室などが配置
され、1階はピロティ式となっていた。
屋上には、機械室、自家発電機を配置し、津波や浸
水に強い構造・配置になっている。
また、建物の構造も免震装置が設置され、地震に強
い構造となっている。
平常時には、防災に関する情報の収集・分析、防災
関係業務を行い、防災機能を活用した啓発活動、防
災教育(ワークショップ、セミナー等)を開催し、
日常的に市民や自主防災組織が利用できる施設と
なっている。
今回の研修で説明をして頂いた、石巻市総務部危
機対策課事業推進官の木村 伸氏は市役所の防災
関係で職務を行っていて、定年後に再任用で防災セ
ンターの責任者となった方で、東日本大震災の発災
時から現在 までの復興の歩みを詳しく説明して
いただきました。
また、我々の質問等にも丁寧に答えて頂き、吉野
川市の防災対策の参考になる点も多くあり、実りの
ある研修であったと思う。
追記として、5月15日に石巻議会議員12名が
「エディブルフラワーについて」視察研修で吉野川
市を訪れていただいたが、その時同行していた、木
村忠良石巻市議長から、我々の視察研修に歓迎の言
葉を頂くと共に、地酒「墨廼江」と名産の「笹かま
ぼこ」を頂いたことも記しておく。
令和元年 7月8日(月)?10日(水)
視察先
宮城県石巻市
岩手県陸前高田市
岩手県県盛岡市
7月 8日(月)14時30分から
石巻市防災センターシュミレーション室
石巻市議会 議 長 木村 忠良
石巻市総務部危機管理対策課事業推進官 木村 伸
石巻市議会事務局政策調査グループ主事 鍵 治彦
木村石巻市議長あいさつ
河野利英薫風会代表あいさつ
○震災復興の取り組みと防災減災対策について
石巻市は平成の大合併によって、1市6町が合併して生
まれた。昔から地震や津波の被害にあい、昭和8年の三陸
沖地震での津波が一番大きく、この時の被害状況を元に被
害想定を行い防災対策をとっていたが、平成23年の東日
本大震災はこの予想を超える大きな被害をもたらせた。
3月11日のマグニチュード9.0、最大震度6強の地
震が約160秒続き、地殻変動が最大1.2m下落、南東
に5.2m移動した。
石巻市の市街地でも、約70cmの地盤沈下があった。
地震が収まって、約30分後に津波が押し寄せた。
地震の被害は、死者3184名、行方不明者417名で
人口の2.3%避難者数は最大で5万人を超え、人口の
31.2%であった。
被災住家棟数は、全壊20038棟、半壊13046棟、
一部損壊23615棟など、76.6%の住家が被害を
受けた。
津波浸水総面積は73?、市内の浸水度は約13.2%、
平野部の浸水度は約30.0%、中心市街地の浸水度は
100%である。
石巻市のハザードマップの想定をはるかに超えた津波
被害であった。
石巻市職員の職員の被害者は48名(死者35名、行方
不明者13名)、家族の犠牲者は98名(死亡66名、
行方不明者32名)で職員の被災率は56.8%であっ
た。
津波避難ビルの指定・・・33社指定
・避難困難区域を解消するための民間整備
・整備事業費を補助(上限額1000万円)
・補助対象は、外付け階段、屋上フェンス、屋上デッキ、
自家発電・蓄電設備
案内表示板、誘導照明灯、備蓄倉庫等
津波避難タワーの整備・・・4基目完成
・避難困難区域を解消するための公共整備
・浸水想定水位以上の高さに避難上有効な場所を確保
・誘導照明灯、備蓄品、太陽光発電装置、蓄電設備を設
置、通信手段の確保
石巻南浜津波復興祈念公園整備事業
・県下唯一の国、県、市の連携による復興祈念公園
・犠牲者への追悼と鎮魂の場を構築し、震災の経験と
教訓を後世に伝承
・総面積 38.8ヘクタール
・平成29年3月起工式→平成32年度完成予定
復旧・復興事業費
石巻市における令和2年度までの復旧・復興事業費は、
国・県が施工する事業を含めると、1兆円を超えると
見込まれている。
●主な財源
〇災害復旧事業
異常な自然災害によって被害を受けた施設を原形に
復旧する事業
事業実施状況(事業費ベース) 約3,666億円
〇東日本大震災復興交付金(根拠法:東日本大震災復興
特別区域法)
東日本大震災により、相当数の住宅、公共施設その他
の施設の減失又は損壊等の著しい被害を受けた地域において、
災害復旧だけでは対応が困難な「失われた市街地の再生」
「生業の再建」等のほか、市町村の多様な復興ニーズに
復興交付金により対応。
事業計画提出状況 計20回提出
配分 約3,958億円(事業費総額は4,853億円)
〇その他
国から県に震災復興特別交付税として交付され、震災
復興基金交付金として、市に交付された震災復興基金に
ついては、被災者の生活支援や地域産業の支援、防災
対策など、主にソフト事業に活用する。
震災復興基金活用状況 約406億円
地域医療復興計画事業費 約205億円
復旧・復興事業費
復旧・復興にかかる事業費の総額は、約1兆2133
億円を予定している。
震災前の石巻市の一般会計歳出予算は617億円で
あったので、約20年分に相当する。(復旧事業費3666
億円、復興事業費8018億円)
☆財源はあるが、職員が足らないので全国の自治体から
応援を頼んでいる。
〇石巻市防災基本条例の制定
東日本大震災を教訓として、石巻市は災害から市民の
生命、身体及び財産を守るためには、災害に強いまちづ
くりを構築することが最重要課題であるとともに、
行政による災害対策には限界があり、「自助」、「共助」
、「公助」の理念に基づき、市民、事業者及び市が相互に
連携し、協力し合い、災害対策に取組むことが必要不可欠
であることを改めて認識しました。
石巻市では、自助・共助・公助の理念のもと、防災意
識を高め、災害に強いまちづくりを目指すことを目的に、
平成26年4月1日に「石巻市防災基本条例」を制定し
ました。
〇災害情報伝達手段の多層化
・衛星電話 孤立集落61箇所
・移動系防災無線
・防災行政無線→デジタル化、中継局の増設
・防災ラジオ・・・FM中継局の増設
・緊急速報メール・SNS
・防災センターの建設
〇災害復旧で苦労したのは
一番困難だったのは、がれきの処分であった。最終的に
は県が処理してくれた。仮設住宅を建てるのや、新たに
住宅地を開発するのに山を切り開いて造成工事をする
のに、個人所有の土地や、相続の出来ていない土地、遺
族の判らない土地などに苦労した。
燃料が無かったので、タンクローリーがやってきたが小
分けする手段がなかったのでタンクローリーを返した
こともある。
質疑応答
Q.開発する山林や土地の所有者がわからない土地はどう
したのか?
A.最終的には、そこの土地を避けて開発した。
Q.復興住宅を、4000戸建てたそうだが、すべて入居
したのか?
A.最初は3000戸の公営住宅の予定だったが、入居者
が増えてきた。
現在は20から30世帯残っている。仮設住宅は家賃無
料。
復興住宅は家賃が必要。仮設住宅は県の仕事。
Q.復興計画に要した期間、メンバーや市民からの意見の
吸い上げは?
A.平成23年4月に震災復興基本方針策定、5月から7
月までに有識者懇談会や市民意見の把握、意見交換会を経
て8月に基本計画骨子策定。11月パブリックコメント、
市民との意見交換会を経て12月22日に石巻市振興復
興基本計画策定した。大学の先生は複数呼んではだめ、
目的を絞って人選する方が良い。
Q.市民意見の選定は?
A.主だった代表者と、一般公募のメンバーを選定した
Q.防災避難所マニュアルは?
A.市の職員のためのマニュアルであって、実際には職員
が行けないので役に立たない。避難所ごとのマニュア
ルが必要ではないか。
市の職員は、各避難所を回って御用聞きのような役目
を果たす。
多くの職員は死亡者や行方不明者への戸籍の対応、道
路や水道などのインフラの復旧、家屋の被害調査など
を行うので、避難所等では共助の精神でボランティア
運営してもらう。出来るものは、民間に委託する。
物資輸送は市職員→自衛隊→佐川急便と時間経過と
共に替わっていった。
応援協定を色々な地方自治体と災害時応援協定を結
んでいる。
Q.町内会への加入率は良いのか?
A.町内会と自主防災会は別組織である。
自主防災会には目的別に色々な補助金を出している。
町内会加入促進には、マンションやアパートの家主さ
んにお願いしている。
自主防災会の結成率は85%である。後は集落別の団
体で活動している。
岸田益雄薫風会副代表お礼の挨拶
所感:石巻市の震災復興の取り組みと防災減災対策につい
ての研修を受けたが、中心市街地がほぼ全域70cm
の地盤沈下があり、浸水したとのことで今回の研修は
市役所の隣に新設された防災センターで実施された。
研修の行われた防災センター3階のシミュレーシ
ョン室では、常時市内の道路(浸水被害のあったアン
ダーパス部分)を数カ所防災カメラで監視していて、
その画像は壁面の大型モニターで見られるようにし
ている。
災害時に的確かつ迅速に被災状況を把握し、救命、
避難や災害応援復旧の指示等を行い、その対応を速
やかにできるよう、地域の防災拠点や避難所、関係
機関との連携が図れる施設となっている。
防災センターは、3階に災害対策本部室、オペレー
ション室、災害対策本部連絡班執務室、コールセン
ター室、通信指令室が連動できるようになっている
そうだ。
2階には災害復旧支援活動部隊詰所、防災関係者等
が協議できる会議や備蓄倉庫や仮眠室などが配置
され、1階はピロティ式となっていた。
屋上には、機械室、自家発電機を配置し、津波や浸
水に強い構造・配置になっている。
また、建物の構造も免震装置が設置され、地震に強
い構造となっている。
平常時には、防災に関する情報の収集・分析、防災
関係業務を行い、防災機能を活用した啓発活動、防
災教育(ワークショップ、セミナー等)を開催し、
日常的に市民や自主防災組織が利用できる施設と
なっている。
今回の研修で説明をして頂いた、石巻市総務部危
機対策課事業推進官の木村 伸氏は市役所の防災
関係で職務を行っていて、定年後に再任用で防災セ
ンターの責任者となった方で、東日本大震災の発災
時から現在 までの復興の歩みを詳しく説明して
いただきました。
また、我々の質問等にも丁寧に答えて頂き、吉野
川市の防災対策の参考になる点も多くあり、実りの
ある研修であったと思う。
追記として、5月15日に石巻議会議員12名が
「エディブルフラワーについて」視察研修で吉野川
市を訪れていただいたが、その時同行していた、木
村忠良石巻市議長から、我々の視察研修に歓迎の言
葉を頂くと共に、地酒「墨廼江」と名産の「笹かま
ぼこ」を頂いたことも記しておく。
令和元年6月吉野川市議会定例会が6月5日に開会され、
市議会議長の申し合わせ任期の1年を経過したので
辞職願を提出し市議会議長を辞職いたしました。
退任にあたり、挨拶をする機会を与えて頂きました。
議員の皆様、市長を始め職員の皆様、特に議会事務局の皆様、
1年間ありがとうございました。
昨年の6月4日に議員の皆様のご推挙により、市議会議長を拝命し
自分なりに一生懸命努めてまいりました。
6月定例会では、文教厚生委員長から提出された「独立行政法人
国立病院機構徳島病院の存続を求める意見書」を全会一致で可決し、
厚生労働大臣、独立行政法人国立病院機構理事長に提出しました。
この意見書の全文を「吉野川市議会だより」に掲載し、多くの市民
の目に留まるようになり、地元の有志を始め病院の存続を求める
市民の皆さんが活動を起こし、署名活動が始まり5万6千名余りの
署名が集まり、県内の他の市町村でも存続を求める意見書の賛同を
得て、徳島県議会でも2月定例会において徳島病院存続を求める
決議が可決されました。
議長としても、県市議会議長会、四国市議会議長会で要望し、6月
11日の全国市議会議長会に提案される運びとなりました。
今後も推移を見守りたいと思います。
9月定例会では、台風21号の接近により、9月3日、4日と予定され
ていました一般質問を1日に短縮し、議員各位には夜の8時までと
いう長時間の定例会の開催にご協力いただきました。
ありがとうございました。
この1年間で、一番悲しかったのは、先輩議員の岸田秀樹議員の
ご逝去でした。
お母様の岸田イサ子さんの思いを受け継ぎ 鴨島町の発展のため、
吉野川市の発展のために活躍されていましたが、志半ばで旅立って
いかれました。
これからは、遠いところから吉野川市の平和と発展を見守って
頂きたいと思います。
色々なことを経験させて頂き、長いようで短かった1年間でしたが、
これからは、1議員として元気で明るい吉野川市を目指して議員活動
を続けていきたいと思っておりますので、
議員の皆様、市長を始め執行部の皆様、市職員の皆様には今後とも
ご指導・ご鞭撻を頂きますようお願い申し上げまして、議長退任の
挨拶とさせて頂きます。
ありがとう ございました。
市議会議長の申し合わせ任期の1年を経過したので
辞職願を提出し市議会議長を辞職いたしました。
退任にあたり、挨拶をする機会を与えて頂きました。
議員の皆様、市長を始め職員の皆様、特に議会事務局の皆様、
1年間ありがとうございました。
昨年の6月4日に議員の皆様のご推挙により、市議会議長を拝命し
自分なりに一生懸命努めてまいりました。
6月定例会では、文教厚生委員長から提出された「独立行政法人
国立病院機構徳島病院の存続を求める意見書」を全会一致で可決し、
厚生労働大臣、独立行政法人国立病院機構理事長に提出しました。
この意見書の全文を「吉野川市議会だより」に掲載し、多くの市民
の目に留まるようになり、地元の有志を始め病院の存続を求める
市民の皆さんが活動を起こし、署名活動が始まり5万6千名余りの
署名が集まり、県内の他の市町村でも存続を求める意見書の賛同を
得て、徳島県議会でも2月定例会において徳島病院存続を求める
決議が可決されました。
議長としても、県市議会議長会、四国市議会議長会で要望し、6月
11日の全国市議会議長会に提案される運びとなりました。
今後も推移を見守りたいと思います。
9月定例会では、台風21号の接近により、9月3日、4日と予定され
ていました一般質問を1日に短縮し、議員各位には夜の8時までと
いう長時間の定例会の開催にご協力いただきました。
ありがとうございました。
この1年間で、一番悲しかったのは、先輩議員の岸田秀樹議員の
ご逝去でした。
お母様の岸田イサ子さんの思いを受け継ぎ 鴨島町の発展のため、
吉野川市の発展のために活躍されていましたが、志半ばで旅立って
いかれました。
これからは、遠いところから吉野川市の平和と発展を見守って
頂きたいと思います。
色々なことを経験させて頂き、長いようで短かった1年間でしたが、
これからは、1議員として元気で明るい吉野川市を目指して議員活動
を続けていきたいと思っておりますので、
議員の皆様、市長を始め執行部の皆様、市職員の皆様には今後とも
ご指導・ご鞭撻を頂きますようお願い申し上げまして、議長退任の
挨拶とさせて頂きます。
ありがとう ございました。
薫風会要望
場 所:衆議院第二議員会館会議室
日 時:平成31年1月22日(月)午後2時から
国土交通省水管理・国土保全局
水政課長 松原 英憲
河川環境課河川保全企画室 課長補佐 西尾 正博
水政課河川利用企画調整官 佐々木 玄真
衆議院議員 石田祝稔 政策担当秘書 室岡 利雄
○吉野川に堆積している土砂の撤去について
山川町の川田川から流れ込んでいる吉野川との合流地点で土砂が堆積し、
増水時に水の流れを阻害している。近年の台風やゲリラ豪雨では氾濫危険
水位に達している。
川田川沿岸には多くの住居があり、昨年には「高越小学校・こども園」が
開校・開園した。
万が一にも、川田川が氾濫すれば大規模な被害が発生することが予測され
るため、今回要望を行なった。
国土交通省担当課長から、早ければ30年度第2次補正予算か、31年度
当初予算に入れて頂けるとのことであった。
事前に要望書を送っていたので、すでに調査に入っており、夏前には着工
したいとのことであった。
○国道192号線の舗装補修について(川島町・山川町)
国道192号線はどこも舗装が傷んでいる。
市民からは、家が揺れる、運転中にハンドルがとられるなどの苦情があり、
今回要望を行った。
国土交通省からは、すぐには対応できないが3~5年程度を要して舗装補修
を行うとの返事をいただいた。
場 所:衆議院会館会議室
日 時:平成31年1月22日(月)午後3時から
国土交通省水管理・国土保全局 治水課長 井上 智夫
治水課課長補佐 丸山 和基
国土交通省道路局国道・技術課
道路メンテナンス企画室長 小林 賢太郎
道路メンテナンス企画室道路工事調整係長 宮地 誠
○国道192号の舗装補修について
国道192号は交通量が非常に多いことから、道路における様々な部分の
損傷なども多くなっており、その中でも舗装路面の悪化が際立って見受け
られる。舗装路面の剥離や凸凹などを解消することで、振動や騒音、交通
事故の防止にもつながることから、道路補修について、調査・研究するこ
とを要望した。
〇吉野川堤防兼用道路について
吉野川市から徳島中心街などに通勤や買い物に行く際、国道192号か
県道徳島鴨島線そして吉野川市東部から徳島市不動町までの吉野川堤防
兼用道路を利用している。吉野川堤防兼用道路を延長すれば、通勤時間
帯の混雑解消につながるとともに、利便性が図られるのではないかと考
え、調査・研究を要望した。
場 所:衆議院第二議員会館会議室
日 時:平成31年1月22日(月)午後2時から
国土交通省水管理・国土保全局
水政課長 松原 英憲
河川環境課河川保全企画室 課長補佐 西尾 正博
水政課河川利用企画調整官 佐々木 玄真
衆議院議員 石田祝稔 政策担当秘書 室岡 利雄
○吉野川に堆積している土砂の撤去について
山川町の川田川から流れ込んでいる吉野川との合流地点で土砂が堆積し、
増水時に水の流れを阻害している。近年の台風やゲリラ豪雨では氾濫危険
水位に達している。
川田川沿岸には多くの住居があり、昨年には「高越小学校・こども園」が
開校・開園した。
万が一にも、川田川が氾濫すれば大規模な被害が発生することが予測され
るため、今回要望を行なった。
国土交通省担当課長から、早ければ30年度第2次補正予算か、31年度
当初予算に入れて頂けるとのことであった。
事前に要望書を送っていたので、すでに調査に入っており、夏前には着工
したいとのことであった。
○国道192号線の舗装補修について(川島町・山川町)
国道192号線はどこも舗装が傷んでいる。
市民からは、家が揺れる、運転中にハンドルがとられるなどの苦情があり、
今回要望を行った。
国土交通省からは、すぐには対応できないが3~5年程度を要して舗装補修
を行うとの返事をいただいた。
場 所:衆議院会館会議室
日 時:平成31年1月22日(月)午後3時から
国土交通省水管理・国土保全局 治水課長 井上 智夫
治水課課長補佐 丸山 和基
国土交通省道路局国道・技術課
道路メンテナンス企画室長 小林 賢太郎
道路メンテナンス企画室道路工事調整係長 宮地 誠
○国道192号の舗装補修について
国道192号は交通量が非常に多いことから、道路における様々な部分の
損傷なども多くなっており、その中でも舗装路面の悪化が際立って見受け
られる。舗装路面の剥離や凸凹などを解消することで、振動や騒音、交通
事故の防止にもつながることから、道路補修について、調査・研究するこ
とを要望した。
〇吉野川堤防兼用道路について
吉野川市から徳島中心街などに通勤や買い物に行く際、国道192号か
県道徳島鴨島線そして吉野川市東部から徳島市不動町までの吉野川堤防
兼用道路を利用している。吉野川堤防兼用道路を延長すれば、通勤時間
帯の混雑解消につながるとともに、利便性が図られるのではないかと考
え、調査・研究を要望した。
薫風会研修
場 所:TKP東京駅八重洲カンファレンスセンター
日 時:平成31年1月22日(月)午前10時から
講師:立命館大学政策科学部教授 森 裕之
〇「決算カードから読み取れる!
あなたのまちの本当の財政状況を知る
決算状況【歳入】
☆国と地方の歳出規模(平成28年度決算純計)より
地方の割合(市・県)が58%、国の割合が42%
特に、教育・福祉・公共事業の内政分野の大半は地方の財政で支
えている。
☆財政再建との関係に留意が必要
国・地方間の財政配分(平成28年度)
国民全体の税金97.5兆円(国税59兆円)で60.5%
(地方税38.6兆円)で39.5%
国から地方へ(地方交付税・国庫支出金等)71.1兆円と
地方の歳出97.3兆円の合計168.4兆円が国民へのサービス還元と
なる。
税の歳出の配分比率が逆転(国からの統制)
歳出総額の不足を公債(国債・地方債など)でカバーしている
国から地方へ来る交付金や国庫支出金などが減額されると、地方
が苦しくなるが、国も苦しい。
〇決算カードとは・・・自治体財政の基本情報である。
地方の県・市町村ごとの、普通会計歳入・歳出決算額、各種財政指標などの状況について、各団体ごとに1枚のカードにまとめたもので、各年度に実施した「地方財政状況調査」に基づいて抽出・整理したもの。収入・支出の内訳が記載されている。
☆財政分析のための決算カード
時系列で自治体の財政の変化を描いている
時系列で現れた変化の背景を探る
財政指標の内訳を探る
詳細な内訳は「地方財政状況調査」でさらに調べることが必要
☆「地方財政状況調査」は単年度だけでなく、5年間程度の年度
別を見て、どこに支出がかかっているのか、どこに原因があ
るのかを調べることが必要、さらに本市に類似した市とひか
くすることも重要となる。
人口や地形が似ているところとの比較
○決算状況(歳入)
地方財政の仕組み(H28年度地方歳入決算の内訳)
地方税38.8%(税収が多い所や少ないところなどがある)
地方譲与税・地方特例交付金・地方交付税19.4%
国庫支出金(補助金)15.4%
地方債(借金)10.2%
その他(ふるさと納税他)16.2%
・地方歳入合計 101兆4598億円
◎租税は平均4割程度で残りを地方交付税・国庫支出金等と地方債
で賄っている。また、地方債の返還は地方税又は地方交付税に
よる。
・一般財源が大事で国庫補助金(借金)はこの一般財源で決まる。
また、一般財源が多ければ、補助金も多くなる。
※借金は財源が無ければできない。
アメリカでは、全て各自治体で対応しているため、自治体に貧富
の差がある。日本は基本的人権があるため国が交付金や補助金等
で守ってくれる。
○自治体の歳入を家計で理解する。
息子夫婦世帯(自治体)
夫(サラリーマン)妻(パート)子供(孫)3人(大・高・中学生)
夫の両親世帯(国):祖父・祖母
・一般財源:自治体が独自で使途を決定できる財源
食費・光熱水費・教育費・通信費など
地方の標準的支出にあたる
給与(地方税)、
不足分を国(祖父母)が家計補てんする(地方交付税)
・特定財源:使途が限定されている財源(国庫支出金・地方債等)
大学生の留学費用補助(国庫支出金)使用目的が決まっている
祖父母からの仕送り(特別分)補助事業費
住宅の改修費用(地方債)借金(国・祖父母から)後で返済する
祖父母からの貸付
場 所:TKP東京駅八重洲カンファレンスセンター
日 時:平成31年1月22日(月)午前10時から
講師:立命館大学政策科学部教授 森 裕之
〇「決算カードから読み取れる!
あなたのまちの本当の財政状況を知る
決算状況【歳入】
☆国と地方の歳出規模(平成28年度決算純計)より
地方の割合(市・県)が58%、国の割合が42%
特に、教育・福祉・公共事業の内政分野の大半は地方の財政で支
えている。
☆財政再建との関係に留意が必要
国・地方間の財政配分(平成28年度)
国民全体の税金97.5兆円(国税59兆円)で60.5%
(地方税38.6兆円)で39.5%
国から地方へ(地方交付税・国庫支出金等)71.1兆円と
地方の歳出97.3兆円の合計168.4兆円が国民へのサービス還元と
なる。
税の歳出の配分比率が逆転(国からの統制)
歳出総額の不足を公債(国債・地方債など)でカバーしている
国から地方へ来る交付金や国庫支出金などが減額されると、地方
が苦しくなるが、国も苦しい。
〇決算カードとは・・・自治体財政の基本情報である。
地方の県・市町村ごとの、普通会計歳入・歳出決算額、各種財政指標などの状況について、各団体ごとに1枚のカードにまとめたもので、各年度に実施した「地方財政状況調査」に基づいて抽出・整理したもの。収入・支出の内訳が記載されている。
☆財政分析のための決算カード
時系列で自治体の財政の変化を描いている
時系列で現れた変化の背景を探る
財政指標の内訳を探る
詳細な内訳は「地方財政状況調査」でさらに調べることが必要
☆「地方財政状況調査」は単年度だけでなく、5年間程度の年度
別を見て、どこに支出がかかっているのか、どこに原因があ
るのかを調べることが必要、さらに本市に類似した市とひか
くすることも重要となる。
人口や地形が似ているところとの比較
○決算状況(歳入)
地方財政の仕組み(H28年度地方歳入決算の内訳)
地方税38.8%(税収が多い所や少ないところなどがある)
地方譲与税・地方特例交付金・地方交付税19.4%
国庫支出金(補助金)15.4%
地方債(借金)10.2%
その他(ふるさと納税他)16.2%
・地方歳入合計 101兆4598億円
◎租税は平均4割程度で残りを地方交付税・国庫支出金等と地方債
で賄っている。また、地方債の返還は地方税又は地方交付税に
よる。
・一般財源が大事で国庫補助金(借金)はこの一般財源で決まる。
また、一般財源が多ければ、補助金も多くなる。
※借金は財源が無ければできない。
アメリカでは、全て各自治体で対応しているため、自治体に貧富
の差がある。日本は基本的人権があるため国が交付金や補助金等
で守ってくれる。
○自治体の歳入を家計で理解する。
息子夫婦世帯(自治体)
夫(サラリーマン)妻(パート)子供(孫)3人(大・高・中学生)
夫の両親世帯(国):祖父・祖母
・一般財源:自治体が独自で使途を決定できる財源
食費・光熱水費・教育費・通信費など
地方の標準的支出にあたる
給与(地方税)、
不足分を国(祖父母)が家計補てんする(地方交付税)
・特定財源:使途が限定されている財源(国庫支出金・地方債等)
大学生の留学費用補助(国庫支出金)使用目的が決まっている
祖父母からの仕送り(特別分)補助事業費
住宅の改修費用(地方債)借金(国・祖父母から)後で返済する
祖父母からの貸付
薫風会研修
場 所:参議院会館B1F-B108会議室
日 時:平成31年1月21日(月)午後1時から
総務省自治税務局市町村税課住民税第三係長 本橋 弘行
林野庁林政部企画課(計画課併任)課長補佐 中山 昌弘
○森林環境譲与税について 本橋説明
森林のない市町村にも譲与される分があるので、全ての都道府県・市町村が譲与対象となる。
特に林業や木材産業の方々には長年にわたり待望されていたものである。
建物の木質化など木材利用の促進にも使えるため、使途の決め方により都市部にもメリットが及ぶ森林環境税(仮称)及びそれを財源とする森林環境譲与税(仮称)は森林整備等のために必要な費用を、国民一人一人が広く等しく負担を分担して森林を支える仕組みで、平成36年度より森林環境税(仮称)が課税され(平成35年度までの東日本大震災を受けての防災対策のための住民税均等割字率引き上げ分が終了した後)それを財源とする都道府県・市町村への森林環境譲与税の譲与は、課税に先行して平成31年度から始まる(平成31年度200億円→徐々に増加させ年間600億円程度になる予定)
(1) 森林環境譲与税の使途
・間伐や路網といった森林整備
・人材育成、担い手の確保
・木材利用の促進や普及啓発
(2) 譲与の基準
・譲与割合は、都道府県:市町村 1:9(当初は2:8)
私有林人工林面積 5/10 (林野率に応じて補正)
林業就業者数 2/10
人口 3/10
森林の整備によって
・台風やゲリラ豪雨時の水害対策になる
・林業の活性化につながる
・国産木材の利用促進になる
・荒れ果てた森林の整備につながる
国民一人一人が負担して、森林を整備し本来の姿に帰っていく背策である。県も市もしっかりと取り組んで頂きたい。
質疑応答
Q:広範囲に使用可能であれば、有害鳥獣対策にも使えるのか?
A:いかに森林整備に使うか考えて欲しい
Q:公有林化して山林確保に使用しても良いのか?
A:使途は市町村にゆだねられている
Q:広範囲の整備の仕方を認めてもらえるのか?
A:市町村の判断に任せる。インターネット等で公表し、説明する。
Q:特に中山間地域などで使用したいが?
A:地域の実情に応じて、市町村で判断
Q:期間は?
A:法令では定められていない
Q:経営管理実施権とは、あくまでも地上権?
A:所有権ではなく、森林の経営管理実施権
Q:収入を得るのに長期過ぎて赤字経営になるのでは?
A:経営者の判断に任す、出来ない場合は市町村で管理
Q:市町村でも踏み切れないのでは?
A:採算ベースに合わない時は、公的管理として税を活用
Q:竹林を除去して里山を守ることでも費用は全額出るのか?
A:地域の実情に応じて検討
Q:市町村が手を挙げて申請するのか?
A:目的が大体決まっている交付税に近い仕組み
Q:新しい税を有効に使える施策は何年くらいたてば出てくる?
A:良い事例を集めて、参考にしてもらえるようにする
Q:各年度の譲与税を設定しているが、どのような設定方法か?
A:市町村の体制整備の進捗に伴い、譲与税が徐々に増加する
Q:各自治体で分けたら少ない額になると思うが
A:各自治体で分けると、物凄く期待できる額ではない。
場 所:参議院会館B1F-B108会議室
日 時:平成31年1月21日(月)午後2時から
文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部
施設助成課法規係長 武田 久仁子
○小中一貫校を整備する補助金等について
公立の小・中学校の校舎の施設整備については「義務教育諸学校等の
国庫負担金に関する法律」等に基づき、財政処置を講じている。
★校舎を新たに建設する場合
☆公立学校施設整備費負担金により1/2負担
・教室不足を解消するための新増築
・統合に伴う新増築
・新増築の工事費の国庫負担は「必要面積-保有面積」(整備費資格面積)
の範囲内とされている。
・構造上危険な状態にある建物等の建替え(改築)
「必要面積」とは、教育を行うのに必要な最低限度の面積であり国庫負担
対象とすべき合理的な面積。学級数に応じて定められている。
「保有面積」とは、当該学校が保有している施設の面積。
★既存校舎を改修する場合は学校施設環境改善交付金により1/3補助
(大規模改造事業)
小中一貫教育を行う小・中学校の施設一体型校舎の整備について
・小学校と中学校の施設一体型校舎を整備する場合
【新築】
校舎を新たに建設する場合1/3の補助(ただし、小学校及び中学校
それぞれの建物が構造上危険な状態にあると判断された場合等に限る)
【改築】
既存の校舎を改修し活用(小・中いずれかの建物に集約)する場合1/3の
補助
【大規模改造】
小中一貫教育を行う学校の施設整備に特化した財政措置はないが、小学校
及び中学校のそれぞれについて現行制度を活用し、施設一体型校舎の整備
が行われている。新たに建て替えて小中一貫校にせず、増改築して小中学
校を一体型校舎にすれば、国の補助が得られることになる。
小中一貫校の整備を考える場合には、小中一貫校のメリット・デメリット
をよく協議・検討しなければならない。
☆公立小中学校の老朽化の現状
現在築25年以上で改修を要する小中学校施設が既に7割を超えている
今後15年で、第2次ベビーブーム期に建てられた施設の更新時期が一斉
に到来
また、学校のトイレの状況は、和式トイレが半数以上を占める
☆公立学校の空調の現状
エアコンは、ほとんどの家庭に設置されているが学校への普通教室への
設置は約半数にとどまる。吉野川市は普通教室100%設置
・体育館にもエアコン設置を! 要望多数
☆公立学校のバリアフリー化の状況
公立小中学校の約9割が避難所に指定されているが、何らかのバリアフリー
対策が施されている割合は6割にとどまる。
☆財産処分の取り扱いについて、小中学校の建物を義務教育学校へ転用する
場合の手続きを不要(学校から学校への場合)
質疑応答
Q:エアコンを設置して5年後に休校すれば補助金は返納か?
A:学校以外に使用すれば返納
Q:学校に設置している太陽光パネルは?
A:10年以上経過していれば国庫額不要
Q:補助金に対して返納?他への活用は
A:返納、学校から学校への転用する場合は、移設費用は必要
Q:文科省で、今後体育館に空調整備をする予定は?
A:総務省の緊急防災減災対策事業債を利用するのが確実
Q:猛暑日の体育は屋内外でも実施出来ないので、空調設備が必要
A:優先順位が、普通教室・特別支援教室への新設
Q:その後に体育館の予算要求をする予定?
A:なかなか見通せない
Q:既設の中学校に小学校2校を統合し小中一貫校を整備すると、
補助金は1/2なのか
A:補助金は1/2
Q:残りは何か財政措置はあるのか?
A:残り1/2は9割程度、地方債を充当できる
Q:どのような地方債?
A:学校教育施設等整備事業債、財源対策債のセットで90%充当
Q:補助金の枠は年間でいくら?
A:当初予算で356億円、30年度2次補正で372億円
Q:自治体が31年度に申請すれば何年かかる?
A:施設整備をしたい前年度に申請してもらうので、32年度
Q:32年度予算で設計から?
A:申請時に、設計できる前提で提出してもらう
Q:古い体育館を耐震補強したが老朽化が進み新築したいが?
A:改築工事、建物の状況で1/2か1/3のどちらか
体力度審査で点数が何点かによって申請してもらう
Q:1/2か1/3かの負担割合で、他の財源の起債は可能?
A:改築の場合は1/3の負担割合で自治体26.7%。1/2でも20%程度
Q:統廃合する可能性がある学校施設にエアコン設置は難しい?
A:10年程度使用することに補助、統合時期が明確なら難しい。
Q:統廃合した学校施設にエアコンが残っているが?
A:社会体育施設等に使用するのは可能、財産処分手続きは不要
場 所:参議院会館B1F-B108会議室
日 時:平成31年1月21日(月)午後3時から
厚生労働省子ども家庭局
母子保健課母子保健係長 桝谷 綾子
子育て支援課子育て援助活動支援係長 横井 菜穂子
総務課少子化総合対策室主査 廣川 晶子
内閣府子ども・子育て本部
児童手当管理室財政第二係長 中西 琢也
○産後ヘルパー活用策について
事業の目的
「産後ケア事業」は市区町村が実施し、分娩施設退院後から一定
の期間、病院、診療所、助産所、自治体が設置する場所である。
保健センター等又は対象者の居宅において、助産師等の看護職が中心と
なり、母子に対して母親の身体的回復と心理的な安定を促進するととも
に、母親自身がセルフケア能力を育み母子とその家庭が、健やかな育児
ができるよう支援することを目的とする。
具体的には、母親の身体的な回復のための支援、授乳の指導及び乳房の
ケア、母親の話を傾聴する等の心理的支援、新生児及び乳児の状況に応
じた具体的な育児指導、家族等の身近な支援者との関係調整、地域で育
児をしていく上で必要な社会的資源の紹介等を行う。
実施主体は市町村で、本事業の趣旨を理解し、適切な実施が期待できる
団体等に事業の全部または一部を委託することができる。
対象者は褥婦及び産婦並びにその新生児及び乳児のうち、市町村の担当者
がアセスメントを行い、利用者を決定する。
なお、母親のみの利用を妨げるものではない。
(1)母親
1、身体的側面
ア.出産後の身体的な不調や回復の遅れがあり、休養の必要が在る者
イ.出産後の健康管理について、保健指導の必要がある者
ウ.授乳が困難である者
エ.産婦健康診査を実施した病院、診療所又は助産所で身体的ケアが必要と
認められる者
2、心理的側面
ア.出産後の心理的な不調があり、身近に相談できる者がいない者
イ.産婦健康診査で実施したエジンバラ産後うつ病質問票の結果により心理的ケアが必要と認められる者
3、社会的側面
ア.育児について、保健指導(育児指導)の必要がある者
イ.身体的・心理的不調、育児不安以外に、特に社会的支援の必要がある者
ウ.家族等からの十分な育児、家事等の支援が受けられない者
エ.妊娠したことを、本人及びパートナー、家族が心から喜び、出産を待ち
望んでいた状態でないなど、妊娠・出産に肯定的でない者
(なお、初産婦の場合は、初めての育児等に不安を抱えていること等が
あり、また、経産婦の場合は、上の子供の育児等の負担が大きいこと
等があり、いずれもそれぞれに身体的・心理的負担を抱えているため、
初産・経産については問わない。また、多胎の場合は、出産・育児等
の負担が大きくなることから、産後ケアの利用が考えられる。)
オ.新生児及び乳児 自宅において養育が可能である者
カ.その他、地域の保健・医療・福祉・教育機関の情報から支援が必要と
認める者
4、除外となる者
ア.母子のいずれかが感染症疾患(麻しん、風疹、インフルエンザ
等)に罹患している者
イ.母親に入院加療の必要がある者
ウ.母親に心身の不調や疾患があり、医療的入院の必要がある者
5、対象時期
出産後の母親の身体的な回復や心理的な安定等を目的とする事業
であることから出産直後から4か月頃までの時期が対象の目安と
なるが、母子の状況、地域におけるニーズや社会資源等の状況を
踏まえ市区町村において判断する。
6、実施担当者
助産師、保健師、看護師を1名以上置くこと
ア.心理に対しての知識を有する者
イ.育児等に関する知識を有する者(保育士、管理栄養士)
ウ.本事業に関する研修を受講し、事業の趣旨・内容を理解した関係者
7、事業の種類
産後ケアに対する地域におけるニーズや社会資源等の状況から
宿泊型、アウトリーチ型、デイサービス型(個別・集団)の3種
類の実施方法がある。
8、実施の方法
市区町村は、本人又は家族の申請を受け、産後ケア事業の対象と認め
られた場合は、実施場所と日時を調整し、本人に伝える。
原則として、利用料を徴収するため本人の意向を尊重するよう努める。
また、経済的減免の処置等、利用者の所得に十分配慮する。
ケアの質を保つため市区町村でマニュアルを作成する。また、ケアの
実施後の報告書、利用者に対するアンケート等で事業全体の評価とと
もに、ケアの内容を確認することが求められる。
○宿泊型事業内容
利用者を宿泊させて産後ケアを行う。利用者は産後に家族のサポート
が十分受けられない状況にある者、授乳が困難な状況のまま分娩施設
を退院した者、不慣れな育児に不安があり専門職のサポートが必要で
ある者等、分娩施設の退院後間もない母子が多くなることが想定される。
産後ケア事業は、本人からの申請等により市区町村がアセスメント決定
した上で実施するため、分娩施設での延長入院(産褥入院)とは区別す
る必要がある。
利用期間は、原則として7日以内とし、分割して利用しても差し支えない。
市区町村が必要と認めた場合は、その期間を延長することができる。
実施担当者は、宿泊型の産後ケア事業については、実施場所によらず1名
以上の助産師等の看護職を24時間体制で配置する。病院、診療所で実施
する場合、医療法に基づく人員とは区別することが望ましい。市区町村の
判断により父親、兄姉等の利用者の家族を同伴させることができる。
家族の利用の際は他の利用者に十分配慮する必要があり、その旨あらかじ
め確認する。
【ケアの内容】
ア.母親の身体的ケア及び保健指導、栄養指導
イ.母親の心理的ケア
ウ.適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケア含む)
エ.育児の手技についての具体的な指導及び相談
オ.生活の相談、支援
○実施場所
助産師の保健指導として産後ケアを行う場合は、病院若しくは病床を
有する診療所において本来業務に支障のない範囲で空きベッドを活用
して行う、又は入所施設を有する助産所において行うことが」適切である。
このため、実施に際しては、自治体の医務主管部局・衛生主管部局と十分
に調整を行ってお必要があると考えられる。
※宿泊型の産後ケアを実施する際には、次のいずれかによる方法が
考えられる。
ア、旅館業の許可を得ること
イ、市区町村が助産所の基準に準ずるものとして、あらかじめ定めた
条例等の衛生管理基準に従って実施すること。この場合には、各
市区町村の医務主管部局・衛生主管部局等の関係者とあらかじめ
十分に調整を行っておくことが適切であると考える。
留意事項
ア.利用者に対して持参するもの(健康保険証、母子健康手帳等)を事前に
連絡しておく。緊急時の連絡先も確認しておく。
イ.宿泊期間中に提供する食事については、利用者の身体的回復に配慮し、
また帰宅後の生活の参考になるよう配慮した食事を提供することが望
ましい。
○アウトリーチ型
事業内容
利用者と日時を調整し、利用所の居宅を訪問して保健指導、ケアを行う。
利用者は産後に家族のサポートが十分に受けられない者、身体的心理的に
不安を抱えている者、授乳が困難な状況のまま分娩施設を退院するなど
授乳に支援が必要な者等が想定される。申し込みの内容により、助産師を
はじめとする専門職が十分な時間をかけ、専門的な指導又はケアを行う。
実施担当者は、助産師等の看護職や、利用者の相談内容によっては、保育士
、管理栄養士、心理に関して知識のある者等が実施する。
保健指導又はケアを行うに当たっては、母子の状況を踏まえ十分な時間を
確保することが望ましい。十分な時間、利用目的の指導、ケアができる時間
を市区町村で定めておく。
【ケアの内容】
ア.母親の身体的ケア及び保健指導、栄養指導
イ.母親の心理的ケア
ウ.適切な授乳ができるためのケア(乳房ケアを含む)
エ.育児の手技についての具体的な指導及び相談
※指導及び相談・・・実施場所 利用者の居宅
留意事項
訪問の際は、必ず市区町村が発行する身分証明書を携行する。
本事業の訪問と同時期に行われる産婦訪問、乳児家庭全戸訪問事
業、養育支援訪問事業又は産前・産後サポート事業(アウトリー
チ型)は、それぞれ目的、事業内容が異なる。切れ目なく母子を
支えるため、利用者のその時の状態に合わせた重層的な支援が求
められる。
○デイサービス型
個別又は集団(複数の利用者)に対して、病院、診療所、助産所、保健セン
ター等に来所させて産後ケアを行う。
利用者は、授乳が困難な状況のまま分娩施設を退院した者や、産褥経過が
順調で育児について大きなトラブルは抱えていないものの、日中の支援者や
身近に相談できる者がおらず、現在行っている授乳等の育児方法を確認する
ことによって、不安の軽減が期待できる者等が想定される。また、心身の
疲労が蓄積している場合、レイパスト的な利用をすることも想定される。
※レイパスト:一時中断や延期、小休止などを意味する。
支援者が一時的に代わってお世話をし、育児者にリフレッシュしてもらう
こと。
○個別型
事業内容
病院、診療所、助産所等において、利用者は予約した時間に来所し、
必要なサービスを受ける。個人の相談、ケアに加え仲間づくりを目的と
した相談、グループワーク等を組み合わせて実施することも可能である。
【ケアの内容】
ア.母親の身体的ケア及び保健指導、栄養指導
イ.母親の心理的ケア
ウ.適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む)
エ.育児の手技についての具体的な指導及び相談
留意事項
ア.新生児及び乳児の兄姉を同伴させる際は、他の利用者に十分配慮する
必要があり、その旨あらかじめ確認しておく。
イ.食事を提供する場合は、利用者の身体的回復に配慮し、また、帰宅後の
生活の参考になるよう配慮した食事を提供することが望ましい。
ウ.利用者が飲食物を持参した場合、冷蔵庫を利用する等食品の衛生管理に
留意する。
○集団型
保健指導、育児指導に加え、助産師等の看護職と共に母親同士
が不安や悩みを共有することで仲間づくりにもつながる。
事業内容
複数の利用者に対して、助産師等の看護職が保健指導、育児指
導等を行う。複数の利用者と複数の実施担当者がいることで、
様々な情報を得ることも可能となる。
一部スペースを区切り、授乳スペースとするほか、必要に応じ
て、個別相談、授乳指導、休憩等ができるようにすることが望
ましい。利用者が」、保健指導、育児指導を受けながら、身体
的、心理的ストレスを軽減し、又は仲間づくりができるような
環境づくりに配慮する。
【ケアの内容】
ア.母親の身体的ケア及び保健指導、栄養指導
イ.母親の心理的ケア
ウ.適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む)
エ.育児の手技についての具体的な指導及び相談
※実施場所
ア.病院、診療所、助産所等の多目的室等
イ.保健センター等の空き室等
留意事項
ア.利用者が飲食物を持参した場合、冷蔵庫を利用する等、食品の衛生管理
に留意する。
イ.新生児及び乳児の兄姉を同伴させる際は、他の利用者に十分配慮する必要
があり、その旨あらかじめ確認しておく。
質疑応答
Q:ベビーシッター派遣サービスとはいくらぐらいかかるのか?
A:平均2,000円程度、安くても1,000円程度
Q:ファミリーサポートセンターの中に産後ヘルパーの役割を入れ
ることはできるのか?
A:交付金の中で行われているものは家事支援を認めていない。
預かりや送迎なら大丈夫
Q:ファミリーサポートセンターの利用料金は決まっていないの
か?
A:預かりの金額は国では決めていない。それぞれの市で決めてい
る。負担金の1/3はセンターの運営費・人件費である。
Q:利用金額は、時間当たり800円ぐらいか?
A:平均700円程度である
Q:病児・病後児の預かりの際の問題事例は?
A:実施市町村が少ないので、特になし
Q:ベビーシッター派遣サービスでのベビーシッターは、保育士な
どの有資格者などの決まりがあるのか?
A:研修を受けることや、事故が起こった場合に保険加入は必要
Q:産後ケアで、退院直後の母子に対しての心身のケアや育児のサ
ポートなどの支援実施を利用期間は原則7日以内と限定してい
るがなぜか?
A:7日以内でだいたい大丈夫。必要に応じて延長も可能
Q:産後ケアの利用料は利用者の所得に応じているが、だいたいい
くらくらいか?
A:市町村の判断にゆだねられている
Q:保育料完全無償化はいつから?
A:税収との兼ね合いも見て
Q:市が独自に保育所無料化を行うと、罰則などがあるのか?
A:財源さえあれば、特になし
Q:消費税の内の何%程度つかうのか?
A:年間8000億円ほど
場 所:参議院会館B1F-B108会議室
日 時:平成31年1月21日(月)午後1時から
総務省自治税務局市町村税課住民税第三係長 本橋 弘行
林野庁林政部企画課(計画課併任)課長補佐 中山 昌弘
○森林環境譲与税について 本橋説明
森林のない市町村にも譲与される分があるので、全ての都道府県・市町村が譲与対象となる。
特に林業や木材産業の方々には長年にわたり待望されていたものである。
建物の木質化など木材利用の促進にも使えるため、使途の決め方により都市部にもメリットが及ぶ森林環境税(仮称)及びそれを財源とする森林環境譲与税(仮称)は森林整備等のために必要な費用を、国民一人一人が広く等しく負担を分担して森林を支える仕組みで、平成36年度より森林環境税(仮称)が課税され(平成35年度までの東日本大震災を受けての防災対策のための住民税均等割字率引き上げ分が終了した後)それを財源とする都道府県・市町村への森林環境譲与税の譲与は、課税に先行して平成31年度から始まる(平成31年度200億円→徐々に増加させ年間600億円程度になる予定)
(1) 森林環境譲与税の使途
・間伐や路網といった森林整備
・人材育成、担い手の確保
・木材利用の促進や普及啓発
(2) 譲与の基準
・譲与割合は、都道府県:市町村 1:9(当初は2:8)
私有林人工林面積 5/10 (林野率に応じて補正)
林業就業者数 2/10
人口 3/10
森林の整備によって
・台風やゲリラ豪雨時の水害対策になる
・林業の活性化につながる
・国産木材の利用促進になる
・荒れ果てた森林の整備につながる
国民一人一人が負担して、森林を整備し本来の姿に帰っていく背策である。県も市もしっかりと取り組んで頂きたい。
質疑応答
Q:広範囲に使用可能であれば、有害鳥獣対策にも使えるのか?
A:いかに森林整備に使うか考えて欲しい
Q:公有林化して山林確保に使用しても良いのか?
A:使途は市町村にゆだねられている
Q:広範囲の整備の仕方を認めてもらえるのか?
A:市町村の判断に任せる。インターネット等で公表し、説明する。
Q:特に中山間地域などで使用したいが?
A:地域の実情に応じて、市町村で判断
Q:期間は?
A:法令では定められていない
Q:経営管理実施権とは、あくまでも地上権?
A:所有権ではなく、森林の経営管理実施権
Q:収入を得るのに長期過ぎて赤字経営になるのでは?
A:経営者の判断に任す、出来ない場合は市町村で管理
Q:市町村でも踏み切れないのでは?
A:採算ベースに合わない時は、公的管理として税を活用
Q:竹林を除去して里山を守ることでも費用は全額出るのか?
A:地域の実情に応じて検討
Q:市町村が手を挙げて申請するのか?
A:目的が大体決まっている交付税に近い仕組み
Q:新しい税を有効に使える施策は何年くらいたてば出てくる?
A:良い事例を集めて、参考にしてもらえるようにする
Q:各年度の譲与税を設定しているが、どのような設定方法か?
A:市町村の体制整備の進捗に伴い、譲与税が徐々に増加する
Q:各自治体で分けたら少ない額になると思うが
A:各自治体で分けると、物凄く期待できる額ではない。
場 所:参議院会館B1F-B108会議室
日 時:平成31年1月21日(月)午後2時から
文部科学省大臣官房文教施設企画・防災部
施設助成課法規係長 武田 久仁子
○小中一貫校を整備する補助金等について
公立の小・中学校の校舎の施設整備については「義務教育諸学校等の
国庫負担金に関する法律」等に基づき、財政処置を講じている。
★校舎を新たに建設する場合
☆公立学校施設整備費負担金により1/2負担
・教室不足を解消するための新増築
・統合に伴う新増築
・新増築の工事費の国庫負担は「必要面積-保有面積」(整備費資格面積)
の範囲内とされている。
・構造上危険な状態にある建物等の建替え(改築)
「必要面積」とは、教育を行うのに必要な最低限度の面積であり国庫負担
対象とすべき合理的な面積。学級数に応じて定められている。
「保有面積」とは、当該学校が保有している施設の面積。
★既存校舎を改修する場合は学校施設環境改善交付金により1/3補助
(大規模改造事業)
小中一貫教育を行う小・中学校の施設一体型校舎の整備について
・小学校と中学校の施設一体型校舎を整備する場合
【新築】
校舎を新たに建設する場合1/3の補助(ただし、小学校及び中学校
それぞれの建物が構造上危険な状態にあると判断された場合等に限る)
【改築】
既存の校舎を改修し活用(小・中いずれかの建物に集約)する場合1/3の
補助
【大規模改造】
小中一貫教育を行う学校の施設整備に特化した財政措置はないが、小学校
及び中学校のそれぞれについて現行制度を活用し、施設一体型校舎の整備
が行われている。新たに建て替えて小中一貫校にせず、増改築して小中学
校を一体型校舎にすれば、国の補助が得られることになる。
小中一貫校の整備を考える場合には、小中一貫校のメリット・デメリット
をよく協議・検討しなければならない。
☆公立小中学校の老朽化の現状
現在築25年以上で改修を要する小中学校施設が既に7割を超えている
今後15年で、第2次ベビーブーム期に建てられた施設の更新時期が一斉
に到来
また、学校のトイレの状況は、和式トイレが半数以上を占める
☆公立学校の空調の現状
エアコンは、ほとんどの家庭に設置されているが学校への普通教室への
設置は約半数にとどまる。吉野川市は普通教室100%設置
・体育館にもエアコン設置を! 要望多数
☆公立学校のバリアフリー化の状況
公立小中学校の約9割が避難所に指定されているが、何らかのバリアフリー
対策が施されている割合は6割にとどまる。
☆財産処分の取り扱いについて、小中学校の建物を義務教育学校へ転用する
場合の手続きを不要(学校から学校への場合)
質疑応答
Q:エアコンを設置して5年後に休校すれば補助金は返納か?
A:学校以外に使用すれば返納
Q:学校に設置している太陽光パネルは?
A:10年以上経過していれば国庫額不要
Q:補助金に対して返納?他への活用は
A:返納、学校から学校への転用する場合は、移設費用は必要
Q:文科省で、今後体育館に空調整備をする予定は?
A:総務省の緊急防災減災対策事業債を利用するのが確実
Q:猛暑日の体育は屋内外でも実施出来ないので、空調設備が必要
A:優先順位が、普通教室・特別支援教室への新設
Q:その後に体育館の予算要求をする予定?
A:なかなか見通せない
Q:既設の中学校に小学校2校を統合し小中一貫校を整備すると、
補助金は1/2なのか
A:補助金は1/2
Q:残りは何か財政措置はあるのか?
A:残り1/2は9割程度、地方債を充当できる
Q:どのような地方債?
A:学校教育施設等整備事業債、財源対策債のセットで90%充当
Q:補助金の枠は年間でいくら?
A:当初予算で356億円、30年度2次補正で372億円
Q:自治体が31年度に申請すれば何年かかる?
A:施設整備をしたい前年度に申請してもらうので、32年度
Q:32年度予算で設計から?
A:申請時に、設計できる前提で提出してもらう
Q:古い体育館を耐震補強したが老朽化が進み新築したいが?
A:改築工事、建物の状況で1/2か1/3のどちらか
体力度審査で点数が何点かによって申請してもらう
Q:1/2か1/3かの負担割合で、他の財源の起債は可能?
A:改築の場合は1/3の負担割合で自治体26.7%。1/2でも20%程度
Q:統廃合する可能性がある学校施設にエアコン設置は難しい?
A:10年程度使用することに補助、統合時期が明確なら難しい。
Q:統廃合した学校施設にエアコンが残っているが?
A:社会体育施設等に使用するのは可能、財産処分手続きは不要
場 所:参議院会館B1F-B108会議室
日 時:平成31年1月21日(月)午後3時から
厚生労働省子ども家庭局
母子保健課母子保健係長 桝谷 綾子
子育て支援課子育て援助活動支援係長 横井 菜穂子
総務課少子化総合対策室主査 廣川 晶子
内閣府子ども・子育て本部
児童手当管理室財政第二係長 中西 琢也
○産後ヘルパー活用策について
事業の目的
「産後ケア事業」は市区町村が実施し、分娩施設退院後から一定
の期間、病院、診療所、助産所、自治体が設置する場所である。
保健センター等又は対象者の居宅において、助産師等の看護職が中心と
なり、母子に対して母親の身体的回復と心理的な安定を促進するととも
に、母親自身がセルフケア能力を育み母子とその家庭が、健やかな育児
ができるよう支援することを目的とする。
具体的には、母親の身体的な回復のための支援、授乳の指導及び乳房の
ケア、母親の話を傾聴する等の心理的支援、新生児及び乳児の状況に応
じた具体的な育児指導、家族等の身近な支援者との関係調整、地域で育
児をしていく上で必要な社会的資源の紹介等を行う。
実施主体は市町村で、本事業の趣旨を理解し、適切な実施が期待できる
団体等に事業の全部または一部を委託することができる。
対象者は褥婦及び産婦並びにその新生児及び乳児のうち、市町村の担当者
がアセスメントを行い、利用者を決定する。
なお、母親のみの利用を妨げるものではない。
(1)母親
1、身体的側面
ア.出産後の身体的な不調や回復の遅れがあり、休養の必要が在る者
イ.出産後の健康管理について、保健指導の必要がある者
ウ.授乳が困難である者
エ.産婦健康診査を実施した病院、診療所又は助産所で身体的ケアが必要と
認められる者
2、心理的側面
ア.出産後の心理的な不調があり、身近に相談できる者がいない者
イ.産婦健康診査で実施したエジンバラ産後うつ病質問票の結果により心理的ケアが必要と認められる者
3、社会的側面
ア.育児について、保健指導(育児指導)の必要がある者
イ.身体的・心理的不調、育児不安以外に、特に社会的支援の必要がある者
ウ.家族等からの十分な育児、家事等の支援が受けられない者
エ.妊娠したことを、本人及びパートナー、家族が心から喜び、出産を待ち
望んでいた状態でないなど、妊娠・出産に肯定的でない者
(なお、初産婦の場合は、初めての育児等に不安を抱えていること等が
あり、また、経産婦の場合は、上の子供の育児等の負担が大きいこと
等があり、いずれもそれぞれに身体的・心理的負担を抱えているため、
初産・経産については問わない。また、多胎の場合は、出産・育児等
の負担が大きくなることから、産後ケアの利用が考えられる。)
オ.新生児及び乳児 自宅において養育が可能である者
カ.その他、地域の保健・医療・福祉・教育機関の情報から支援が必要と
認める者
4、除外となる者
ア.母子のいずれかが感染症疾患(麻しん、風疹、インフルエンザ
等)に罹患している者
イ.母親に入院加療の必要がある者
ウ.母親に心身の不調や疾患があり、医療的入院の必要がある者
5、対象時期
出産後の母親の身体的な回復や心理的な安定等を目的とする事業
であることから出産直後から4か月頃までの時期が対象の目安と
なるが、母子の状況、地域におけるニーズや社会資源等の状況を
踏まえ市区町村において判断する。
6、実施担当者
助産師、保健師、看護師を1名以上置くこと
ア.心理に対しての知識を有する者
イ.育児等に関する知識を有する者(保育士、管理栄養士)
ウ.本事業に関する研修を受講し、事業の趣旨・内容を理解した関係者
7、事業の種類
産後ケアに対する地域におけるニーズや社会資源等の状況から
宿泊型、アウトリーチ型、デイサービス型(個別・集団)の3種
類の実施方法がある。
8、実施の方法
市区町村は、本人又は家族の申請を受け、産後ケア事業の対象と認め
られた場合は、実施場所と日時を調整し、本人に伝える。
原則として、利用料を徴収するため本人の意向を尊重するよう努める。
また、経済的減免の処置等、利用者の所得に十分配慮する。
ケアの質を保つため市区町村でマニュアルを作成する。また、ケアの
実施後の報告書、利用者に対するアンケート等で事業全体の評価とと
もに、ケアの内容を確認することが求められる。
○宿泊型事業内容
利用者を宿泊させて産後ケアを行う。利用者は産後に家族のサポート
が十分受けられない状況にある者、授乳が困難な状況のまま分娩施設
を退院した者、不慣れな育児に不安があり専門職のサポートが必要で
ある者等、分娩施設の退院後間もない母子が多くなることが想定される。
産後ケア事業は、本人からの申請等により市区町村がアセスメント決定
した上で実施するため、分娩施設での延長入院(産褥入院)とは区別す
る必要がある。
利用期間は、原則として7日以内とし、分割して利用しても差し支えない。
市区町村が必要と認めた場合は、その期間を延長することができる。
実施担当者は、宿泊型の産後ケア事業については、実施場所によらず1名
以上の助産師等の看護職を24時間体制で配置する。病院、診療所で実施
する場合、医療法に基づく人員とは区別することが望ましい。市区町村の
判断により父親、兄姉等の利用者の家族を同伴させることができる。
家族の利用の際は他の利用者に十分配慮する必要があり、その旨あらかじ
め確認する。
【ケアの内容】
ア.母親の身体的ケア及び保健指導、栄養指導
イ.母親の心理的ケア
ウ.適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケア含む)
エ.育児の手技についての具体的な指導及び相談
オ.生活の相談、支援
○実施場所
助産師の保健指導として産後ケアを行う場合は、病院若しくは病床を
有する診療所において本来業務に支障のない範囲で空きベッドを活用
して行う、又は入所施設を有する助産所において行うことが」適切である。
このため、実施に際しては、自治体の医務主管部局・衛生主管部局と十分
に調整を行ってお必要があると考えられる。
※宿泊型の産後ケアを実施する際には、次のいずれかによる方法が
考えられる。
ア、旅館業の許可を得ること
イ、市区町村が助産所の基準に準ずるものとして、あらかじめ定めた
条例等の衛生管理基準に従って実施すること。この場合には、各
市区町村の医務主管部局・衛生主管部局等の関係者とあらかじめ
十分に調整を行っておくことが適切であると考える。
留意事項
ア.利用者に対して持参するもの(健康保険証、母子健康手帳等)を事前に
連絡しておく。緊急時の連絡先も確認しておく。
イ.宿泊期間中に提供する食事については、利用者の身体的回復に配慮し、
また帰宅後の生活の参考になるよう配慮した食事を提供することが望
ましい。
○アウトリーチ型
事業内容
利用者と日時を調整し、利用所の居宅を訪問して保健指導、ケアを行う。
利用者は産後に家族のサポートが十分に受けられない者、身体的心理的に
不安を抱えている者、授乳が困難な状況のまま分娩施設を退院するなど
授乳に支援が必要な者等が想定される。申し込みの内容により、助産師を
はじめとする専門職が十分な時間をかけ、専門的な指導又はケアを行う。
実施担当者は、助産師等の看護職や、利用者の相談内容によっては、保育士
、管理栄養士、心理に関して知識のある者等が実施する。
保健指導又はケアを行うに当たっては、母子の状況を踏まえ十分な時間を
確保することが望ましい。十分な時間、利用目的の指導、ケアができる時間
を市区町村で定めておく。
【ケアの内容】
ア.母親の身体的ケア及び保健指導、栄養指導
イ.母親の心理的ケア
ウ.適切な授乳ができるためのケア(乳房ケアを含む)
エ.育児の手技についての具体的な指導及び相談
※指導及び相談・・・実施場所 利用者の居宅
留意事項
訪問の際は、必ず市区町村が発行する身分証明書を携行する。
本事業の訪問と同時期に行われる産婦訪問、乳児家庭全戸訪問事
業、養育支援訪問事業又は産前・産後サポート事業(アウトリー
チ型)は、それぞれ目的、事業内容が異なる。切れ目なく母子を
支えるため、利用者のその時の状態に合わせた重層的な支援が求
められる。
○デイサービス型
個別又は集団(複数の利用者)に対して、病院、診療所、助産所、保健セン
ター等に来所させて産後ケアを行う。
利用者は、授乳が困難な状況のまま分娩施設を退院した者や、産褥経過が
順調で育児について大きなトラブルは抱えていないものの、日中の支援者や
身近に相談できる者がおらず、現在行っている授乳等の育児方法を確認する
ことによって、不安の軽減が期待できる者等が想定される。また、心身の
疲労が蓄積している場合、レイパスト的な利用をすることも想定される。
※レイパスト:一時中断や延期、小休止などを意味する。
支援者が一時的に代わってお世話をし、育児者にリフレッシュしてもらう
こと。
○個別型
事業内容
病院、診療所、助産所等において、利用者は予約した時間に来所し、
必要なサービスを受ける。個人の相談、ケアに加え仲間づくりを目的と
した相談、グループワーク等を組み合わせて実施することも可能である。
【ケアの内容】
ア.母親の身体的ケア及び保健指導、栄養指導
イ.母親の心理的ケア
ウ.適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む)
エ.育児の手技についての具体的な指導及び相談
留意事項
ア.新生児及び乳児の兄姉を同伴させる際は、他の利用者に十分配慮する
必要があり、その旨あらかじめ確認しておく。
イ.食事を提供する場合は、利用者の身体的回復に配慮し、また、帰宅後の
生活の参考になるよう配慮した食事を提供することが望ましい。
ウ.利用者が飲食物を持参した場合、冷蔵庫を利用する等食品の衛生管理に
留意する。
○集団型
保健指導、育児指導に加え、助産師等の看護職と共に母親同士
が不安や悩みを共有することで仲間づくりにもつながる。
事業内容
複数の利用者に対して、助産師等の看護職が保健指導、育児指
導等を行う。複数の利用者と複数の実施担当者がいることで、
様々な情報を得ることも可能となる。
一部スペースを区切り、授乳スペースとするほか、必要に応じ
て、個別相談、授乳指導、休憩等ができるようにすることが望
ましい。利用者が」、保健指導、育児指導を受けながら、身体
的、心理的ストレスを軽減し、又は仲間づくりができるような
環境づくりに配慮する。
【ケアの内容】
ア.母親の身体的ケア及び保健指導、栄養指導
イ.母親の心理的ケア
ウ.適切な授乳が実施できるためのケア(乳房ケアを含む)
エ.育児の手技についての具体的な指導及び相談
※実施場所
ア.病院、診療所、助産所等の多目的室等
イ.保健センター等の空き室等
留意事項
ア.利用者が飲食物を持参した場合、冷蔵庫を利用する等、食品の衛生管理
に留意する。
イ.新生児及び乳児の兄姉を同伴させる際は、他の利用者に十分配慮する必要
があり、その旨あらかじめ確認しておく。
質疑応答
Q:ベビーシッター派遣サービスとはいくらぐらいかかるのか?
A:平均2,000円程度、安くても1,000円程度
Q:ファミリーサポートセンターの中に産後ヘルパーの役割を入れ
ることはできるのか?
A:交付金の中で行われているものは家事支援を認めていない。
預かりや送迎なら大丈夫
Q:ファミリーサポートセンターの利用料金は決まっていないの
か?
A:預かりの金額は国では決めていない。それぞれの市で決めてい
る。負担金の1/3はセンターの運営費・人件費である。
Q:利用金額は、時間当たり800円ぐらいか?
A:平均700円程度である
Q:病児・病後児の預かりの際の問題事例は?
A:実施市町村が少ないので、特になし
Q:ベビーシッター派遣サービスでのベビーシッターは、保育士な
どの有資格者などの決まりがあるのか?
A:研修を受けることや、事故が起こった場合に保険加入は必要
Q:産後ケアで、退院直後の母子に対しての心身のケアや育児のサ
ポートなどの支援実施を利用期間は原則7日以内と限定してい
るがなぜか?
A:7日以内でだいたい大丈夫。必要に応じて延長も可能
Q:産後ケアの利用料は利用者の所得に応じているが、だいたいい
くらくらいか?
A:市町村の判断にゆだねられている
Q:保育料完全無償化はいつから?
A:税収との兼ね合いも見て
Q:市が独自に保育所無料化を行うと、罰則などがあるのか?
A:財源さえあれば、特になし
Q:消費税の内の何%程度つかうのか?
A:年間8000億円ほど
薫風会研修
場 所:TKP東京駅八重洲カンファレンスセンター
日 時:平成31年1月23日(月)午前10時から
講師:立命館大学政策科学部教授 森 裕之
〇「決算カードから読み取れる!
あなたのまちの本当の財政状況を知る
決算状況【財政収支】
☆近年の自治体財政の赤字問題
◆歳入歳出差し引き(形式収支):歳入決算額から歳出決算額を単
純に差し引いた額(あくまでも単年度)
歳入歳出差引=歳入決算額―歳出決算額
◆実質収支(黒字か赤字かがわかる)
形式収支から事業繰越などに伴い、翌年度に繰り越すべき財源を
差し引いた額(当該年度に属すべき収入と支出の実質的な差額)
実質収支=形式収支―翌年度へ繰り越すべき財源
※赤字で予算は組めないので必ず黒字にする。
◆財政再建団体
赤字額が標準財政規模の5%(都道府県)または20%(市区町
村)を超えた破綻状態にあり、地方財政再建促進特別措置法(再
建法・廃止)に基づき、財政再建計画を策定し、総務大臣の同意
を得た地方自治体のこと。正式には、準用財政再建団体という。
財政再建団体となることはしばしば企業の倒産に例えられるが、
破産や民事再生法適用の場合と異なり地方債の完済が前提となっ
ている。なお、再建法の要件を満たした自治体が再建法を準用し
ないで自主的に再建する「自主再建」という方法をとることもあ
る。この場合、地方債の発行制限があるなど、国の各種支援措置
は受けられないことになる。
◆単年度収支
当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差引いた額
(当該年度のみの実質的な収支と支出の差額)⇒この金額が年々
下がってきたら危ない。
単年度収支=当該年度の実質収支―前年度の実質収支
◆実質単年度収支
単年度収支に当該年度に措置された黒字要素(財政調整基金積立
金『貯金』地方債繰り上げ償還金(借金の繰り上げ返済))及び
赤字要素(財政調整基金取り崩し額)を除外して実質的な単年度
収支を表わした額。
実質単年度収支=単年度収支+財政調整基金積立額+地方債繰上
げ償還額―財政調整基金取崩し額
★財務省の基金に対する見方
基本増加率と臨時財政対策債の増加率
? 臨財債残高(借金)を増やしながら基金も積増している自治体が
551自治体・・・全体の70%
? 臨財債残高(借金)を増やしながら基金を減らしている自治体が
167自治体・・・全体の2%
? 臨財債残高(借金)を減らしながら基金を減らしている自治体が
15自治体・・・全体の2%
? 臨財債残高(借金)を減らしながら基金も積増している自治体が
51自治体・・・全体の6%
◆借金には、良い借金と悪い借金がある
借金は、市民の負担を公平にすべきである。例えば、箱物を建て
る場合、現金で支払うと、それは今まで住んでいた住民の税金で
支払うことになる。現金支払い後、市外から移住してきた人の負
担はない。しかし、借金で建てると、移住してきた人も税金から
支払うことになるので平等になる。税負担は公平でなければなら
ない。また、借金で建てる方が早く出来、早く提供できる。
場 所:TKP東京駅八重洲カンファレンスセンター
日 時:平成31年1月23日(月)午前10時から
講師:立命館大学政策科学部教授 森 裕之
〇「決算カードから読み取れる!
あなたのまちの本当の財政状況を知る
決算状況【財政収支】
☆近年の自治体財政の赤字問題
◆歳入歳出差し引き(形式収支):歳入決算額から歳出決算額を単
純に差し引いた額(あくまでも単年度)
歳入歳出差引=歳入決算額―歳出決算額
◆実質収支(黒字か赤字かがわかる)
形式収支から事業繰越などに伴い、翌年度に繰り越すべき財源を
差し引いた額(当該年度に属すべき収入と支出の実質的な差額)
実質収支=形式収支―翌年度へ繰り越すべき財源
※赤字で予算は組めないので必ず黒字にする。
◆財政再建団体
赤字額が標準財政規模の5%(都道府県)または20%(市区町
村)を超えた破綻状態にあり、地方財政再建促進特別措置法(再
建法・廃止)に基づき、財政再建計画を策定し、総務大臣の同意
を得た地方自治体のこと。正式には、準用財政再建団体という。
財政再建団体となることはしばしば企業の倒産に例えられるが、
破産や民事再生法適用の場合と異なり地方債の完済が前提となっ
ている。なお、再建法の要件を満たした自治体が再建法を準用し
ないで自主的に再建する「自主再建」という方法をとることもあ
る。この場合、地方債の発行制限があるなど、国の各種支援措置
は受けられないことになる。
◆単年度収支
当該年度の実質収支から前年度の実質収支を差引いた額
(当該年度のみの実質的な収支と支出の差額)⇒この金額が年々
下がってきたら危ない。
単年度収支=当該年度の実質収支―前年度の実質収支
◆実質単年度収支
単年度収支に当該年度に措置された黒字要素(財政調整基金積立
金『貯金』地方債繰り上げ償還金(借金の繰り上げ返済))及び
赤字要素(財政調整基金取り崩し額)を除外して実質的な単年度
収支を表わした額。
実質単年度収支=単年度収支+財政調整基金積立額+地方債繰上
げ償還額―財政調整基金取崩し額
★財務省の基金に対する見方
基本増加率と臨時財政対策債の増加率
? 臨財債残高(借金)を増やしながら基金も積増している自治体が
551自治体・・・全体の70%
? 臨財債残高(借金)を増やしながら基金を減らしている自治体が
167自治体・・・全体の2%
? 臨財債残高(借金)を減らしながら基金を減らしている自治体が
15自治体・・・全体の2%
? 臨財債残高(借金)を減らしながら基金も積増している自治体が
51自治体・・・全体の6%
◆借金には、良い借金と悪い借金がある
借金は、市民の負担を公平にすべきである。例えば、箱物を建て
る場合、現金で支払うと、それは今まで住んでいた住民の税金で
支払うことになる。現金支払い後、市外から移住してきた人の負
担はない。しかし、借金で建てると、移住してきた人も税金から
支払うことになるので平等になる。税負担は公平でなければなら
ない。また、借金で建てる方が早く出来、早く提供できる。

 9時30分 - 17時00分
9時30分 - 17時00分 12月9日
12月9日